「穴」を探る【草森紳一】
「穴」を探る
| 書籍名 | 「穴」を探る |
|---|---|
| 著者名 | 草森紳一 |
| 出版社 | 河出書房新社(216p) |
| 発刊日 | 2009.2.28 |
| 希望小売価格 | 2,100円 |
| 書評日等 | - |
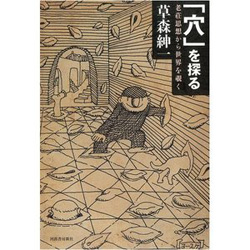
草森紳一という名前は、僕のなかでは「百科全書派」という言葉と結びついている。「百科全書派」は18世紀フランスで森羅万象を科学的に記述した「百科全書」のディドロやダランベール一派を指す。それがなぜ草森と結びついたかといえば、彼がエッセーの対象としたのが専門の中国文学だけでなく、ビートルズやポップアート、マンガ、荷風をはじめとする日本文学、古典から現代までの外国文学、広告、写真、デザイン、ファッション、書道に散歩と、ジャンルからジャンルを横断してとどまるところを知らないからだ。
最初に読んだのは『ナンセンスの練習』(1971)だったと思う。ビートルズの「HELP!」に李賀の詩を重ね、王陽明を論じながらいつの間にか野球の話になっている。狭くタコ壺化した時代に珍しいこの「ひとり百科全書派」は、しかし本場の「百科全書派」とちがって科学より非合理に、啓蒙より美的惑溺に、体系より閃きに傾くように思え、そこが若かった小生の好みにぴったりだった。
2008年に亡くなった草森の『「穴」を探る』には、「老荘思想から世界を覗く」というサブタイトルがつけられている。草森はこう書く。
「この二十年、私は、『穴』なるものに興味をもってきた。いったん『穴』なる入口が見つかると、私の読む本すべてが、この『穴』に集約されていく。それらを並べるとランダムに見えるが、私の中では、きっちりと『穴』で通底されていて、情ないほどに一貫しているわけだ」
何を見、何を読んでも「穴」にこだわった草森の「穴」に関する文章を没後に集めたのがこの本なのである。
「穴」といっても物理的なそれだけでなく、比喩としての「穴」もあれば、思想としての「穴」もある。冒頭におかれた「穴三題」というエッセーでは、三つの「穴」が取り上げられている。
まず「口という洞窟」という見出しで、 楳図かずおのマンガを引いて人体の口が論じられる。マンガではふつう開いた口は真黒に塗られる。でも楳図は「その黒い洞窟の口の中に元気な白い歯と赤い舌まで」描きこむことで、少女の表情が一瞬にして恐怖のため老婆のようになってしまうことを表現する。
「わが国一等の恐怖作家たる楳図かずおは、『穴』なるものに、もっとも関心を寄せているマンガ家である。初期からそうだが、始原的にも人間の恐怖は、『穴』なるものに対してであることを、よく知っているからだ」
続けて草森は映画『イヤー・オブ・ザ・ ドラゴン』に触れ、映画の舞台になるニューヨークのチャイナタウンを都市の穴であると言う。「ニューヨークとて、大迷路である。無数の穴だらけの街のようでもあり、巨大な大穴にも見える。その一角に、東洋の穴、チャイナタウンが異物のように巣食っている」。
楳図かずおの口は人体の物理的な穴だけれど、チャイナタウンは比喩としての穴ということになる。僕はニューヨークのチャイナタウンが大好きで、1年滞在している間に週1度はほっつき歩いたから、そう言いたくなる気分はよく分かる。
確かにここはマンハッタンの他の街と空気が違う。差別的な言い方になるかもしれないけど、チャイナタウンの雑踏を歩いていると、人ではなく虫が蝟集しているなかを自分もまた一匹の虫になって歩いている気分になり、それが心地よくもある。自分もまぎれもなく東洋人だなあと思う。アングロ・サクソンならこの街から異様な感触を受けるだろう。それを草森は穴と表現した。
最後に取り上げられるのは日本画家・小林古径の「いでゆ」。女が二人、風呂に入っているなまめかしい図で、湯が張られた風呂は黒く描かれている。「風呂桶も、一つの穴である。私は、水にも穴を感じるが、それは水が穴なのでなく、水は溶れ物に入って、はじめて水だからだろう。穴があるところ、水はたまる。陰門もまた同じである。水溢れて、はじめて男も入っていける。ここには、安らぎもあれば、地獄もある」。
ざっとこんな具合。鉈で削ぎ落としたような文体が素敵だ。サブタイトルにある老荘思想については、「『荘子』の勉強」で説明されている。老荘の思想は「虚」とか「無」という言葉に象徴されるが、「虚」も「無」も「穴」を意味する。
「荘子は、わが身を忘れて生きることが、最高の境地だとするのは、そういう時、なまじの分別知、世間知が働いていないからである。わが身を忘れるとは、分別の溶解、分別の無化、穴そのものになってしまうことである。積極的にむなしく生きるのが、荘子である」
「積極的にむなしく生きる」とは、荘子を語りながら草森が自身を語っている趣がある。穴とはその生き方を目に見える形にしたものだろう。そんな場所から、草森ひとり百科全書派の穴探しが始まる。
カッパドキアの洞窟住居にキリスト教修道士のユートピアを探る「谷は隠者で超満員」。独房の地下に穴を掘って脱獄を繰り返した「日本の脱獄王」白鳥由栄を追った「破牢の穴、自由の穴」。「春本三題」ではアナイス・ニン、ヘンリー・ミラー、永井荷風(伝)のポルノグラフィーを読みくらべて、女性の人体を巡る三者の「穴感覚」を比較している。
かと思うと「落語覗き三題」は、落語に出てくる障子の穴や壁の穴を使った覗きの噺を取り上げ、「とかく好奇心は、『穴』の属性をもつので、かならずといってよいほど自ら掘った『落し穴』にはまるものなのだ」とオチをつけてみせる。
末尾におかれた「穴さがし読書紀行」は、取り上げる本のリストが、いかにも草森らしい。
まず女性SF作家、ヴォンダ・マッキンタイアの『脱出を待つ者』は地下都市から宇宙へ脱出を試みる少女の物語。続いて地下都市から洞窟への連想で、蒲松歳『聊斎志異』の一編が紹介される。洞窟から穴に話がいってイタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』が俎上にのせられ、そこから近藤唯之のノンフィクション『背番号 の消えた人生』に進んで、現役引退後、水道工事をなりわいに穴を掘っている元プロ野球選手の話になる。
とりわけ、「心の穴」に落ち込んだ主人公の脱出譚である石川淳の『天門』(天門は女陰の比喩)から、SMが繰り広げられる土蔵を『蛇の穴』と呼ぶ団鬼六の小説に飛び、「蛇の穴」に手を突っ込んで噛まれる少年を主人公とした大江健三郎『河馬に噛まれる』に転ずるあたり、その手つきの鮮やかなこと!
「穴」をキーワードに普段並べられることのない小説がつながり、読書ガイドの体裁を取りながら、それ自体「穴」をめぐる面白いエッセーになっている。草森紳一の真骨頂だね。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





