「フクシマ」論【開沼 博】
「フクシマ」論
| 書籍名 | 「フクシマ」論 |
|---|---|
| 著者名 | 開沼 博 |
| 出版社 | 青土社(416p) |
| 発刊日 | 2011.06.15 |
| 希望小売価格 | 2,310円 |
| 書評日 | 2011.08.07 |
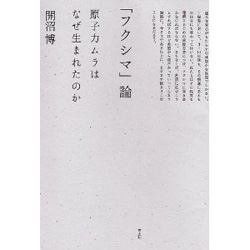
人に運不運があるように、本にも幸運な本と不運な本とがある。どんなに優れた内容の本でも、そのとき読者の関心がそこになければ省みられず、毎日200冊以上刊行される大量の出版物の海に埋もれてしまう。その意味では、福島第一原発の事故というこれ以上ない不幸な出来事に時期を合わせるように刊行された「『フクシマ』論」は、極めて幸運な本と言えるかもしれない。
これは東京大学大学院に在籍して社会学を専攻する著者の修士論文で、今年初めには書き上げられていた。そこへ「3.11」の事態が起き、「あとがき」から察するに指導教官の吉見俊哉か、推薦文を書いている姜尚中、上野千鶴子らの推挙で出版されることになったらしい。刊行に際しては、既に書き上げられていた本文の前後に「3.11」をふまえた「まえがき」と「補章」がつけ加えられている。
この本は「原子力ムラはなぜ生まれたのか」とサブタイトルがついていることから分かるように、二つの「原子力ムラ」について考察を加えたものだ。ふたつの「原子力ムラ」のひとつは、すっかり知れ渡った電力業界・学者・行政・政治家・マスコミが一体となって原発を推進してきた「ムラ」。もうひとつは、原発を受け入れ、交付金や雇用の拡大、臨時労働者の流入によって潤ってきた、文字通り地元の「ムラ」。開沼は、この中央と地方ふたつの「ムラ」の生成の歴史と構造を、主に地元の「ムラ」の側から考察している。ちなみに著者は「ムラ」にほど近い福島県いわき市の出身。
開沼がここで言っていることは、一言でいえば、地元の「ムラ」は、貧しさから脱却するために自ら欲望して原発を受け入れ、そのことによって中央の「ムラ」に自発的に服従することになった、というものだ。結論だけを取り上げれば、とりたてて新しい視点というわけではない。でも、そのことを学術論文としてデータを基に客観的に論じながら、文章の背後には地元出身者の愛、あるいは悲しみが流れていることが感じられる。
もちろん若い研究者の論文だから、社会学分野での研究史や論点の変遷を踏まえていて、その部分は学会という「ムラ」に属していない者には面白くもないけれど、なぜ福島県に多くの原発が立地するようになったのか、原発を誘致する過程で中央と地方との関係がどう軋み、どう変わったのか、そのいきさつをよく知らなかった僕にはとても興味深かった。
いま「原子力ムラ」がある福島県双葉郡は、かつて「東北のチベット」あるいは「福島のチベット」と呼ばれた県内で最も貧しい地域だった。この捨て置かれた(それゆえ自給自足だった)貧しい農漁村が、政治的にも経済的にも国家に組み込まれるきっかけになったのは戦争だった。1938年、軍部は現在の福島第一原発の土地の一部を強制買収して熊谷飛行隊の分校を開設し、陸軍の練習飛行場とした。「赤トンボ(練習機)が60機、兵隊が200人ほど」いたという。
戦後、この土地は放置され、荒地となっていた。それを買ったのは堤康次郎の国土計画で、堤はこの土地で大規模な塩田を営んだ。敗戦後、瀬戸内の塩田は荒廃して食塩が不足していたから、双葉町にはほかにも多くの製塩所が作られ、ヤミ米、ヤミ野菜などとともに首都圏に送られた。住民は製塩所に職を得たり、パイプラインなどの設備建設に従事することで収入を得た。しかしこの製塩事業も、技術改良によって海水から直接に塩が取れるようになったことで廃れ、土地は再び荒地に戻る。
ところで戦後日本復興の鍵のひとつは、増大する生産力に対応する電源の開発だった。もともと福島県は、大正期に猪苗代水力発電所を開発して京浜工業地帯に送電していた「全国屈指の電力県」だった歴史を持つ。県は、1950年代に新潟県に競り勝って只見川電源開発を実現する。一方、都市が高度成長を実現すればするほどに農業は衰退し、「ムラ」では出稼ぎと若者の流出、過疎化と高齢化が進んでいた。
そんななかで原子力基本法が制定され、2年後の1957年、福島県選出の参院議員・木村守江(後に県知事となり「原発知事」と呼ばれる)は、まだ他に手を上げる自治体がないなかで、「後進県からの脱出をめざして」いちはやく原発誘致に動き出す。地元にも根回しし、双葉・大熊町議会は誘致の意思を示した。「ムラも欲望していた」のだ。実現への最大の課題だった用地については、木村は荒地になっていた元塩田に目をつけ、堤康次郎に通じてメドをつけていた。
そのような経緯をたどって福島に原発が建設され、「原子力ムラ」が成立していく。もっとも東京電力の第一、第二原発とは別に東北電力が浪江町・小高町(現・南相馬市)に原発を計画していたが、これは実現せず、今も現地に「浪江・小高原子力準備本部」が残っているのを、この本で初めて知った。
本書には1962年から2002年までの「福島県内の一人当たり分配所得の地域格差」の表が掲載されている。1962年には双葉町・大熊町・浪江町・富岡町などは県内最低水準にあった。しかし70年代になると原発を誘致した双葉町・大熊町・富岡町は県内最高レベルに踊り出、一方、周辺の葛尾村、川内村などは相変わらず最低レベルに留まっている。ところが90年代後半になると、最高レベルになった自治体も原発からの税収の低下、交付金で建設したハコ物の維持費などで財政が苦しくなり、新しい施設の誘致や建て替えを要請することになった。「ムラ」にとって原発は「一度はまると抜け出せない麻薬のようなもの」となっていたのだ。
「浪江・小高原発」が実現しなかったように、1960年代の反公害運動や環境意識の高まりのなかで、地元でも反対運動はあった。しかし、賛成か反対かという対立はあっても、「ムラの利害」という見地から見れば反対派も「無視しうる誤差」であり、「反対派をからめとりながら安定した秩序が構成」された。反対派が存在することで、国や電力会社は「地元懐柔の必要性」を強く感じ、つまりはより多額のカネが落ちることになるからだ。
こうして1970年代以降、反対派は新しい原発建設を断念させることで一定の「成果」をあげ、新規立地をあきらめた推進派は既存の原発を活用することに新たな道を求めるという「両者にとってある面では満足の行く結果」によってムラは「安定」していった。
「推進派のみならず、反対派も、官産学政や反対派、マスメディアも含めて、それぞれの意図はそれぞれにあろうとも、意図せざる結果として原子力が安定的に社会と共生していく条件が出来た」
その構図は「3.11」まで続き、その日を境に「安定」に亀裂が入った。誰もが内心恐れていたように、原発がいったん重大な事故を起こせば、地方と中央の「ムラ」はもちろん、国の姿まで100年単位で変えてしまうような深刻な被害をもたらすことを目の当たりにして、推進・反対いずれの立場をも飲み込んで続いてきた「安定」がいかに虚構の上に成り立っていたかを、苦い思いとともに自覚せざるをえなかった。
「3.11」後に加えられた部分で、開沼はこう書いている。
「国道6号線をただひたすら北上すればよい。『国土の均衡ある発展』を目指した挙句に誕生した田畑と荒地にパチンコ屋と消費者金融のATMが並ぶ道。住居と子どもの養育費以外に費やしうる可処分所得をつぎ込んでデコレーションされた車。郊外巨大『駐車場』量販店と引き換えのシャッター街のなかには具体例をあげるのも憚られるあまりにどうしようもないネーミングセンスで名づけられた再開発ビル。その中で淡々と営まれる日常。例えば『ヤンキー文化』『地域○○』といったあらゆる中央の中央による中央のための意味づけなど空虚にひびく、否、ひびきすらしない圧倒的な無意味さ。成長を支えてきた『植民地』の風景は『善意』ある『中央』の人間にとってあまりにも豊穣であるはずだ」
「福島において、3.11以降も、その根底にあるものは何も変わってはいない。私たちはその現実を理解するための前提を身につけ、フクシマに向き合わなければならない。さもなくば、希望に近づこうとすればするほど希望から遠ざかっていってしまう隘路に、今そうである以上に、ますます嵌りこむことになるだろう」
ここまで書いてきたとき、「浪江・小高原発」計画の地元・南相馬市が原発交付金を辞退することを決めた、というニュースを知った。
開沼が現地で見た「3.11以前の福島は思いのほか『幸福』に満ち、3.11以後も彼らはその日常を守ろうとしている」という「福島の『幸福』と『不変』」はその通りとしても、その一方で、南相馬市(桜井勝延市長)のように、戦後長らく中央に「服従」してきた自治体が、自らの意思で自分たちの将来を決めようとする姿勢、そのためには金銭的な「幸福」を捨てることもいとわない姿勢が鮮明になってきている。それは全国の原発立地地域で後戻りできない広がりを持ちつつある。これは開沼の言う「反対派を含めた安定」とは別のフェーズが生まれたということだろう。
僕自身は段階的な脱原発プログラムを支持するけれど、原発の将来についてどのような国民的合意をめざすべきなのか。まずは「国道6号線を北上」して(というのは比喩的な言い方だけど)フクシマや三陸海岸を見つめ、その声に耳を傾け、その上でいろんな考えを公の場で戦いあわせることが必要だと思う。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





