廃墟建築士【三崎亜記】
廃墟建築士
| 書籍名 | 廃墟建築士 |
|---|---|
| 著者名 | 三崎亜記 |
| 出版社 | 集英社(224p) |
| 発刊日 | 2009.01.26 |
| 希望小売価格 | 1,365円 |
| 書評日等 | - |
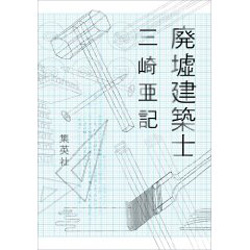
「となり町戦争」で2007年の小説すばる新人賞を受賞したこの作家の作品を読むのは初めてだ。このところ小説を読むことがめっきり少なくなっている。若い時はかなり小説を読んでいたのだが、読むべき小説が少なくなったと言うほど最近の文壇情況を知っている訳でもなし、気持ちの問題だと自己分析。そんなことを考えている間に一冊読み終えることも可能と早々に気持ちを切り替えて、手にしたのが本書。
長めの短編小説(妙な言い方だが、「短かめの長編小説」や「中編小説」という言い方よりは判っていただけると思う)が4編 収録されている。その全てが建物をモチーフとした小説で、ありえないと思えるような非日常的事柄を私達の日常風景に登場させ、あたかもありえるかもしれないと思わせる構成や小道具がちりばめられている。そうした仕掛けがフィクションとしての楽しいところである。個人的には「ありそうな話だが事実でない小説」よりも本書のような「ありえない話だが事実そうに思える小説」のほうに興味は惹かれる。
「七階闘争」は、マンションやアパートの「七階」で犯罪や自殺といった事件が多く発生しているということから話は始まる。その市の議会では「七階」の存在自体が問題の根源といった議論が行われ、市長は「その街にある全ての七階を撤去する」ことを約束する。主人公はマンションの七階の住人でこの騒動に巻き込まれていくのだが、何故か「七階」の歴史的正統性を唱えて執着する人達や、「七階」を撲滅させようとする勢力が入り乱れて反対運動や排除活動が繰り広げられる。
その反対運動の中に息子を自殺でなくした男がいる。息子は遺書を残さなかったため、何故死を選んだのかも判らない。しかし、周りの人たちは自殺したのは七階に住んでいたのが原因と決め付ける。親としても七階に住んでいたことが息子の死の原因だったろうかと思い悩みつつ、「七階闘争」に参加したものの「七階を守る側の論理」もピンと来ない。主人公も同様に至極普通の人なので双方の議論に戸惑っている。かたや、各所で「七階」の撤去は進められ、今まで十階建てだった建物は七階が物理的に消滅したため九階建となる。こうした、強制排除の結果、転居に反対して七階に住み続けていた住民は七階とともに消滅していく。
このように七階がないという世界は異様に思えるものの、よく考えると身近にそうした状況は存在しているのだ。海外に旅行してアメリカなどでホテルの十三階がなく、エレベータの表示ボタンも十三階はないことは多い。宗教的とか文化的な忌み数は世界でいろいろあるのだろう。そうして考えると突然「七」を排除したいという信念や主義や信仰がどこかで生まれてきてもおかしくないという思いがふつふつと沸いてくる。人間は論理的な順番さえも忌み数によって変えてきた。 病室番号で四号室がない病院もある。こうした人間の弱さを上手く表現した掌編である。
「廃墟建築士」は、廃墟の存在こそ国の文化のバロメーターという話。日本は廃墟が少なく、だから文明度が低いと世界各国から指弾された結果、建物を最初から廃墟として建設して行こうということになる。そのため廃墟建築士という職業が確立されている。こうした中、新たに開発された大廃墟が華やかにオープンする。これを設計した廃墟建築士の師匠である老廃墟建築士はこの大廃墟に批判的な眼差しを向ける。廃墟はもっと職人的な手仕事の結果生まれるべきで、弟子の作っ た華々しい廃墟は邪道であると考えている。彼にとって理想的な廃墟とは200年以上建築をし続けている「連鎖廃墟」と呼ばれている建物で、最初に建設された部分はもう崩壊しつつあるという代物。「廃墟のための廃墟」が理想であり、「廃墟とは、人の不完全さを許容し、欠落を充たしてくれる、精神的な面で都市機能を補完する建築物です。都市の成熟とともに、人の心が無意識かつ必然的に求めることになった『魂の安らぎ』の空間です」と老廃墟建築士は語っている。
作者の三崎は、「バブル期に居住や利用の観点を無視したような建物が多く作られたことに触発されてこの小説を書いた」と言っている。この小説を読んでみて、バルセロナのサクラダ・ファミリアと紙一重だと思った。サグラダ・ファミリアは1882年から延々と建設され続け、最近の推定では完成は2256年という説がまことしやかにささやかれているぐらいだから、まだ240年ぐらいかかることになる。サグラダ・ファミリアでは新築工事と同時に補修工事が行われていると聞いている。これは建築している間に廃墟になっていくというのもありえない話ではない。「完成前」のサグラダ・ファミリアが「世界遺産」に登録されてしまうというのも奇怪な感じすらするのは私だけだろうか。
「図書館」という話は、図書館に収蔵されている本が夜になると飛び回る習性を利用して夜間開館をするというテーマ。図書館は夜になると野生を取り戻し、それに刺激されて本が飛び回るという設定はなかなか面白い。これは、動物園を夜間に開放して昼間とは違う動物達の習性を見てもらおうというイベントと同様の発想である。ただし、本はしっかりと調教しなければ飛行の管理もできず収拾がつかなくなるため、プロである「図書館調教士」が本達を調教して夜間開館を実現していく。基本的に本は飛び回る能力が有るのだが、飛び方は本によって特性があり、例えば個人蔵書が寄贈されたものは、前の所有者の癖がついていて調教し難いとか、工業や建築を含む体系の本は航空力学に適った理想的な飛行を追求するとか、美術や音楽のジャンルの本は飛び方が優雅で遊び心を持っているといった設定である。
本の本来持っている独特な存在感は、例えば、一度読んだ本をなかなか捨てられないという感覚などにも現れているのだろう。そうした本の持つ特別な意味に向き合うと、もしかしたらこの本は飛ぶかもしれないと思ったりする。
この話を読みながら同種の感覚、日常と非日常の交錯感を覚えたことがあったと感じた。それは、童話だったと思い至る。童話の凄さは時限も越え、理論も越えてストーリーが展開するところにあるが、子供たちは否定する知識を持っていないからこそ、自由な空想力を発揮して楽しむことができる。本書は私の好きな、宮沢賢治の「なめとこ山の熊」のような日常と非日常の強烈な集合体ではないにしても、大人向けの理屈で多少味付けした童話だと思った。「図書館」をもっと短くコンパクトにして、子供にわかる言葉遣いに変えてみたらなかなか凄い童話になりそうだ。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





