ランドマーク【吉田修一】
ランドマーク
| 書籍名 | ランドマーク |
|---|---|
| 著者名 | 吉田修一 |
| 出版社 | 講談社(208p) |
| 発刊日 | 2004.7.15 |
| 希望小売価格 | 1400円+税 |
| 書評日等 | - |
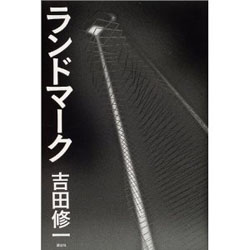
この本にインスピレーションを与えたと思われる3つの建築(計画)がある。
ひとつは本文のなかでも引用されている、ロンドンのスイスRE社ビル。「ガーキン(ピクルスのきゅうり)」と通称されるとおりの形で、全面ガラス張りのユニークな高層ビルだ。上海香港銀行やセンチュリー・タワー(お茶の水)で名高い建築家、ノーマン・フォスターの設計になる。
いまひとつは、同じノーマン・フォスターが提案したニューヨークのワールド・トレード・センター再建案。六角形あるいは三角形のフロアが階ごとにズレて重なりながらツイン・タワーをなすプランで、外側の鉄骨をはずして考えると、その内側には三角(六角)の筒をねじったような建築物が現れる。ただしこの案は採用されなかった。
最後のひとつは、本書の舞台となっている「さいたま新都心」に建設しようと誘致運動が始まった「さいたまタワー」。地上デジタル放送のための電波塔で600メートル級、完成すれば「世界一のタワー」になるという。
ロンドンの「ガーキン」は、テムズ川沿岸再開発の目玉として注目を集め、この地区の新しいランドマークとなっている。ついでにいうと、やはりフォスターの設計になるロンドン市庁舎には、この小説の重要なキーワードであるスパイラルな空間が取り入れられている。
フォスターのワールド・トレード・センターの設計プランやロンドン市庁舎が、本書の主役である高層ビルO-miya スパイラルの原イメージをなしていることは想像に難くない。
でも、作者がこれらの建築物を参照しているだろうことに関して、それ以上に重要なのはニューヨークの旧ワールド・トレード・センターがテロによって崩壊したという事実だ。作者にとっても、またこの小説を読む読者にとっても、その背後には「崩れ落ちる高層ビル」というデジャ・ヴュが抜きがたく横たわっているように思える。
「さいたまタワー」の構想を聞いたときには、思わず笑ってしまった。「世界一」?これって東京タワーに喜んだ1950年代、高度成長以前の感覚そのままではないか(ちなみに評者はさいたま市民である。恥ずかしい)。
しかし吉田修一は、そのような感覚をこそ小説のなかに取り込もうとした。あるいは、O-miyaスパイラルという先鋭的な建築物に対比される形でそれを必要とした。都会的な洗練の対極にあるそのような感覚が求められた結果として、主人公のひとりである鉄筋工の恋人、ラーメン屋の女店員とその母親が造形されている。
この小説には2人の主要人物が登場する。一人はO-miyaスパイラルの設計を担当している建築家。妻のいる都内の自宅にはほとんど帰らず、現場近くのホテルに泊まり込んでいるが、設計事務所でバイトをしている娘とデキている。
いまひとりはO-miya スパイラルの現場で働く鉄筋工。作業員の宿舎である寮に暮らしているが、週末には新宿のライブハウスに通い、ラーメン屋で働く恋人がいる。
2人は小説の冒頭近く、互いに知った顔だと考えながらちらりと視線を交わす。そのまま挨拶もせずに別れてしまうのだが、以後、小説の終わりまで交わることはない。交わることのないまま、2人の男の物語が語られてゆく。
小説の前半に流れているのは、高層ビルの建築現場で働く男たちの、地上から離れているという浮遊感である。
地上45メートルの現場。鉄筋工は「目の前にぽかんと開いた壁の穴の先、雲一つない真っ青な冬空」を見て、「天窓で区切られた空を見上げているような錯覚」に陥る。高い場所から水平に空を見ている自分の視線を、垂直の視線と錯覚している。その垂直の視線は、鉄筋工が寮の二段ベッドで感ずる、「手を伸ばせば届きそうな場所に、ヤニで汚れた蛍光灯があって、目を閉じると自分のからだが天井近くで浮いているように思える」という浮遊感に満ちた描写と重なり合っている。
建築家は建築家で、床の空カンを拾いながらテーブルの立体模型を見て、自身の揺れ動く視線を感じている。「ゆっくりとテーブルの横から立ち上がると、ちょうど地中から地上へ、そして地上から上空へ、視点が移動していくように立体模型を眺められる」。
建築家も鉄筋工も、地上から切り離されているという不安に支配されている。その不安を増幅するのが「スパイラル」という特殊な建築物の構造だ。重箱をずらしながら重ねてゆくようなO-miyaスパイラルは、不安定な「二本のバネのあいだに床を挟みこんだような構造」であるため建物がねじれ、そのねじれを建物内部のチューブで支えることで安定を保っている。もしチューブの設計や施行にミスがあれば、建物は「自分の重みによるねじれに耐えられなく」なって崩壊するだろう。
浮遊の感覚に襲われる鉄筋工を地上に繋ぎとめているのは、恋人とその母親の存在。ラーメン店で働く恋人は「大宮の悪そうなやつとは、みんな知り合い」というジモチーだし、母親は鉄筋工が訪ねても畳に寝転がったまま応対し、「あんたみたいな男には娘みたいなのがちょうどいいのよ」とうそぶく女。また、鉄筋工の同僚がみな秋田出身で、彼らの会話がすべて東北弁で記されていることにも注意すべきだろう。
地元の母娘の設定にしても、東北弁を話す同僚の設定にしても、作者は東京の都心から20キロ圏であり、東北地方へのターミナル駅でもある大宮という土地の地政に敏感であることが分かる。文学でも写真でも、都市近郊というのはこのところ焦点になっている場所だけれど、中央線や小田急線沿線の郊外、あるいは横浜方面の郊外でなく、東北に向けて開かれた町である北の郊外に舞台を設定したことに作者の計算の確かさを感ずる。
物語の半ばまでを支配していた浮遊感と不安は、終わり近くなって、建物のねじれを支えるチューブの施工に問題があるかもしれないことが分かるあたりから、一気に崩壊へとなだれこんでゆく。スパイラル建築の脆弱な構造の説明が、二度繰り返される。崩れるかもしれない高層ビルの描写を、読者は客観的な記述とは取らず、明示されてはいないが不安に侵された建築家の白昼夢として感受するだろう。そう受け取る読者の背後に、9.11のデジャ・ヴュがあることは言うまでもない。
ところで、鉄筋工は小説の冒頭で、アメリカから通信販売で求めた男の貞操帯を自らの身に装着する。彼は「何やってんのよ?」と聞く恋人に「強姦防止」と答え、しばらく後になって、「ぜんぜんイライラすることがねぇから、わざとイライラするようなことしてんじゃねぇか」と説明し、さらに「現場でも、寮でも、街を歩いてても、誰も知らねぇんだよ。こんなもんつけてるやつが、そばにいたり、ふらふら街を歩いたりしてんだぞ。……気味悪くねぇか?」とも言っている。
それはスパイラル構造の高層ビルとともに、この小説を支配するもうひとつの「もの」なのだが、その「もの」が指し示す意味合いが、評者にはいまひとつ納得できないまま残った。
男は貞操帯のカギを大量に複製して、工事現場でフロアごとにコンクリートのなかに埋め込んでゆく。かと思うと、しばらくぶりに恋人と会うと我慢できなくなってカギをはずし、セックスしてしまう。カギのかかった貞操帯は、なにごとかのメタファーのようでもあり、そのつもりで読んでいくと肩すかしを食って、物語を飾るための小道具のひとつにすぎないような気もしてくる。
小さな不満を述べたけれども、現実と情報を巧みに統御しながら、交わらない物語とでもいうべき今日的なフィクションをつくりあげた著者の力に脱帽する。クールでバッドな小説を楽しんだ。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





