流【東山彰良】
流
| 書籍名 | 流 |
|---|---|
| 著者名 | 東山彰良 |
| 出版社 | 講談社(408p) |
| 発刊日 | 2015.05.12 |
| 希望小売価格 | 1,728円 |
| 書評日 | 2015.11.19 |
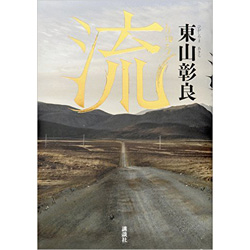
今年の直木賞を受賞した『流(りゅう)』はまぎれもなく日本語で書かれた小説だけど、どこか日本の小説じゃないみたいだな。
考えてみれば当たり前なんだけど、そう感じた理由はふたつ。ひとつは、言うまでもなく東山彰良が日本人ではないこと。受賞の報道で知った人も多いだろうけど(僕自身もそうだった)、東山彰良はペンネーム。著者の王震緒は台北生まれ、今も中華民国の国籍を持っている。「東山」は祖父の出身が中国の山東省だったことから、「彰良」は母親が台湾の彰化出身であることから来ているという。
5歳で来日し、9歳のとき台北の小学校に入学。以来、日本に住みながら台湾、中国と行き来している。台湾、中国、日本、「どこにいても“お客さん”なんです」(asahi.com、2009年2月24日)という東山の言葉からは、青年期、自らのアイデンティティについていろんな悩みがあったろうことを想像させる。
それは結果的に文化的な多様性を身につけたということでもある。だから台湾人少年を主人公に台湾、中国、日本を舞台とする『流』は、文化の混淆が豊穣をもたらすクレオール文学という一面ももっている。もっとも、東山の文章はネイティブが書く日本語以上にスピード感があり、かつ端正でもある。
もうひとつ「日本の小説じゃないみたい」理由には、ちょっと補足して「今どきの日本の小説じゃないみたいだな」と。そもそも舞台と主人公の設定からして日本と日本人ではないからそう感ずるのも当然だけど、そればかりでなく登場人物が生きている世界とその価値観が今どきの日本の小説とまったく異質だと感じられる。その濃密な人間関係と、国や法律と無関係に生きる彼らの道徳や倫理は、もしこれが現在の日本人を主人公にした小説なら、まったくリアリティを感じられないのではないか。
主人公はじめ、登場人物はみな家族と仲間のために生きている。彼らのためなら、血を流し命を投げ出すことをためらわない。そして喧嘩と恋。今どきの日本のクールな小説にはない懐かしさを感じてしまった。それがめっぽう面白い。
1975年、台北。蒋介石総統の死で喪に服するこの町で、17歳の「わたし」は高校を退学になる。同じころ、布屋を営んでいた祖父が後ろ手に縛られ浴槽に沈められて殺される事件が起こった。遺恨を想像させる死に方。祖父は蒋介石とともに中国山東省からやってきた「外省人」で、大陸では国民党の匪賊として日本軍に協力した村人や共産主義者を殺した男だった。
誰が祖父を殺したのか。小説はミステリーの形を取って、最後に犯人は意外な人物だったことがわかるけれど、作者の眼は謎解きそのものには向いていない。
船乗りで黒道(ヤクザ)の友達もいる宇文叔父さん。幼馴染みの看護師で、「わたし」の歳上の恋人になる毛毛(マオマオ)。やはり幼馴染みの親友で、黒道の杯を受けた感化院帰りの小戦(シャオジャン)。祖父の大陸時代の命をかけた仲間である李爺爺や郭爺爺。おじいちゃん子の「わたし」が祖父の秘密に触れ、毛毛とつきあい、小戦と2人で喧嘩を繰り返して成長してゆく「わたし」の青春物語になっている。
今どきの日本の小説と違うのは、大家族で、しかも家族と家族の間がなんと密接なのかと感じさせるところ。じいちゃんの殺された同志の子供でじいちゃんの息子として育てられた宇文叔父は、「わたし」と小戦の喧嘩を買ってでてヤクザの事務所に殴り込み、刑務所送りになってしまう。毛毛と別れて腑抜けになっている「わたし」とおばあちゃんはこんな会話を交わす。
「『女にふられたってご飯は食べなきゃならないんだからね』
祖母は……おでこを指でつついた。
『ふられてよかったわよ。あんな家と親戚になるくらいなら、あたしのほうがアメリカに行っちゃうわよ』
『ほっといてくれよ!』祖母に暴言を吐きつつ、わたしは茶碗の白米をかきこむ。『おれにかまってないで李奶奶(リばあさん)と麻雀でもやってくれば!』
『そういうところ、あんたのおじいちゃんにそっくり。あの人が最初の奥さんを捨ててあたしを選んだときもずーっとそうやってねちねち後悔してたものよ』」
この小説、青春物語なのにじいちゃん、ばあちゃん、祖父の同志の李爺爺や郭爺爺といった年寄りが、台湾・中国と日本の家族の在り方の差を反映しているんだろうけれど印象深い。そういえばホウ・シャオシェン監督の傑作『恋恋風塵』でも、孫の幼い恋を黙って見つめるおじいちゃんの存在が際立っていた。この映画だけでなく、『童年往時』や『風櫃の少年』といった喧嘩好きの少年たちを主人公にしたホウ監督の半自伝的な青春映画は、家族にしろ町の風景にしろ恋にしろ『流』の世界とすごく近い。
ひどく懐かしくなってしまったのは、台北のちょっと怪しげな繁華街である萬華の描写。僕が知っている萬華はこの小説の設定より10年ほど後のことだけど、台北の町全体が小奇麗になりつつあった当時でもこんな雰囲気を残していた。
「売春宿や蛇を食べさせる店が軒を連ね、男女の悲しみや蛇の血のせいで街全体に饐えたようなにおいが漂い、刺青を入れ、檳榔の噛み汁で歯を真っ赤に染めた極道たちが暮らしていた。……
雷威(注・主人公の喧嘩相手)は檳榔をぐちゃぐちゃやりながら、屋台で豚血糕(ジュシュエガオ)を買おうとしていた。豚血糕とは餅米を豚の血で固めて串刺しにしたおやつで、なにを隠そう、わたしの大好物である」
21世紀の日本(今の台北もそうかもしれないが)からは失われてしまった人間たちと町の風景。その埃っぽく血と汗が染みついた匂いがこの小説にはむんむんしている。
そんな舞台のなかで、主人公たちは家族や同志のために命を危険にさらすことを厭わない。抗日戦争と国共内戦を背景に、20年の時を黙って過ごし大陸と台湾との間で命のやりとりをする。その時間感覚は、これこそ大陸的という感じがするけれど、その時を超えた因果を納得させてしまうのは東山が中国人として家族や仲間のありかたを熟知しているからだろう。その底に流れているのは、過酷な歴史を生きたじいちゃんの世代の悲しみであり、それを手渡された主人公の悲しみにほかならない。
「わたし」と小戦の悪友ぶり。「わたし」と毛毛の姉弟のような恋の行方。宇文叔父の男気。じいちゃんと仲間たちの肖像。物語を読む喜びをたっぷり味わえる一作だった。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





