堀田善衛 上海日記【紅野謙介】
堀田善衛 上海日記
| 書籍名 | 堀田善衛 上海日記 |
|---|---|
| 著者名 | 紅野謙介 |
| 出版社 | 集英社(440p) |
| 発刊日 | 2008.11.05 |
| 希望小売価格 | 2,415円 |
| 書評日等 | - |
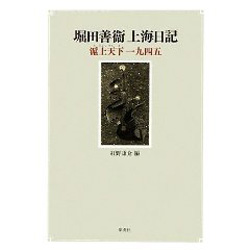
横浜山手「港の見える丘公園」の緑に埋もれるように神奈川近代文学館はあるが、そこで本年(2008年)10月から堀田善衛展が開催された。目玉のひとつが本書のベースとなった未発表の日記である。第二次大戦の終結前後の19ヶ月間、堀田は上海に滞在し、日本にとっての敗戦、中国にとっての解放という異常事態の真っ只中で日記を書き綴っていた。堀田は戦後上海や中国に係わる作品を数多く発表しているが、特に、1959年に出版された「上海にて」に描かれている多くのプロットはこの日記の中にあることが分かる。日記と推敲された文章の違いは大きいが、日々の断片的な思いである日記からは推敲された文章とは違った意味のパワーを感じるものである。
27歳の早熟した作家・文学者の姿とともに、ヨーロッパ特にフランスに傾斜している若者の姿が見てとれる。人生観を左右する時期・年齢における日記なので 日常の些細な事柄を含めて、特有の細かさがあり、後に結婚することになるN夫人(中山れい)との恋愛感情も随所に記述されている。基本的には「素」の堀田が良く出ているといってよいだろう。
日記の冒頭部分にある、8月15日の終戦から数日間の記述は二ヶ月後に書かれているようで、日本の敗戦という混乱の一瞬を切り取ったというよりも、一呼吸 おいた文章であることを知っておくことは意味がある。それは、この日記が第三者に読まれることを想定していたのかも知れないし、混乱期において、とても日記を付けている時間もなく過ごし、後日、メモとして書き留めたものかも知れない。
この短い期間は租界を含めて日本の支配期、日本の敗戦からの混乱期、国民政府の支配期、共産党支配の予兆期といった、目まぐるしく変化する時期であった。1945年8月11日の記述には、第二次大戦終結を目前にして、日本の敗 戦がかなり公然と語られていたことが記されている。
「・・・電車に乗ると、同盟(通信)の赤間さんが僕の隣に坐った。『何だかとうとう来たようですね。』と赤間氏が云う。僕はよく納得出来ぬままに、ええ?と聞き返した。氏は『未だ知りませんか?』と云った。『何ですか?』『日本が降伏したと云ふんですよ』・・・・・」
国策通信社であった同盟の社員をはじめとして、海外情報に接することが多かった堀田の立場(外務省管轄下の国際文化振興会調査部、後に海軍軍令部臨時欧州 戦争軍事情報調査部で暗号解読に携わっている)からも正確な情報を日本からではなく、海外からの情報で把握出来ていたことは十分予想できる。そして敗戦を迎えるのだが、玉音放送を聴く状況の記載に疑問を持ちつつ、興味深く読んだ。
「・・・事務所のラジオのある部屋に行くと、姿勢正しく坐っている人、頭をたれて腰掛けている人など、三・四人がいて、ラジオは荘重に勅語を告げていた。これが、陛下御自らの御放送であるとはその時私は知らなかった。雑音が多くてよく分からない。ただ一句「臣子衷情朕コレヲ知ル」と仰せられたのだけはよく分かった。涙が出た。・・・」
「玉音放送」に対する素直且つナイーブな表現に驚いてしまう程である。というのも、彼は1971年に出版した「方丈記私記」の中で東京大空襲の時の天皇と 国民の姿を批判的に表現していたからである。骨子は次のようなものであった。「・・・1945年3月10日の東京大空襲の後、焼け野原となった被災地を昭 和天皇が視察した。その天皇に平伏して、結果責任を負うべき当の相手に対してひたすら詫びているひとびとの『優情』を目撃し、日本および日本人に理解不能な『重い疑問』を抱いた」
玉音放送の「臣子衷情朕コレヲ知ル」という天皇の言葉に「涙する」堀田と、視察する天皇に平伏する日本人に「重い疑問」を抱く堀田。この深いギャップに驚かされた。
日々の生活描写からも多くの発見がある。まず、堀田は戦後も驚く程多くの映画を見て歩いていることである。アメリカ映画、ソ連映画、ヨーロッパ映画となんでもござれの映画漬けである。それほど堀田は時間をもてあましたのかとも思うし、上海という都市の持つ文化的許容度の深さを感じるところである。また、昭和21年の正月の記述を読むと、上海における日本人達が日本国内に比べ豊かな生活をしていることが分かる。
「元旦の朝はお雑煮をすませてから、北井さんのところにゆき、コーヒーを一杯のみ、『ライフ』、『ヤング』などのアメリカ雑誌を見てから・・・二日は朝ほんのすこし迎へ酒をして、・・・新年会だか分からぬものにゆき、肉をやたらと食った。・・・」
この記述だけ読んでいるとまるで異次元の生活のようでもあり、戦中・戦後を問わず上海を舞台にしての利権や国家戦略という美名で資金が投入されていたという話が窺がわれるような話である。戦争中の上海には、文化工作・情報戦略のために多くの日本人が滞在していた。本書にもいろいろな分野の人間が登場している。
そのうちの一人が名取洋之助。1940年前後は上海を拠点として、南京・広東にネットワークを持って、外務省外郭の国際文化振興会や内閣情報部と深い関係があったといわれている。戦後は岩波写真文庫の編集に力を振るったのは良く知られている。また、戦後東和映画を立ち上げる川喜多長政・かしこ夫妻も中華電 影公司の責任者であった。武田泰淳を初めとして多くの作家・ジャーナリストも同様。こうしてみると多彩な人材が終結したのは満州だけでなく、上海もしかり。しかし、こうした日本人社会も次第に帰国者が増加していく中で敗戦から一年も経つと堀田も弱気になっていく心情が語られる。
1946年8月5日の記述、 「かうして飼ひ殺しのやうでもあり、全く自分勝手のやうでもあり、金は全く無くて、時間ばかりが矢鱈にある生活をしていると、自分の人生について考える時間が多い・・・」
こうした、上海での19ヶ月を「上海にて」ではつぎのように書いている。 「・・・1945年の3月24日から1946年12月28日までの上海での生活は、私の、特に戦後の生き方そのものに決定的なものをもたらしてしまった。もとより文学の仕事を一生の仕事にとは以前から思い定めていた。けれども、そこへ、中国と日本というまったく思いもかけなかったものが入ってきた。私は戸惑った。いまだに戸惑いから脱しきれていない。・・・・」
堀田本人が語っているように、明らかに人生を変えたという時期であればこそ、堀田善衛という文学者を理解するひとつの重要な切り口として本書は読まれると思う。そして、日本と中国の関係について危機感を抱いていた堀田であるが、新しいグローバリゼーションの中で両国が苦悩・努力している現在の姿を彼はどう見るのか興味は尽きない。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





