われらが背きし者【ジョン・ル・カレ】
われらが背きし者
| 書籍名 | われらが背きし者 |
|---|---|
| 著者名 | ジョン・ル・カレ |
| 出版社 | 岩波書店(518p) |
| 発刊日 | 2011.11.07 |
| 希望小売価格 | 2,730円 |
| 書評日 | 2013.01.08 |
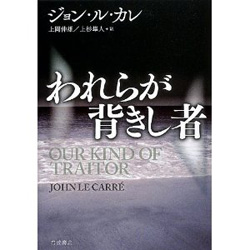
ジョン・ル・カレの愛読者だったのはもう40年近く前のことになる。最初に読んだのは世界的ベストセラーで映画にもなった『寒い国から帰ってきたスパイ』で、それまでスパイ小説といえばイアン・フレミングの007しか知らなかった身には、東西冷戦下、なんともリアルでぞくぞくするような物語だった。
そこから始まって、ソ連のスパイが現実に英国諜報部に潜り込んでいたキム・フィルビー事件を素材にした『ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ』、つづいて同じ主人公スマイリーが活躍する『スクールボーイ閣下』『スマイリーと仲間たち』と“スマイリー3部作”に熱中した。細かいストーリーは覚えていないけれど、どんより曇った空の下、さえない中年男のスマイリーが地道な調査と心理的駆け引きでスパイを炙りだしてゆく、全編を貫く暗鬱な雰囲気は今も鮮烈に思い出すことができる。
同時に、ル・カレのスパイ小説の先駆けともいうべきグレアム・グリーンの『密使』やジョセフ・コンラッド『闇の奥』(映画『地獄の黙示録』の原作)に遡って、リアリズムを基調とするイギリス小説の面白さを知ったのもこの頃だった。
その後、ル・カレとは縁がなくなったけれど、久しぶりに新作を読んでみようという気になったのは、去年、『ティンカー・テイラー・ソルジャー・スパイ』を映画化した『裏切りのサーカス(邦題)』を見たせいかもしれない。ゲイリー・オールドマンがスマイリーに扮した映画版は、渋いながらも現代的な映像感覚で、小説を支配する冷たく灰色の空気をよく再現していた。
さて、『われらが背きし者』である。舞台はカリブ海に浮かぶリゾート、アンティグア島。オックスフォード大学の英文学教師・ペリーと、恋人で弁護士のゲイルがバカンスを楽しんでいると、ディマと呼ばれるロシアの富豪がペリーにテニスの試合を挑んで近づいてくる。
ディマは禿げ頭で屈強な身体、腕には胸をはだけた聖母マリアの刺青を彫り、ダイヤを散りばめた金のロレックスをはめている男。ものものしいボディガードを従え、精神に異常を来たしたらしい妻と、双子の息子、誰の子か分からない2人の幼い姉妹と、透き通るような肌の十代の美少女を伴ってい る。やがてディマはロシア・マフィアの幹部で、組織のマネー・ロンダリングを担当していることが分かる。しかしボスに睨まれ、命の危険を感じて、情 報提供と引き替えに自身と家族のイギリス亡命を希望している、とペリーに持ちかける。
そこから舞台は一転してロンドン。とある館の地下室。ディマの伝言をイギリス諜報部に伝えたペリーとゲイルが、諜報部の尋問を受けている。質問するのは上級職員のヘクターと部下のルーク。物語はこの4人を中心に、ヘクターらが質問しペリーらが答える会話体のスタイルで、時間と場所を行き来しながら進行する。
ヘクターは考える。ディマという男とその情報は信用できるのか。引き替えに永住権を与えるほどの重要な情報を持っているのか。ディマはこうほのめかしていた。ロシア・マフィアはマネー・ロンダリングのためイギリスに銀行を設立しようとしている。
またイギリス諜報部出身の国会議員がロシア・マフィアと関係している、と。話を持ちかけたディマと、巻き込まれたペリー、ゲイル。質問するヘクター、ルークと、答えるペリー、ゲイル。それぞれの間で信頼と疑心暗鬼が揺れ動く。会話を通して繰り広げられる心理ドラマがこの本の最大の読みどころだ。なかでもディマ、ペリー、ヘクター、ルークの4人のキャラクターと、それぞれの関係が面白い。
エリート・インテリのペリーは、自らその地位を捨て貧しい地域の公立中学の教師になろうとしている。彼にはディマの依頼に応ずる義務などないけれ ど、ディマの強引だが率直なやり口と熱情に惹かれてゆく。ディマはかつて母のために殺人を犯し、収容所では囚人の元締めとしてのし上がり、出所してマフィアの幹部になった男だ。
「彼(ペリー)がひと目でも見たいと望んでいるのは一体誰なのか? 彼にとってのジェイ・ギャツビーであるディマか? 彼個人にとってのクルツ(注・『闇の奥』の怪物的登場人物。映画でマーロン・ブランドが演じた)と言えるディマか? 彼が愛してやまないジョセフ・コンラッドの作品に登場する、欠点の多いほかのヒーローか?」
ル・カレはフィッツジェラルドやコンラッドの小説の主人公を挙げながら、ディマがどのような人物なのかを語っている。またこの小説が、どのような系譜のなかにあるものなのかを語っている。
一方、諜報部のヘクターやルークは“スマイリーもの”同様、スーパーヒーローではなく、どこにでもいる悩み多き人間として造形されている。ヘクターはやり手だが組織を批判したことで上から睨まれ、主流からはずされている。息子は自動車事故で人を殺し服役中だ。ルークは女好きで、同じチームの女性やゲイルに欲望を感じている。浮気がばれ、上流階級出身の妻とはうまくいっていない。
ヘクターはペリーとゲイルに再びディマと接触させ、元諜報部の議員とマフィアの関係が明るみに出るのを恐れる上司と衝突しながら亡命計画を練る。舞台はロンドンからパリへ、さらにスイスへと移ってゆく。最後は『寒い国から帰ってきたスパイ』を思い出させるシチュエーションになって、はらはらどきどきさせてくれる。
もっとも、この小説を読む楽しみははらはらどきどきではなく、登場人物たちのいかにもイギリス人らしい皮肉と冷徹な現実認識に裏打ちされた会話だ ろう。ペリーは部下のルークにこう語る。
「人びとの痛みから利益が生まれる。コロンビアだけで数百億ドル、コンゴでも数百億。アフガニスタンでも数百億。世界経済の八分の一だ。真っ黒い 金。われわれにはわかっている。……それがどこにあろうと、同じだ。ソマリアの将軍のベッドの下に隠されていようが、シティの銀行でビンテージ物のワインと一緒に保管されていようが、金の色は変わらない。血の金なんだ。……強奪、麻薬売買、殺人、恐喝、集団レイプ、奴隷化によってもたらされた利益だ。言い過ぎたようであれば、指摘してくれ」
ル・カレの小説は最近のエンタテインメント小説に比べると決して読みやすいわけではない。ディマという魅力的なアンチ・ヒーローこそいるものの、快刀乱麻の力をもったヒーローはいないし、色恋沙汰にも深入りしない。会話による心理ゲームが中心だから、派手なストーリー展開で読者を引っぱるわけでもない。小説全体が始めは暗灰色で模様も定かでないタペストリーのように見え、でも細部に目を凝らしてゆくとやがて登場人物一人ひとりの風貌がじわっと浮かび上がってきて、親近感を抱くようになる。その瞬間の快感こそが、ル・カレの小説を読む楽しみじゃないだろうか。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





