時間の古代史【三宅和朗】
時間の古代史
| 書籍名 | 時間の古代史 |
|---|---|
| 著者名 | 三宅和朗 |
| 出版社 | 吉川弘文館(189p) |
| 発刊日 | 2010.09 |
| 希望小売価格 | 1,785円 |
| 書評日 | 2011.02.10 |
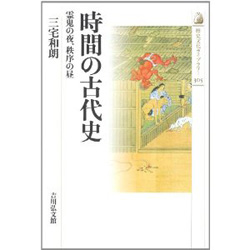
「霊鬼の夜と秩序の昼」という副題に惹かれた。現代に生きる我々は一日24時間を目いっぱい利用して多様な生活パターンを満喫しているのだが、いつでも利用可能なコンビニや朝までやっている飲食店などが存在する「現代の夜」と漆黒に支配される「古代の夜」とはそこに生活する人々にとってまったく異なった意味をもつ時間帯に違いない。近代に入り明るさをコントロール出来るようになった人類にとって夜の活動時間は圧倒的に多くなってきた。しかし、そうした状況も、ほんの100年程前までは朝は夜明けとともに起床し、暗くなれば就寝していたのが庶民の生活だ。ガス灯やランプといった近代照明器具が導入されていった明治時代初期でも日々の生活は天体の運行という自分たちではコントロール出来ない仕組みに大きく依存していた。
本書で紹介されている時間概念でいえば、「感じられた時間」(自然の動きがモデル)と「刻まれた時間」(時計によって刻まれた長さとしての単位)の対比が示されている。こうした点から古代の人々の「夜の時間帯」の意味や、その時間帯をつなぐ「夜明け」や「黄昏」などを含めて生活における時間感覚を探るというのがテーマである。「記紀」に始まって、「風土記」「日本霊異記」「今昔物語集」など膨大な資料から引用がされている。いくつかの説話は中学・高校の時に古文担当の板谷菊男先生から習ったようにも思われた。先生の得意な「おばけ」話というか「異類」話に属する引用も多く先生の講義の正当性も再認識できたのが収穫。
さて、古代ではどのように「昼夜」が異質な時間帯として認識されていたのかを示す例として、日本書紀から日本最古の前方後円墳と言われている箸塚の造成時の話しが「この墓は、日は人が作り、夜は神が作る」と紹介されている。このように夜と昼が異なる時間帯として認識されていただけでなく、百鬼夜行という言葉があるように、夜は人間以外の異類が活動する時間として古代人は考えていた。
「・・・視覚が遮られる夜は人間の創造力が発現する時間帯といえる。それに対して昼は人間が活動する秩序や必然性が支配する時間帯で、夜とは区別されていた。ここに古代の人々の心性を考察する糸口がある、つまり昼間と違って夜には人間の想像力が働くものとみられる・・・」
漆黒の時間帯を考えれば、人の想像力はいやが応にも駆り立てられる。その結果、人々の夜の事象は宗教的・原初的な活動が多くなるということか。神婚(妻問婚)などは夜の象徴であるし、祭りの多くも夜を本来の時刻としていた。例えば、風土記に書かれている夜祭りである歌垣とは春と秋に若い男女が集い歌舞、飲食し歌を掛け合う神祭りとしての行事である。しかし、葬送儀礼や死罪の処刑も夜に行われていた。興味深いことに平安京外からの帰京も夜の行事だったという。この理由は夜の時間帯に「神」になって入京するためともいわれているのは興味深い。
もうひとつの時間認識として示されているのが境界的な時間としての朝夕の重要さである。昼から夜に変わる時間帯は薄暗くなって人が誰だか見分け難くなることから「誰そ彼(たそがれ)時」ともいい、「魔」に出会うことから「逢魔が時」ともいっていた。今昔物語の中には時間の境界領域である「たそがれ時」と、場の境界領域である「橋」において鬼やら霊やら精が出現するという説話が多い。多くの夜にまつわる説話が紹介されている中で、夕刻の生活習慣として「夕占(ゆうけ)」という行動が万葉集などを引用して紹介されている。つまり、「夕暮れに道を行く人たちの会話や言葉によって吉凶を占う」という習慣があったようだ。しかし、占いとしては「夜」を前にした心性からするとあまり前向きなものにならないと思うがどうだろう。
一方、朝は、「闇の夜と太陽の輝く朝との境に、なにか特別な、くっきりとした変わり目の一刻があった。異変が起こるのはいつもその夜と朝の狭間、夜明けのころでなければならなかった。・・・」とある。つまり、夜明けは鬼の退場の時刻。夜から夜明けにかけて起こった異変が朝日の下で察知されて人々が驚愕するという時刻として理解されている。
したがって、その時間に異界のものが出現するということはない。朝の生活行事として紹介されているのは「変若水(おちみず)」という行事である。朝汲み上げたいわゆる神水を飲むことによって若返ったり、病気が治ったりという言い伝えである。新年にも若水行事があるように、毎朝もこうした新生感覚があるというところに境界領域としての「朝・夕」の差があったということ。
さて、昼は人間の秩序が優先される時間帯であるが、時刻によって行動が管理され始めたのは律令制成立期からのようだ。延喜式によると、各地域の祈年祭は「卯四刻」から始まるとある。卯四刻とは午前六時半のことだから、そこから始まって昼ぐらいまで行われた典型的な昼間の祭祀と言ってよい。また、新嘗祭や各地神社の祭祀の中で行われていた昼の祭祀が多く紹介されている。古代王権祭祀の中でも夜行われる行事と昼間に行われる行事があり、昼間に実施される行事はいずれも律令制成立後に実施されるようになったもので、国郡支配による服属儀礼の意味合いがあるという。古代の時刻制を示すものとして朝廷政治に関する日本書紀の記述が紹介されている。
推古12年(604年)の記述には当時の役人達が朝廷に参内することを怠っているとして、卯の時(午前6時)前に朝参し、巳の時(午前10時)の後に退朝させるという指示が出されているのも象徴的だ。ただこうした政治の場で時刻の精度を上げて管理され始めたのは中大兄皇子が「漏刻(水時計)」をつくり時を知らせた斉明6年(660年)が記録として残されていることである。こうした時刻管理の国家としての広がりと定着を示すものとして1981年奈良県の水落遺跡で漏刻台の遺構が発掘されことは歴史家たちから注目されたものだ。
このように昼の秩序は観念的な時間ではなく、時刻として管理され社会制度の進化に貢献していった。近代になってますます昼夜の同質化が進むことによって、人間に対して別の問題を引き起こしている。確かに「夜の秩序化」は人類にとって進歩ではあったものの、その意味を冷静に考えてみる必要もあるだろう。現代の我々には「新しい夜の自我の形成を必要としている」と著者は課題提起している。歴史の視点や環境の視点からの議論の広がりも望まれているようで著者の次のステップに期待がかかる。「日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか」という課題も魅力的だ。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





