なぜヒトは旅をするのか【榎本知郎】
なぜヒトは旅をするのか
| 書籍名 | なぜヒトは旅をするのか |
|---|---|
| 著者名 | 榎本知郎 |
| 出版社 | 化学同人(208p) |
| 発刊日 | 2011.01.20 |
| 希望小売価格 | 1,575円 |
| 書評日等 | - |
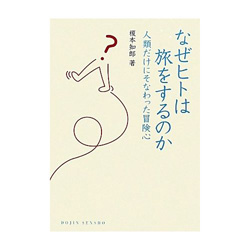
「遠い世界に旅に出ようか・・」という西岡たかし作詞の歌があった。学生の頃の歌だ。それにつけても、演歌であれジャズのスタンダードであれ、人間は「旅」にまつわる詞を多く生み出してきた。TV番組に目を向けても「旅もの」は根強い支持がある。旅は楽しいし、好奇心を満たしてくれるちょっとした冒険の時間なのだろう。それでは「なぜヒトは旅をするのか」とまともに質問されてみるとなかなか答えが難しい。この問いを人類学のテーマとしてみようというのが本書の狙いである。著者が示す旅とは「『うち(仲間)の集団』の生活圏を出て『よその集団』の生活圏に入り、その集団の人たちと敵でも味方でもない対等なコミュニケーションをとりつつ、その集団から食事や宿舎の提供を受け、何日も移動しながら最終的には『うちの集団』に戻る行動」というもの。
まず、「ヒト」の移動や旅を歴史的な視点から類型化を試みている。「グレート・ジャーニー」といわれている20万年前に南アフリカに生まれた「ヒト」の移動があった。中近東から中央アジアに到達し、当時地続きだったベーリング地峡を通ってアメリカ大陸に渡っていった。この大移動は何万年もかけて行われ、南アフリカに戻ることなく「ヒト」は各地に定着していった。こうした「ヒト」の移動は海洋を渡るケースを含めて数多く知られている。
次に、仏教僧の旅である。4世紀の中国の僧法顕の旅は「法顕伝」として残されているのでその状況を知ることが出来る。法顕は法典を求めて旅立ったものの、路銀を潤沢に持っていなかったので、ひたすら托鉢をして喜捨を受けながら旅を続けた。長安から6年をかけてインドに着き、そこで6年間研鑽を積み長安に戻ってきたのは旅立ってから14年後のことである。また、時代が下った7世紀には唐の玄奘が国禁を犯して出国している。16年間におよぶ旅の始まりである。このとき玄奘は学才の誉れ天下に高く、行く先々の君主・国王などから手厚い待遇を受けたともいわれている。この旅から「大唐西域記」が生まれ、伝説としての「西遊記」が書かれた。
このように、気の遠くなるような長い旅もあれば、一方通行の移動の典型的な例としてお輿入れがある。古代エジプトでの1500km離れた国からの嫁入りの歴史もあったと聞くと、言葉も文化もまったく異なる土地に輿入れをする少女の不安を察するに余りあるが、こうした嫁入りにまつわる移動は庶民にしても数多く経験していたものである。
また、好奇心に駆られての旅というと、14世紀のモロッコに生まれたイブン・バットウータという男が紹介されている。名目としては聖地メッカを目指したというものの、以来28年間、エジプト・インド・東アフリカ・中央アジア・黒海・イスタンブール・中国にまで足を延ばした旅であった。帰国するとスルタンは彼を呼び出して、世界について語るよう指示し「大旅行記」が生まれた。日本人では森本右近太夫という人物が紹介されている。
この男、江戸時代カンボジアのアンコールワットに落書きを残したために名が知られているのだが、彼は両親の死後、祇園精舎として知られたアンコールワットに仏像を寄進する目的で旅立ったのが1632年である。この二人のケースで重要なことは誰かに命じられて使命をもって旅したのではないということである。聖地メッカを目指すとか、祇園精舎に仏像を寄進するというのも何やら楽しい旅の言い訳にしか思えない。「東海道中膝栗毛」が大ベストセラーになったのも庶民の旅の憧れが強かったことを示している。
これに比較して動物や昆虫の移動も紹介されているのだが、最大の違いは「ある集団の生活圏を出て移動し、再びその生活圏に戻ってくる」という「旅」という移動様式は動物界にはないということだ。越冬や繁殖のための移動としての「渡り」はある、群れを離れ他の群れに入ることはある、集団でテリトリーを捨てることもある、ただ「旅」はない。
「ヒト」が旅をすることが出来る条件として、「見知らぬ人を敵として排除しない。だからといって、味方でもない。こうした中立的で対等な関係に立ってコミュニケーションができる」という能力・性質を「許容」ということばで著者は表現している。この「許容」が生み出される要因として、「ヒト(現生人類)」の遺伝子のバラツキが他の動物の種に比較して極端に少ないことが挙げられていて、これは地球寒冷化の時期に人口が急激に減少した結果ともいわれている。「ヒト」は文明を手に入れ始めた7000年前と比較しても特異的な進化の痕跡は認められないということがポイントである。
仮にタイム・マシンが発明されて1万年前の「ヒト」の赤ちゃんを現代に連れてきて育てても、時代と文化に馴染んでなんの違和感もなく生活するだろうと言われているくらい人と人の付き合い方はあまり変わっていないし「うちの集団」と「よその集団」という生活圏が違っていても、また言葉が通じなくとも基本的なコミュニケーションを可能にしているのが実体。身振りや表情でやり取りが出来るし、その状況さえわきまえていれば言葉か通じないこともさしたる障害にならないのは今も昔も同じである。
「あいさつは敵意のないことのメッセージであると同時にあと平静な気分でコミュニケーションをとるための準備の働きがあるといわれている。コミュニケーションの場を作るためのこうしたコミュニケーションをメタ・コミュニケーションと呼ぶ・・・・」
このメタ・コミュニケーションという概念が「許容」という性質に弾みをつけるもので、あいさつをするときほとんどの人は「ほほえみ」を浮かべるのはどの民族にも見られるし、もうひとつの共通行動といわれている「おじぎ」なども文化や時代を超えている。
こうした「許容」という性質が進化していった理由を以下のように説明している。 「男の狩猟は一人で立ち向かえる大きさの獲物をとることから始まって、段々と大型動物を狩りの対象としていった。このために大きなグループで行動することが必要になってきた。時には数百人が役割分担を定めて臨機応変に集団行動を行う必要が出てきたわけだ。そうした動きが出来たのはホモサピエンスだけだった。・・・・これは社会生活における革命だった。・・・・」
一方、大型類人猿は手話などシンボルを操作する能力がありながら言語を進化させることが無かった。言語が進化するには、それを用いて調節するコミュニケーションの場が共通化する必要があるのだが、彼らの生活の中ではその必要性がなかった結果であると同時に当然のことであるが「許容」も性質として深まることは無かった。
また、メタ・コミュニケーションによって「ヒト」は言語とともにトレードという概念を手にし、敵対でも親和でもない相互対照的な交渉を可能にしたという指摘は面白い。遺伝子中心主義説の浸透によって、「肉親を助けて、わが身を捨てる」という利他行動が説明された結果、遺伝子差が少なく、あたかもクローンの集団のようなわれわれ「ヒト」はその個体の適応度(利己的な要素)が低下しても利他的な包括適応度(全体最適度)が上昇することが多いし、仮に包括適応度が低下したとしても、ベネフィットさえあればその低下を相殺することもありそうだ。「旅人になけなしの食料と宿を提供する」ことに対するベネフィットこそ「自分の知らない情報を得ること」という著者の仮説は興味深いが、さてそれだけかというパンチの弱さも感じた。
日常の事柄を考えるためのヒントとして面白く本書を読んだ。ただ、本書は「旅」という行動の意味について納得感を得るためのものであって、読後に「さァー旅に出るぞ」という気持ちを湧き立たせるものではないことだけは指摘しておきたい。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





