帝国の残影【與那覇潤】
帝国の残影
| 書籍名 | 帝国の残影 |
|---|---|
| 著者名 | 與那覇潤 |
| 出版社 | NTT出版(240p) |
| 発刊日 | 2011.1.21 |
| 希望小売価格 | 2,415円 |
| 書評日 | 2011.02.10 |
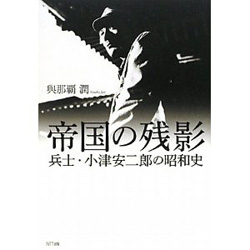
1937年。既に日本映画界の若き巨匠として名声を確立していた小津安二郎は帝国陸軍に召集され、1939年までの2年間、一兵士として中国戦線で戦った。その足跡は上海から内陸の漢口、武昌にまで及んでいる。そうした小津の兵士としての中国体験が、戦後、小津映画にどんな影響を与えたのか。日本近代史の研究者である著者が、小津安二郎の作品を通して昭和史を考えてみようというこの本のモチーフはとても魅力的だ。
小津安二郎の代表作といえば『晩春』とか『東京物語』とか、家庭内のささやかな出来事に家族の心がいっとき揺れるが、やがて穏やかな結末を迎える家族映画、というのが誰もが思い浮かべるイメージだろう。確かに戦後の小津映画に、正面から戦争と敗戦後の社会をテーマにした作品はない。『二十四の瞳』『また逢う日まで』といったヒューマンな反戦映画が次々につくられていた時代に、「小津は戦争と戦後の現実を描いていない」という批判があったくらいだ。
ところで「家族映画の巨匠」小津安二郎が生涯を独身で貫いたことは、小津ファンならよく知っている。與那覇は、「みずから体験した戦場を描き出すことなく、しかし自身は形成した経験のない家族について語りつづけた小津という人物の秘めた謎」に着目する。
中国戦線から帰った小津は国策映画『ビルマ作戦・遥かなり父母の国』の準備に取りかかったが、現在から見れば幸運なことに戦局の悪化から製作中止が決まり、結局、小津が戦争と戦場を映像化することは一度もなかった。でも戦後の小津作品を仔細に見ていくと、人物の設定やセリフの端々にまぎれもなく戦争の影が見え隠れしている。與那覇はそうした映画の細部に注目して、まずそれらを拾い集めてくる。
著者がつくった三つの表が面白い。「後期(戦中・戦後)小津映画における『戦争』と『植民地』への言及一覧」「戦前の小津作品における暴力関連描写一覧」「戦後の小津作品における『中国的』要素一覧」。
「戦争」と「植民地」への言及については、全17作品のうち16作品で登場人物の戦争と植民地への関わりが示唆されている。「暴力描写」は夫が妻を殴るといったシーンが多いが、この表の背景について與那覇は、「家族という場が自然なトポスではなく……人為的な強制力が必要」で、「都市部での皆婚化と家族形成というこの時期新しく始まった日本人の生き方こそが、戦争に淵源する巨大な暴力のもとで形成された、奇妙な様式」だったと指摘している。小津映画では戦場が直に描写されることはなかったが、その代わり近代的家族というもうひとつの戦場での暴力が描かれた、ということだろうか。
「中国的」要素については、登場人物がマージャンで遊んだり中華料理屋で会ったりするのだが、それらはしばしば家庭の平和を乱す要因につながる。與那覇はそこに、「戦争の影の下で統合された日本家族の構図が揺らぐ場面に、つねに中華風のモチーフを採用するという小津安二郎の記号学」を見る。そこにもまた、小津の中国と中国的なものに対する複雑な感情が隠されている。
戦後の小津映画のなかで、與那覇は『風の中の牝雞』『宗方姉妹』『東京暮色』という3本の「失敗作」に注目している。「家族映画の巨匠」小津の名声を決定づけた『晩春』『麦秋』『東京物語』『彼岸花』といった名作群にはさまれて、小津は彼の作品系列のなかでは異色の、どちらかといえば家族の崩壊を描いた暗いトーンのこれらの映画を撮っている。それは興行的にも、作品の評価でも「失敗作」とされている。だが、なぜ「失敗」なのか?
例えば『宗方姉妹』(1950)は、大仏次郎の小説を原作とするこんな映画だ。主人公一家は戦前、満州の大連にいたと設定されている。技術者だったらしい父(笠智衆)は引き揚げて引退し、姉(田中絹代)は父の後輩らしい男(山村聡)と結婚している。独身の妹(高峰秀子)は姉夫婦と同居している。山村聡の夫は職もなく、無為に原書を読んだり酒を飲んだりの日々で、ことあるごとに妻の田中絹代に辛く当たる。高峰秀子の妹は、姉の夫の仲間で、大連では姉の恋人だったらしい男(上原謙)と親しくしている。横暴な夫に耐える良妻賢母型の田中絹代と、奔放なアプレゲールの高峰秀子。敗戦の挫折から虚無に沈む山村聡と、戦後は家具作りに転進して成功した上原謙。4人の男女の微妙な関係が、山村聡と田中絹代の夫婦に亀裂を生じさせてゆく。映画の最後で、山村聡は自殺とも疑われる突然の死を遂げる。
高峰秀子演ずる妹は「満里子」という名なのだが、これは「満洲里」という地名からつけられている。「『大連で生まれて、あちらで教育を受けた』がゆえの奔放さを設定されている宗像満里子によって、前作『晩春』で様式化された日本家族のモラルは真っ向から否定される。そればかりではない。満里子を演ずる高峰秀子は、上原謙扮する宏の前で、しばしば彼と姉の関係を揶揄した一人芝居を演じる。これは原作にない映画独自のモチーフであり、結果として満里子の宏への告白も、演技の続きなのか、それとも本気なのかが判然としないように撮影され、小津映画が提示する家族の物語自体が『演じられたもの』にほかならないことを、言外に仄めかすかのごとくなのだ」
つまり、『宗方姉妹』という作品は「『晩春』に代表されるいわゆる『小津調』の家族映画に対する、一種の自己批判となっている」と與那覇は言う。
もう一本の「失敗作」である『風の中の牝雞』では、敗戦後の生活苦から一夜の売春をした田中絹代は、復員してきた夫の佐野周二に階段から突き落とされ、危うく死にかける(映画監督の黒沢清によれば、「(家族の)全員が死んでいるとしか思えない」)。
一方、『東京暮色』で主人公一家は京城(ソウル)から引き揚げてきた。京城での家庭崩壊が原因で、一家の娘(有馬稲子)は自殺に近い事故死に至る。『風の中の牝雞』も『宗方姉妹』も『東京暮色』も戦争と大陸の影が色濃く、どの映画にも死(あるいは死に近いもの)が訪れる。この3本の「失敗作」は、小津が彼なりのやり方で戦争体験を語ろうとした作品なのではないか。
もっとも僕がこの3本を見た印象では、どの作品でも小津の演出は極めて抑制され、音楽も高鳴ることなく、小津映画の常として感情が高揚するカタルシスに至らない。当時のリアリズムを基準にすれば、映画にドラマチックな感動を求める観客はこれらの小津映画を見て欲求不満に陥ったはずだ。また作品全体としても、いわゆる小津調のシーンと暗くリアルなシーンとが齟齬を来して、全体として必ずしも出来のよいものではないと思う。それが「失敗作」という評価につながったのだろう。その一方、原節子が「紀子」を演じた『晩春』『麦秋』『東京物語』の「紀子三部作」は、美しい風景のなかで展開される日本的な家族の物語として高い評価を得てゆく。
もっともそれは、小津の問題である以上に観客である戦後の日本人の問題だというのが與那覇の考えだ。
「(小津の世界から)植民地の影と帝国時代の記憶とを消し去り、『日本的』という修辞へと回収せしめたのは、制作者たる小津本人以上に、受容者の意識ないし無意識であったといわねばなるまい」
「戦後の小津映画の歴史は『名人らしからぬ失敗作』を撮るごとに、原(節子)の出演作によって『名匠の栄光』を取り戻すという過程の反復となってゆく──小津のキャリアの頂点として人口に膾炙するいわゆる紀子三部作は『宗方姉妹』による自己批判を経てもなお、人々が小津映画に求めたものが『晩春』の『嘘』(注・『晩春』の穏やかなラストが、シナリオと異なる偶然の産物だったこと)の方だったことを証しだてるものかもしれない。殊に小津安二郎の作品に関する限り、いつも内地で完結する家族の物語が勝利し、それを危機にさらす帝国の影が忌避されてきたのである」
そのようにして、小津安二郎は「家族映画の巨匠」として神話化されていった。
ところで、この原稿を書くために『宗方姉妹』を見直していて気づいたことがある。小津映画にはしばしば「空(から)ショット」と呼ばれる画面が挟みこまれる。それまでの物語の展開とは無関係に挿入される「風景ショット」のことで、それが小津独特のリズムや間を生んでいる。今では「空ショット」を好む監督も多いけれど、その源泉(少なくともその一人)は小津だと言えるだろう。戦前から戦後間もなく撮影された作品で小津が好んだ空ショットは、一方で山や空などの自然風景であり、他方でビルやガスタンクといった都市風景だった。
こうした都市風景の空ショットについて、小津は新興写真と呼ばれた写真の新しい動向に敏感だったのではないかと感じたことがある。昭和初期に台頭した新興写真は、それまでの絵画的な「芸術写真」でなく、都市のリアルな風景を捉えることを特徴とした。小津はライカを愛用していたことからも分かるように写真好きだったし、新興写真の担い手の一人だった木村伊兵衛らと写真と映画に関する座談会に出席したこともある。だから小津の空ショットと新興写真とが親近しているのは、ある意味で当然かもしれない。
『宗方姉妹』に戻れば、この映画でも空ショットが何個所か挿入されているけれど、いちばん目立つのは墓石のショットだ。墓石が立ち並ぶ墓地のショット、墓石の向こうを省線が走るショット、後半でももう一度、墓石のショットが出てくる。何の説明もなく繰り返し挿入される墓石のショットに、見る者はぎくりとし、なにやら不穏な気配を感ずる。ただし、その気配が次に何らかの映像やセリフによって具体的に説明されることはない。
それが分かるのは映画を見終わってからで、その墓石の空ショットは、映画の終盤で山村聡が突然のように死んでしまう、その死の予兆であったことに気づく。小津は墓石の空ショットをあらかじめ挿入することによって、山村の死を映画全体の空気を支配する出来事として提示したのだと思う。山村の敗戦後の虚無が満洲のどんな体験によったものかを、小津は例によって説明していない。しかしそれだけに、戦争が小津映画の登場人物にもたらしたもの、あるいはそのような人物を造形した小津本人にもたらしたものを、さまざまに想像することができる。
この本で、與那覇は小津映画の「戦争と植民地」「暴力」「中国的なるもの」を拾い上げ、それを基に小津映画の「帝国の残影」を探ってみせた。同じように小津作品のすべての空ショットをピックアップしてみると、そこから見えてくるものもあるのではないか。そんなことを考えた。時間があれば全作品を見直して、やってみたい。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





