焼き餃子と名画座【平松洋子】
焼き餃子と名画座
| 書籍名 | 焼き餃子と名画座 |
|---|---|
| 著者名 | 平松洋子 |
| 出版社 | アスペクト(280p) |
| 発刊日 | 2009.09.30 |
| 希望小売価格 | 1,785円 |
| 書評日等 | - |
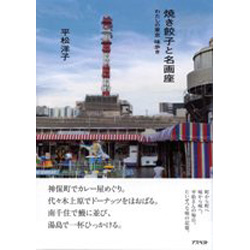
本書はタイトルの通り極めて「日常的」な食に関するエッセイである。それにしても上手いネーミングだ。「とびっきりの東京の味」というサブタイトルを見るとレストラン・ガイドかと誤解しそうであるがそうではない。世上、食べ物に関する書物はこの四半世紀で飛びぬけて増えた出版領域の一つだと思う。「食材」に関するもの、「料理」を作るもの、「食べる」という目線でのレストラン・ガイドなど、多くの食べ物本のジャンルがある中で圧倒的に「食べる(レストラン・ガイド)」領域が多くなってきたのは何故だろうか。季節の食材を家庭料理で楽しむという風潮はなくなったわけではないにしても、プロの技を堪能し、とても素人では作れない料理を賞味するという時代になったのだろうか。日本、特に東京では世界の美食が堪能できるといわれ、日本も豊かなったと20年前には素直に思っていた。しかし、いまや世界の美食は中国にとって代わられつつあるというのも事実。それでも日本ではレストラン・ガイドが夥しく出版されている。そこで、一般人が予約し難い店や、個人が自費で食事をするにはひどく高価な店などの紹介されているのを見ると、何の為のガイドかと疑問を持つことも度々ある。
本書はそうした非日常的なファションとしての食と店の紹介ではなく、店・料理と著者自身の生活を交えた食のエッセイである。
「町歩きは、てきとうに気が抜けているほうがいい。お天気がよくて、用事に追われていなくて、路上観察とか、果したい目的とか、なにもないのがいい。糸の切れた凧になれるから。けれども、よくばりな気持ちもやっぱりどこかにあるので、おいしい匂いや気配にだけは反応してしまう。・・・・・皆それぞれに自分の町の地図をもっている。歩いたぶん、暮らしたぶんの歳月が降り積もってできあがった地図。・・・・・ひとりひとりの地図は微妙にずれたり重なったり、そしてあたらしい書き込みを増やしたり消したりして書き換えながら、自分だけの一枚が胸におりたたみこまれる。時間は流れて過ぎるものではない。ゆっくりと重なって堆積していくのだ・・・・」
まずは、土地と時代。そして構成は『昼』・『小昼』・「薄暮」・「灯ともし頃」と一日の食を楽しむ時間によって章立てされている。時間が遅くなるほど料理と酒のバランスは微妙に変化して、食よりも酒が主役の場所も登場する。それにしても、料理と店(建物と人)、そして場所が一体となって食が語られているのだが、そこに表現されている時空は1970年代初めから現在までの間をゆっくりとその時間軸は揺れ動いている。大きな柱時計の振り子のような文章だ。その一つが本書のタイトルにもなっている「焼き餃子と名画座」である。
「きょうはすかっと晴れて風薫る5月の昼下がり、うきうきとした気分で神保町のちいさな映画館をめざすことにした。ずっと観たかったのにどこの名画座にもいっこうに掛からず、いや掛かっていたのかもしれないけれど、まるで気づかなかった。そんな一本に巡り合う機会がやってきたのだもの・・・考えてみたら、休日でもないのに日の高いうちから名画座に足を運ぶというのもかなり小原庄助さん的である。ひとさまが働いていらっしゃる時間だというのにうきうき名画座を目指して歩いていると、優越感と一緒に後ろめたさが顔をのぞかせる。・・・おまけに胸に一物あるのです。映画を観終わったら映画館の真向かいの『天鴻餃子房』で生ビールと焼き餃子で・・・・・・」
という流れで、「天鴻餃子房」の餃子が美味そうに語られていく。映画が大切な文化のキーワードであった時代は団塊の世代が体験したものであるし、餃子も団塊の世代の青春からは捨てがたい。著者の平松は映画に関して言えばかなりマニアックだ。なにしろ観にいっている映画は「小原庄助さん」・監督は清水宏・1949年の新東宝作品。食べ物の本であるから著者は必然的に食いしん坊なわけであるが、食い気と興味と文才が合体したときにその力は最大化される。また、特定の食べ物を食べたくなる瞬間をこんな風に表現している。
「後戻りのきかない味がある。いったん思い出すと困り果てる。例えば、とんかつ、焼き鳥、鮨。この三つばかりはいったんスイッチがはいってしまうと代替がきかず、軌道修正がむずかしい・・・・」
あるな、こうした食べ物が。著者が挙げた三つとは違うものの、無性に食べたくなる料理は評者の中にも存在する。ただ、どちらかというと、とんかつとかカレーといった「料理」よりも店が特定される傾向が強い。「渋谷百軒店にあるムルギーのカレー」とかがその最たるものである。私とて東京中のカレーを食べつくして渋谷ムルギーにたどり着いたということではなく、学生時代に大学から帰宅する途中の渋谷の百軒店に有ったジャズ喫茶の「ブラックホーク」に入り浸っていた時代。腹が減ったといっては、ムルギーに行ったり、麗郷に行ったりしていた。そうした時間の堆積の中に食べ物が存在している。
今となっては、「ブラックホーク」はもうないのだが、ムルギーも麗郷も健在なのはうれしい限りである。つまり、ムルギーも麗郷も現在の味だけでその料理を評価することは不可能なのだ。時代がついて回る。同様に、「美味い料理」や「美味い店」というよりも「好きな料理」と「好きな店」という選択の結果が本書を貫く姿勢であることが良く判る。加えると、「好きな時間・好きな場所」という要素が主観的に組み合わされて、著者は東京をそぞろ歩いている。
想像するに、数多くの店を食べ歩き、美味いものも、不味いものも体験して、紹介されている180店は選ばれているのだろう。評者がこれらの店について考えてみると、1/3はいったことのある店である。しかし1/3の店は名前は聞いたことがあるだけだったり、はたまた全く初めて聞く店だったりする。特に武蔵野・吉祥寺・荻窪・阿佐ヶ谷といった地域は評者にとっては全くと言っていいほど土地勘がないので当然ながら紹介されている店はほとんど知らない。
しかし、そこで語られている時間と空間は主題である食べ物を越えて面白い。それは筆者の筆力とともに共有していた過去の時間の感覚が同一の波長なのだろう。こうした不可思議な求心力が本書にはある。共感と異議を許容する力だ。著者平松がとんかつの「聖地」は新橋の燕楽だと声高に叫んだとしても、俺は違う、「目黒のとん喜だ」とか「日本橋のかつ吉だ」とか言いたいことのいえる余地こそ本書のオープンな感覚の良さである。 (正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





