マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー【野谷文昭】
マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー
スペイン語翻訳者の9年ぶりのエッセー集
| 書籍名 | マジカル・ラテン・ミステリー・ツアー |
|---|---|
| 著者名 | 野谷文昭 |
| 出版社 | 五柳書院(448p) |
| 発刊日 | 2003.12.12 |
| 希望小売価格 | 3200円 |
| 書評日等 | - |
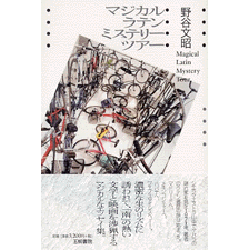
訳者で買ってしまう本がある。しかもそれが好きな著者の本であれば、買ったときからもう悦楽の読書が約束されたようなものだし、知らない著者の本であれば、この人が訳したのなら面白いにちがいないと勝手に思いこむ。
そんな訳者が何人かいる。ドイツ語の池内紀、フランス語の堀江敏幸、英語の井上一馬、田口俊樹といった人たち。僕にとっては、スペイン語の野谷文昭もそんな一人だ。
ガルシア=マルケス「予告された殺人の記録」やボルヘス「七つの夜」の訳者として知られる野谷だが、なかでも「蜘蛛女のキス」や「赤い唇」などプイグの小説は、野谷の色彩とリズム感あふれた翻訳によって、その作品の隅から隅までが僕らの脳裏に刻みこまれている。
この本は、野谷の9年ぶりのエッセー集。ラテン・アメリカやスペインの文学、映画、音楽、美術、さらにはスポーツが論じられ、また中上健次や村上春樹、村上龍ら日本の作家がラテン・アメリカの影という視点から論じられる。その時々に媒体に求められて書いたエッセーを集めたものだが、短いものでも長いものでも、その姿勢は見事なほど一貫している。
僕たちは往々にして、たとえばラテン・アメリカ文学なら「南への憧憬」とか「マジック・リアリズム」とかいう言葉で、なにか分かったつもりになってしまう。
野谷はそんな「常識」に、決して声を荒げることなく、しかし断固としてごつごつした石を投げ込んでみせる。たとえば中上健次の作品でアルゼンチンは南の国として描かれるけれど、ブエノスアイレスの人々にとって南国とはブラジルであり、「彼らの街は冬の寒さが身にこたえる場所なのだ」といった具合に、「南」幻想の修正を僕たちに迫る。
あるいはまたウォン・カーウァイの映画の手法が、ラテン・アメリカ文学を媒介にしてフォークナーにつながっているという指摘がなされて、ふたつの名前の結びつきの意外さと新鮮さにびっくりさせられてしまったりもする。
ここで野谷が僕たちに教えてくれるのは、「「百年の孤独」で氷や磁石を驚異的なものと見るマコンド(小説の舞台となる架空の土地)の住民のパースペクティブを取り敢えず認めること。彼らの目で世界=現実を眺めること」の大切さなのだろう。そうすることによってはじめて、常識や思い込みにとらわれた「他者像の歪み」を修正することができる。
もっとも、こうしたいくぶん啓蒙的な仕事は、野谷の過去のエッセー集でも同じように試みられていた。この本の魅力はそれだけではない。これまでのエッセー集にはなかった、あるいはあったとしても遠慮がちにしか展開されなかった要素が2つ、大きくフィーチャーされている。
ひとつは、野谷の「私」が前面に出ている文章が収められていることだ。なかでも「丸子多摩川と二子玉川に挟まれた楽園」で過ごした少年時代の記憶を語ったいくつかのエッセーは、こちらが野谷と同世代であり、野谷が東京の南の境を流れる多摩川の河原で遊んだのに対し、僕は東京の北の境を流れる荒川の河原で遊んだという似た体験があるだけに、その情景が手に取るように理解できる。
もうひとつは、旅の文章がいくつも収められていること。たとえば「ジンジャーとカトレア」は、こんな書き出しで始まる。
「匂いが瞬時にして過去の記憶を甦らせることがある。たとえば、柑橘類の花の甘く刺激のある香りを嗅ぐと、宵闇に包まれたコルドバ駅のプラットホームが目の前に現れる。あれは夏だった。アンダルシアを回り、マドリードに戻ろうと夜行列車を待っていたときのこと、強い匂いに誘われて、ホームを進むと、白い花をつけた小さなオレンジの木が立っていた」
まるで短篇小説の書き出しのような、こんな描写ひとつで、読む者は野谷の記憶の世界へと連れ去られてしまう。翻訳と同様に快いリズムを持ち、決してべたつくことない野谷の文章は、冷たい官能とでもいったものを感じさせる。旅の文章では、その持ち味がいよいよ冴えを見せる。
「サン・アンヘルの石畳」は、メキシコ・シティーに長期滞在したときの体験だが、こちらでは旅のもつ気楽さと甘さばかりでなく、通りすがりの旅行者には見えないものにまで錘が下りてくる。
「職人はたいていメスティーソか先住民である。それに屋敷で働くメイドや炊事婦、洗濯係、執事もメスティーソや先住民系が多い。主人はほとんどが白人で、車を使うから石畳を歩くことはあまりない。だが使用人や職人は、郊外や下町からミクロ(小型バス)かメトロに乗り、徒歩でやってきて、石畳を歩く。車がないので、私も毎日石畳を歩いた」
そのような「石畳を歩く」姿勢によって、野谷が滞在した家の主人である白人インテリの交友関係ばかりでなく、メスティーソや先住民が混在する社会階層の微妙な関係が見えてくる。「第三世界」という言葉だけではくくれない世界が見えてくる。
読者としての勝手な願望を言わせてもらえば、僕は野谷の、翻訳の副産物ではないエッセーを読んでみたい。次の著書では、専門である文学と、現場での体験(できればハバナあたり)と、それらに触発される思索とが組み紐のように縒りあわさった陰影のある長い独立したエッセーを読みたい。野谷文昭はそれだけの魅力をもった書き手だと僕は思う。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





