メルトダウン【大鹿靖明】
メルトダウン
| 書籍名 | メルトダウン ほか |
|---|---|
| 著者名 | 大鹿靖明 |
| 出版社 | 講談社(368p) |
| 発刊日 | 2012.01.27 |
| 希望小売価格 | 1,680円 |
| 書評日 | 2012.04.11 |
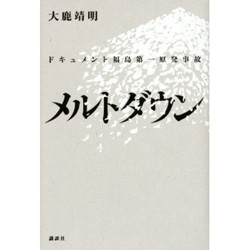
+「レベル7」東京新聞原発事故取材班/「プロメテウスの罠」朝日新聞特別報道部
マス・メディアの重要な仕事のひとつに調査報道がある。日々のニュースを追うだけでなく、時間をかけた独自の取材で事件や事故の全体像を描き、問題をえぐりだす。手間ひまも金もかかり、時に権力の内側にまで入り込む必要もあるから、今の日本で個人の力で調査報道を継続することはむずかしい。
福島第一原発の事故は、最悪の場合、首都圏の避難という国の存亡にも関わりかねない大事故だった。そのとき、現場の第一原発や官邸、霞が関で何が起こっていたのか。巨大地震や津波とともに、これこそマス・メディアの調査報道の力が試される出来事だったろう。それに対する答えが、ようやく単行本になりはじめた。
『メルトダウン』は、事故直後の緊急事態に現場と官邸がどう対応したかを中心に、菅政権が崩壊するまでを主に官邸や経産省、東電本店など中央の側から描く。著者の大鹿は雑誌『AERA』の記者で、菅直人(当時・首相)、福山哲郎(官房副長官)、寺田学(首相補佐官)、下村健一(内閣審議官)ら事故対応に当たった当事者へのインタビューが可能だったのは、むろん彼が属する朝日新聞というバックがあってのことだろう。東電本店や保安院、経産省の幹部(匿名も実名も)はじめ、125人への取材・インタビューがこの本の基になっている。
『レベル7』は、脱原発の姿勢を鮮明にして活発な紙面をつくっている東京新聞に連載されたもの。事故から1週間の動きが時系列に沿って再構成されているので、危機がどんなふうに進行したかがよく理解できる。過酷な事故現場で働く下請け作業員への取材も含め、現地と中央にバランスよく目配りも効いている。また事故直後の動きだけでなく、汚染水との闘いや、過去に遡って原発という国策がどう推進されたかの歴史が検証される。
『プロメテウスの罠』は朝日新聞に現在も連載がつづく長大な企画の第1巻。事故直後、汚染が知らされる前の浪江町に現れた謎の「防護服の男」や、自粛を求める厚労省所管の研究所に辞表を出して現地へ放射線測定に向かった「研究者の辞表」など、さまざまな角度からのヒューマン・ドキュメントによって事故の全貌に迫ろうとする。硬派の連載には珍しく、面白い読み物としての工夫がなされている。
事故が起こったとき、僕もテレビに釘付けになり危機の進行をはらはらして見守った一人だけど、あのときの真相はどうだったのか、知りたいポイントがいくつかある。それがこの3冊でどう描かれているかに興味があった。
巨大な地震と津波に対して東電も学者も「想定外」という言葉を連発した。でも地震も津波もこれまでの「想定」でいいのかという疑問は何人かの研究者から既に提出されていたし、「全電源喪失」の危険も指摘されていた、と『レベル7』は明らかにしている。
そうした事故以前の「罪」も大きいけれど、事故後最大の「罪」は、汚染の広がりを予測するスピーディ(SPEEDI)が生かされず、激しく汚染されている地域に避難したり、汚染を知らされずに取り残されて、多数の住民が浴びなくていい放射性物質を浴び、将来の不安に脅える結果になってしまったことだろう。スピーディがなぜ生かされなかったのか、そのいきさつを『メルトダウン』が追っている。
3月11日午後9時、2号機の爆発を避けるためにベント(放射性物質の放出)を行わざるをえなくなり、保安院は初めてスピーディを動かして汚染のシミュレーションをした。12日午前1時には2回目のシミュレーションが行われている。その結果は官邸地下の危機管理センターに届けられ、各省庁から派遣された連絡員に手渡された。ところが、この情報が肝心の菅、枝野(官房長官)、海江田(経産大臣)らに届けられなかった。午前4時にもスピーディのシミュレーションが行われ、風向きが変わって放射性物質がそれまでの海側でなく内陸に向かうという結果が出たが、この情報もまた官邸中枢に届かなかった。結局、スピーディのデータのほとんどは保安院に退蔵されたままになった。
大鹿の取材に、スピーディのデータを官邸に送った保安院の責任者(実名)は「物理的に端末があったから僕のところを経由した形になっているだけ」と答え、災害対策監(実名)は、スピーディのデータが住民避難に役立たなかったことについて「思い至らなかった」と答えている。「日本の最高学府を出て政府に勤める男たちは、国民の安全に供する当たり前のことに、遂に一度も思い至らなかった」と大鹿は書く。
危機に際してほとんど機能しない官僚。危機管理のため首相の傍らに控えた保安院のトップは専門家でなく事務方だった。保安院は直に情報を集められず、東電に頼るしかない。その東電も現場と本店で情報が行き違う。官邸に詰めた東電幹部は現場と直でなく本店経由で情報を取っている。当初、首相が意見を求められる専門家は斑目原子力安全委員長ひとりで、それも「爆発はない」と楽観的な見通しを語るばかりだった。情報を収集・判断するシステムの機能不全に加えて信頼できる専門家も不在で、事態の進行に振り回されるばかりの政治家。事故直後の官邸は、はらはらしながらテレビを見る僕らと大して変わるところがなかったように見えるのが悲しい。
もうひとつ知りたかったのは、東電が撤退を申し出、菅直人が「撤退はありえない」と命じた「事件」。東電は本当に「撤退」するつもりだったのか。
3月14日、1号機と3号機が水素爆発を起こし、2号機も冷却機能を喪失して危機が迫っていた。『メルトダウン』によれば、このとき第1原発所長の吉田は死を覚悟し、「各号機の制御に必要な要員を残して、大半は避難させよう」と考えた。同じころ、東電の清水正孝社長は海江田に「第1原発から第2原発に退避したい」と申し入れている。さらに枝野や細野(首相補佐官)にも同様の申し入れをし、拒否されている。しかし作業員の人命を考えると政権幹部たちも揺れ、首相に判断を仰ぐことになった。15日午前3時、菅直人を中心に会議が開かれ、菅の「撤退なんてありえないぞ」の一言で方針が決まった。翌朝、菅が自ら東電に乗り込むことになった。
後に東電は「退避と言った。撤退とは言っていない」と弁明したが、清水は海江田らに「最低限の人数を残す」という吉田の考えを伝えていなかった。だから申し入れを受けた海江田も枝野も清水の言葉を「全面撤退」と理解している。
『プロメテウスの罠』は、官邸の伊藤哲朗(内閣危機管理監)と東電幹部のこんな会話を記録している。
「第1原発から退避するというが、そんなことをしたら1号機から4号機はどうなるのか」
「放棄せざるをえません」
「5号機と6号機は?」
「同じです。いずれコントロールできなくなりますから」
「第2原発はどうか」
「そちらもいずれ撤退ということになります」
東電幹部が本当に「全面撤退」を考えていたのか、それともトップの説明不足(それはそれで緊急時の能力を問われる)だったのかは分からない。でもこういう会話を読むと、信じがたいことだがその可能性も否定できない。仮に「全面撤退」することになったら、東電幹部の言うように第1原発はコントロール不能になり、圧力容器や格納容器が爆発すれば、最悪のケースとして検討された「首都圏3000万人の避難」が現実のものになったかもしれなかった(現在も、4号機の燃料プールが崩壊すれば同様の危機と隣り合わせだ)。後に枝野は、「あの瞬間はあの人が首相で良かった」と振り返っている。
3冊のドキュメントを読んでいると、日本の政治と官僚と企業が非常時に際してほとんど機能していないのに唖然とする。日常の手続きにこだわったり(菅とともに東電本店に乗り込んだ細野は、撤退か否かの瀬戸際に総務部に稟議書をつくらせ回す姿にあきれている)、自ら能動的に動かなかったり(保安院は情報収集に東電本店に人を派遣せず、あまつさえ第1原発の現場からオフサイトセンターに撤退すらしている)、いったん決めたことを正す勇気を持たなかったり(政府は避難区域外で高濃度に汚染された浪江町や飯舘村の人々を長期に渡って放っておいた)、制度に縛られ、立ちすくんでいるように見える。
緊急時にある程度の混乱は避けられないものだから、限られた時間、限られた情報でしなければならなかった判断のミスならまだ理解はできる(ミスが分かればすぐ改めればいいわけだ)。でもこれらはそういう救いのあるミスというより、非常事態に際して個人も組織も本能的に俊敏に反応しない(できない)体質が骨がらみになった、この国の人とシステムのもっと深い危機であるような気がする。
3冊それぞれに興味深く、教えられるところもたくさんあったけど、1冊だけと言われたら、個人の視点で貫かれノンフィクションとしての出来もいい『メルトダウン』をお勧めする。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.


