4321【ポール・オースター】
4321
| 書籍名 | 4321 |
|---|---|
| 著者名 | ポール・オースター |
| 出版社 | 新潮社(800p) |
| 発刊日 | 2024.11.30 |
| 希望小売価格 | 7,150円 |
| 書評日 | 2025.04.18 |
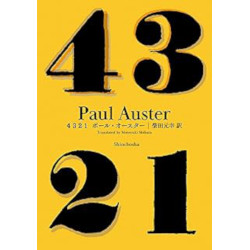
2024年に亡くなった作家ポール・オースターが2017年に発表した長編小説。帯の惹句に「作家人生の集大成的超大作」とあるように、これまでも彼の小説でさまざまに言及されてきた自伝的な要素がふんだんに散りばめられている。といっても、「自伝的」という言葉から連想される、オーソドックスに自らの過去を振り返った作品ではない。ひと言で言えば少年の成長物語なのだが、日本語版(柴田元幸訳)で大判の上下2段組み800ページという大作の構成に壮大な、ある仕掛けがほどこされている。
全体が四つのパートに分かれていて、章ごとに時間のずれはありつつ四つの物語が同時進行する。どのパートも主人公は同一人物で、アーチー・ファーガソンというポール・オースターその人を思わせる少年。ニューヨークに隣接するニュージャージー州で生まれ育った中産階級のユダヤ系3世、という設定は作家自身の経歴と同じだ。でも成長の過程で、人生にはいくつもの分かれ道がある。例えば両親の死や離婚。それによって経済的な環境が変わるし、親が再婚すれば親戚関係も変わってくる。どの学校に入るかで、どんな友人や異性と出会うかも違う。少年が必ずしも自分で選択できるわけではないいくつもの岐路で、どの道が選ばれたかによって人生は決まってくる。そのとき別の道が選ばれれば、また別の人生がありえたはずだ。
「いまあるこの世界は世界のごく一部分にすぎない。なぜなら現実とは起こりえたけれど起こらなかったものからも成っているのであって、どの道もほかの道に較べていいとか悪いとかいうことはいっさいないのだ。一つしかない身体で生きることの辛さは、どの瞬間にも一つの道にしかいられないことである。ほかの道にいたることもありえて、いまごろまったく違う場所へ向かって進んでいたかもしれないのに」
ふつうの物語では、主人公のたどったひとつの道しか描かれない。でもこの本でオースターは、主人公のアーチーに四つの身体を与えた。小説のなかの現実であるひとつの身体と、ありえたかもしれない三つの身体。その四つの青春を、物語ることにかけて極めつきの巧者である(あった)著者は自在に紡ぎだす。オースター自身が、書くことそのものを楽しんでいるのが、見事な翻訳を通して伝わってくる。彼と同い年の小生、それをたっぷり楽しんだ。
晩年に至ってこんな実験的な手法を採用したことも驚きだが、ではポール・オースターはそれによって何を語ろうとしたのだろうか。僕がこの大長編を読み終えての感想は、彼はひとつの時代と場所を多角的に、いくつもの視点や環境によってその全体像を語ろうとしたのだ、というものだった。時代とは、1960年代。場所とは、ニューヨーク(と隣接するニュージャージー)。
四つのバージョンのうちのひとつでは、家電販売業を営んで成功した父親は、彼の兄弟の裏切りによって店を畳み、経済的には苦しい環境でアーチーは成長する。別のバージョンでは、店の火事で父親は亡くなってしまう。また別のバージョンでは、父親の店は成功し「郊外小売業の王」と呼ばれるようになるのだが、アーチーは父を「成金俗物団の一員」と軽蔑し、やがて両親は離婚することになる。
離婚した母親は、かつて勤めていた写真館の息子たちと──ひとつのバージョンでは兄と、別のバージョンでは弟と──再婚する。兄弟の親族には音楽評論のジャーナリストや大学で教えている知的な伯父伯母がいて、アーチーは大きな知的刺激を受ける。
アーチー自身も、あるバージョンでは高校時代から高校バスケット・ゲームの記事を新聞に書き始める。別のバージョンでは小説を書き始める。また別のバージョンでは映画評論を書きはじめる。アーチーにはエイミーという幼馴染の恋人がいるのだが、あるバージョンでは彼女の父親(写真館の息子)が自分の母親と再婚して、ふたりは姉弟の関係になってしまい、アーチーは心に大きな葛藤をかかえることになる。また別のバージョンでは、アーチーは自分がゲイかもしれないことに気づき、大学に行かずパリへと旅立つ。
そんなふうに、さまざまな環境におかれたアーチーの生き方はいろんな相貌を見せるのだが、ただひとつ共通しているのはアーチーが、ものを書く人間になろうとしていることだ。なかで、物語の途中で結局は死んでしまう三つの「ありえたかもしれない人生」でなく、残った一つである小説中の現実の人生で、アーチーが高校時代から書き始めた「靴底の友」(Sole Mates──Soul Matesと掛詞になっている)という小説が詳しく記述される。主人公にとって小説は天職だったということだろう。
ニュージャージーの小さな町で育ったアーチーは、郊外の平均的市民が住むそこを「世界中どこよりもいたくない場所」と呼んで、週末にはニューヨークに住むエイミーの家を訪れ、「濃密さ、巨大さ、複雑さ」に象徴されるニューヨークに憧れる。大学はニューヨークに行きたいと熱望する。この作品は、これまでのポール・オースターの小説に比べてセンテンスが長いと感じられるのだが、その典型のようなワン・センテンスを(余りに長いので途中省略して)引用してみよう。
「窓の外に目をやればそこにはニュージャージー北部の陰惨で荒んでいく一方の風景が広がり、沼や川や鉄の撥ね橋の背景には崩れかけた煉瓦の建物が古き資本主義の残滓という趣で点在し、まだ使われているのもあれば廃墟と化したものもあり、どちらにしろおそろしく醜く、……やがて列車を降りてフェリーに乗り換えると、天気が一応まともであればデッキに立って顔に風を浴び足の裏にエンジンの振動を感じ、頭上ではカモメが旋回して、と、考えて見れば何とも平凡な話で、月曜から金曜まで毎朝何千人もの通勤客がやっている移動にすぎないわけだが今日は土曜日なのであり、十五歳のファーガソンにとってはこうやってロウアー・マンハッタンへと移動することが掛け値なしのロマンスであって、自分が現在やりうる良きことすべてがここにあった」
物語の前半はニュージャージー、中盤からは、あるバージョンでアーチーはコロンビア大学に進んで、ニューヨークを中心に物語は進行する。ことにコロンビア大学周辺の学生街の描写は、なじみがあるからだろう親しげで、なんともリアルだ(オースターはコロンビア大学出身)。
そんなニューヨークでの生活の遠景にはカリフォルニアとパリがある。あるバージョンで、恋人エイミーはカリフォルニアに去る。サンフランシスコに行ったアーチーは、その地を「汚れも不完全さも許容しない都市計画者が設計した、疑似都会・疑似郊外の辺境。そのせいで町は退屈で人工的に思えた」と感ずる。一方、別のバージョンでアーチーはパリに行くが、そこは「アメリカでないもののすべての中心地」で「最良の詩人、最良の小説家、最良の映像作家、最良の哲学者、最良の美術館、最良の食べ物」があると思う。
1960年代にニューヨークにいた十代の青年にとってカリフォルニアは遠く、パリともども自分の住む環境とは全く違う異国と感じられたのだろう。
その1960年代はアーチーにとって、十代から二十代前半に当たる。13歳のときにジョン・F・ケネディが大統領選に出馬して以来、アーチーはケネディ兄弟を期待を込めて応援してきた。そしてケネディ暗殺。ベトナムには多くの兵士が送り込まれ、戦争が激化する。キング牧師暗殺を契機に全米で人種暴動が起こる。アーチーが大学(あるバージョンではコロンビア大学、別のバージョンではニュージャージーのプリンストン大学)に入ったときには反戦運動が盛り上がっていた。アーチーは反戦運動に共鳴しつつも大学新聞の記者となって距離を取るが、名門女子大バーナードに進学したエイミーは運動に参加して過激化する。
そんな激動の時代にアーチーとエイミーがどんな大学生活を送ったか。二人の愛と別れを絡めながら、ニューヨークの反戦運動の中心だったコロンビア大学のなりゆきが描かれる。学内でのアフリカ系反戦グループとの共闘や対立。運動方針をめぐる対立から武闘派グループ「ウェザーメン」が生まれることなど、小生も同時期に東京で大学生活を送っていたから、共通するところも異なるところも、なるほどそうだったのかと思いながら引き込まれた。
アーチーは思う。「バリケードで戦う気はないが、戦っている連中を応援はする。そして部屋に帰って本の続きを書く。/この立場がどれだけ危なっかしいかはわかっていた。その傲慢さ、自分勝手さ、芸術至上式思考の限界。けれどこの論法にしがみついていないことには、本などもはや必要でない世界を措定する反論に屈してしまうだろう。そして本を書く営みにとって、世界が燃えている──そして自分も一緒になって燃えている──一年ほど重要な瞬間があるだろうか」
もうひとつ興味深かったのは、アーチーが作者と同じ東欧から移住したユダヤ系3世という設定。アーチーの伯父伯母や親の結婚相手の親戚に知的職業に就いている人間が多く、アーチーにさまざまな小説や映画を勧めて大きな知的刺激を与えてくれる。ユダヤ・コミュニティ(都市部の中産階級の、だろうが)では大学へ行くのは当然、できれば大学院に進むのがよいという言葉も出てくる。そんな環境が作家志望であるアーチーを産む土壌となっている。作中に出て来る小説や映画の題名は、小生も同世代だから共通するものがいくつもある(なかでも映画『長距離ランナーの孤独』をめぐる会話には、そうそう、そうだよな、と頷いてしまった)。
さらに驚いたのは宗教に関して。アーチーの家庭も宗教に熱心でないとはいえ、ユダヤ・コミュニティで生きる上でユダヤ教の規範は、例えば日本の平均的な家庭での仏教の規範よりずっと大きいのだろう。あるバージョンで父親の理不尽な死を経験したアーチーは、神はいるのかという疑問に捉われる。それを検証するため、進学した私立高校でアーチーは学業を徹底的にさぼって落第点を取り、もし神がいるならこんな自分を罰するはずだ、と考える。神に向かって「どうか姿を現してください」と何カ月も祈り続け、最終的に、神はいない、と結論づける。高校生らしい拙いやり方ではあるけれど、幼いなりに神はいるのかと真剣に悩む。主人公にそのような経験をさせたということは、オースター、あるいは彼の周囲のコミュニティのなかで、そのようなことがありうることの反映かもしれない。
小生は東京近郊、オースターはニューヨーク近郊と育った場所は違うが、同い年、同じ時代を生きてきた者として、深い共感をもって読み終えた。こういうのを読書の愉楽というんだろうな。もう彼の新作を読めないのが悲しい。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





