夢みる教養【小平麻衣子】
夢みる教養
| 書籍名 | 夢みる教養 |
|---|---|
| 著者名 | 小平麻衣子 |
| 出版社 | 河出書房新社(208p) |
| 発刊日 | 2016.10.05 |
| 希望小売価格 | 1,620円 |
| 書評日 | 2017.01.17 |
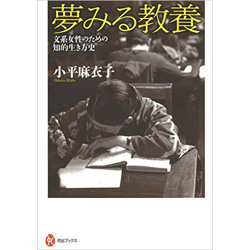
「夢みる教養」というタイトルと「女はいつも文化のお客様」という帯のキャッチコピーが気になって本書を手にした。しかし、それらの柔らかな表現とは裏腹に著者小平の厳しい視点の分析が繰り広げられている。大正から現代に至る期間で、女性が学問を志すことへの制約と男たちの排他的な言説が女性の学問意欲をいかに削いできたかを示し、その結果女性にとって「教養=実現しない夢」となってしまってきた歴史を緻密に描き出している。小平は昭和43年(1968年)生れ、慶應大学文学部に学び、現在同校文学部教授。近代文学におけるジェンダーについての研究をしてきたので、本書はまさに彼女の専門のど真ん中と言える。
小平は「教養」とは、深い知識を前提とした物事に対する理解力や創造力であり、古今東西の文学・宗教・哲学などの幅広い読書を通して、自己の人格を高めることとしている。しかし、「役に立たないが生活を豊かにする知識」とか「だれでも知っているべき一般常識」といった混沌とした「教養」の概念がまん延していることを証左として、それぞれの時代に求められてきた女性像に対応して、都合良く使われて来た言葉であったことを指摘している。同時に、「NHKの朝ドラ」で知的女性たちの人生を成功とか進歩という表現でドラマが作られていることに批判的な目を向けている。それは、少数の成功者を語ることで、一般の女性たちの苦労が隠され、解決すべき問題が明らかにならなくなってしまうという主張である。
まず、戦前の学制が持っていた制度的な問題点を取り上げている。大正時代に教養派と呼ばれた夏目漱石門下の和辻哲郎に代表される人達は「教養」とは自立した人間だけが持てる統合的な人格と考えていたが、それは、旧制高等学校の教育の理念そのものであった。しかし、旧制高等学校の入学資格は男子であること、帝大の入学前提は旧制高校卒業であることから、必然的に女子が最高学府で学ぶことは旧学制において不可能だったという事実を指摘している。その結果、1920年代から30年代に高等女学校から専門学校におけるカリキュラムを見ると家政に重点を置いたものであり、その教育結果を生かして社会において意見を表明できる職業は作家ぐらいでしかなく、女性の教養の一つに広義の文学が大きな位置を占めていたのもこうした状況があるとしている。
次に、大正末期から戦前までの期間の女性の生き方や教育について、吉屋信子の「地の果まで」(1920年)と、野上弥生子の「真知子」(1929年)という二つの小説を詳細に読み込んでその時代背景を明らかにするという試みをしている。これらの主人公たちは、学ぶことの前向きさは裕福な家庭環境からも許されてはいたものの、その教育成果を社会的に位置づけることが出来ず、女性が真面目で真剣に学べば学ぶほど「教養を夢にとどめてしまう」社会構造や家族観が描かれている。まさに、小平の研究成果そのものといえる。
ただ、読み進んでいくと、こうした小説からの時代分析という手法の限界も感じてしまうのだが、この二人の女性作家の体験エピソードも紹介されていて、それらの方が問題提起としてはシンプルで判りやすい。それは、吉屋信子が高等女学校に在籍時に、新渡戸稲造から「あなた方は良妻賢母となる前に、一人の良い人間とならなくては困る。教育とはまず良き人間になるために学ぶことです」との話を聞き、彼女は「神の声を聞くように恍惚とした」という。しかし、その翌日、教頭が生徒たちを集めて「新渡戸博士は外国婦人と結婚している特殊な人だから、言う事を真に受けてはいけない。」と語ったという話。
同様に、作家として活躍していた野上弥生子は1936年に刊行された「学生と教養」で谷川徹三はじめ15名の評論家、大学教授、哲学者がそれぞれの分野で教養について記述しているのだが、その中で唯一の女性として野上が文章を書いている。「一つの注文」と題されたその文章はイタリアに留学する息子に向けたもので、「母さんは、」という書き出しで始まっている。野上が自らその題材を選択したのか、依頼されたのかは別としても、この文章に対して小平は、「賢明な弥生子がそれを選んだとしたら、なおさら、女性の教養は母親としてしか世間に許容されないということなのである」と厳しい見方をしている。これらのエピソードは人生の選択肢を与えられることなく、良妻賢母を強制される時代を象徴している。
男性こそ、最大の敵とでも言うような時代状況も小平は熱く語っている。昭和12年(1937年)に創刊された「新女苑」という部数も少なく知名度も低いが、高等女学校在校・卒業生の愛読雑誌第一位だった雑誌を小平は取り上げている。この雑誌には「教養の頁」というコラムがあり、各種の仕事に従事している女性たちのインタビューなどを掲載し、働くことに金銭以上の価値が有る事を伝えるとともに、人間としての成長と労働を結びつけて新たな女性の「教養」に対する考え方をリードしていたという先鋭的なものである。
一方、この雑誌には読者投稿欄があり、多くの女性たちがペンネームで文章を投稿していたが、それらの批評を担当していた川端康成たちの論調を小平は分析してみせる。男性評者達は、妻や母に関する内容の投稿には高い評価を与えている一方、投稿している女性たちの文章そのものについては趣味的・素人芸的として、けして高い評価を与えなかったということから、女性が「教養」に真面目に向き合おうとすると「素人として無心に取り組んでいるのが得難い美しさだ」と褒め殺しにされ、職業化を阻止されたと小平は語る。
また小平は、太宰治が1939年に発表した「女生徒」という小説と太宰の一読者であった有明淑(しず)の書いた日記とを全文比較して、その酷似性とこの小説の中で太宰が新たに作り出したエピソードが皆無であることを明らかにしている。本書で比較されている文章を見ると現在で言えば盗作と言われるに違いない程似ている事に驚かされる。加えて、川端康成はこの小説を激賞し「こうした話は女には書けない」とまで言い放ったことに対して、「男性作家たちの邪悪な共同体」と名付けて小平は憤っている。
戦時中、女性は家庭に入るか働くかの二者択一を迫られていく。国策としては女性の職業進出を奨励しつつ、1941年には「人口政策要綱」で今後十年間に結婚年齢を三才下げ、一夫婦の出産数を平均五名とすることを目標とした。二つの国家政策を両立させる手段が政策として提示されている訳ではない。こうした戦中を乗り越え、戦後のエピソードを本書からつまみ食いしてみるとこんな形になる。
1960年代、女性の大学進学率は1955年に5%だったものが1960年代末には20%近くに上昇していった時代、1962年のミス エールフランスに選ばれた女性が早稲田大学の国文科に在学していた学生で、そんな浮っついた奴は大学に来るなということで、早稲田大学の暉峻康隆と慶応大学の池田弥三郎の対談から「女子大生亡国論」という言葉が生まれた。
1970年代は、高度経済成長期で経済的利益を生み出す労働と、労働の再生産にあたる「家事・出産・育児」を男女で分担した方が効率的と考えられ、この結果、専業主婦率が史上最高となり、必然的に、女性が大学で学ぶ教養は「夢」に置き換えられていった。同時に大学のみならずカルチャーセンターが大きく成長した。1980年の朝日カルチャーセンターの会員数5万人のうち女性が76%という数字にそれが示されている。教養はカルチャーとなり女性は教養のお客様としてのみ文化と経済に貢献することとなった結果、「教養とは教育から選抜をマイナスしたもの」という言葉も何やら正しそうに思えてくる時代ということか。
こうして、歴史的に見た「教養」を核にした形で、女性の立場を見た場合、建前と本音の社会構造は依然として存在しているという主張や、教養をめぐる抑圧的な構造は表面的にみえる事象を変えながら、現在に至るまで機能し続けているという小平の主張は間違ってはいないだろう。ただ、抑圧論は過去の男女差別の歴史においてその存在を否定するものではないが、現在における女性の仕事・教養論で言えば男女問わず抱えている共通の問題として理解すべきではないのかと思うのだ。一方、女性の立場からすると、社会の悪さはその社会の中心に男がいる限り続くことになるのも事実であろう。ただ、働くという観点でいうと男もけして自由な職業選択をしている訳ではないし、学問・教養の成果としての専門性を生かした「職」を選べている訳でもない。たまたま入社出来た「会社」で働いて金を手にしているという悲しい事実なのである。 (内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





