吉行淳之介エッセイ・コレクション【吉行淳之介】
吉行淳之介エッセイ・コレクション
| 書籍名 | 吉行淳之介エッセイ・コレクション |
|---|---|
| 著者名 | 吉行淳之介 |
| 出版社 | ちくま文庫(322~328p) |
| 発刊日 | 2004.2.10~ |
| 希望小売価格 | 各780円+税 |
| 書評日等 | - |
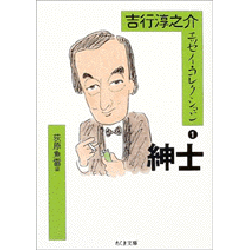
ちくま文庫のエッセイ・シリーズが憎い。殿山泰司の「三文役者」シリーズ(7巻)に始まって、田中小実昌エッセイ・コレクション(6巻)、色川武大・阿佐田哲也エッセイズ(3巻)とつづき、今度は吉行淳之介(4巻)ときた。これを書いている5月1日現在、全4巻のうち「紳士」「男と女」「作家」の3冊が出ている。
いずれも、私がかつてハマッたことのある書き手たち。書店でぱらぱらページをめくっていると、懐かしいタイトルがあり、もちろん読んでいないものもあり、だからついつい買ってしまう。殿山泰司を除いて新しく編集しなおされているから、いままで気がつかなかった発見もある。
吉行淳之介を片っ端から読んだのは30歳になったばかりの頃だったから、もう25年以上前のこと。
ちょうど「夕暮まで」が中年男と若い女の不倫小説として話題になっていて、「夕暮れ族」なる流行語が世間をにぎわしていた。そこから入って「驟雨」や「街の底で」(これを読んだとき、見慣れた街の風景が別のものに見えたのを今でも覚えている)や「暗室」に戻り、同時にしゃれたエッセイや「アサヒ芸能」連載の対談を楽しみにしていた。
戦後生まれの私たちより2世代上になる戦中派の吉行の書くものは、私たちにとって「大人」になるためのテキスト、といった一面を持っていた。30歳になるかならないかの当時、こちらにはまだ学生時代の観念的な物言いのしっぽが残っていたから、吉行の文章が身に沁みた。
「原点、ラジカル、会合をもつ、現時点……いずれも、私が好まないことばである。ことばの身振りが大きい。ということは、演説口調につながるのであって、事実、学生活動家が頻繁にこの種のことばを使う。語尾を伸ばすような彼らの口調は、戦前の軍国主義者に酷似していて、いかにも権力志向の持ち主と見える」(「ことばの感覚」)
身に覚えのあることだから、「軍国主義者」とか「権力志向」などと言われては反発もしてみるが、なにしろ吉行淳之介の小説やエッセイにハマッている身だから、結局のところ納得しないわけにいかない。その一方で、吉本隆明なんかを読みつづけてもいたわけで、そっちのしっぽは未だに残ったままだけれど、同時に30代になった自分の精神のフィールドに、吉行淳之介は確かにある場所を占めることになった。
読んでいて、思い出した。吉行淳之介を「大人だな」と思ったのは、好きだった梶井基次郎についてのこんな文章を読んだからでもあった。
「私は、梶井基次郎の文章は日本語の手本のようなものと思っているが、その梶井の代表作と見なされる「檸檬」は、私だったら「れもん」と書く。このむつかしい文字に、はじめてお目にかかったときには、なにか禍々しい気分を受けた。作品の内容は、八百屋で売っている一個のレモンが、しだいに爆弾のようなものに変化してゆくことを書いてあって、したがって禍々しい感じを与えるのが作者の狙いかもしれないが、やはり「檸檬」となると行き過ぎとおもえる」(「わたしの文章作法」)
「檸檬」という言葉に、ある種のダンディズムや青春の気取りを感ずるのが、梶井ファンの大方の読み方だろう。私自身もそうだった。それを「禍々しい気分」というのは、「原点」や「ラジカル」という言葉に拒否反応を示すのと、ちょうど同じ場所から発された言葉にちがいない。
ほかにも、何十年かぶりに読みなおして、いくつかのことに気づいた。
吉行淳之介は個性的な文体を持つと言われているし、自分もそう思っていたけれど、こんど読み返して感じたのは、作家のオリジナルという意味での個性ではなく、むしろオリジナルな個性を消そうとする意志に支えられた透明感という「個性」を湛えていることだ。
このちくま文庫のエッセイ・シリーズの書き手たち、殿山泰司、田中小実昌、色川武大の世界は、いずれもけものの住処に迷いこんだような、彼らにしかない強烈な匂いを発している。それらに比べると、吉行の文章は、さらさらと口のなかで溶ける蟹の刺身のような、あるいは深い谷から湧く清水のような、気づくか気づかないかの、ほのかな甘さと香りを感じさせる……と思っていたら、彼自身がそのように書いていた。
「私は水のような文章が書きたい。水道の水では駄目で、あれはカルキのにおいがする。水は無色透明無臭だが、無味ではない。味ともいえない微妙な味がある。私はその日の気分や体調によって、飲みたいものはさまざまであって、飲めばうまいとおもうのだが、結局は水が一番好きである」(「水のような」)
そう言われてみれば、「水」というのは吉行淳之介を理解するための重要なキーワードだった。
先ほども触れたけれど、僕たちの世代には彼の書くものが「大人」のためのテキストのように見えていた。酒、女、ギャンブルといった「遊び」を楽しむ姿勢は、それ以前の「戦後派」の作家たち(野間宏、島尾敏雄、大岡昇平ら)に比べて、いわばノンポリのように思えていた。
でもこんど読んで感じたのは、考えてみれば当たり前のことだけれど、彼の「遊び」に耽溺する姿それ自体が深く戦争の影を負っているということだ。昭和20年に20歳そこそこだった吉行が、どのような精神の態度で戦争をくぐり抜けたか、その体験が戦後、彼にアプレ・ゲールとしてのどんな姿勢を強いたかを、吉行は繰り返し語っている。
「原点」とか「檸檬」という言葉に対する彼の違和感の表明と、吉行が「遊び」に没入することとは、同じ精神の別々の現れにほかならない。それを吉行の「戦争体験」と呼んでいいのだろう。
そんな作家の精神の遍歴を改めて明らかにするのが、このコレクションを編んだ編者(荻原魚雷)の狙いのひとつかもしれない。もっとも、その分だけ、吉行の「遊び」にはページが割かれていない。ファンとしては、そんな吉行淳之介ももっと読んでみたい。間もなく出る第4巻「トーク」を楽しみにしよう。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





