雪沼とその周辺/魔法の石板【堀江敏幸】
雪沼とその周辺/魔法の石板
小説とエッセーがコインの表裏のように支えあう
| 書籍名 | 雪沼とその周辺/魔法の石板 |
|---|---|
| 著者名 | 堀江敏幸 |
| 出版社 | 新潮社(202p)/青土社(296p) |
| 発刊日 | 2003.11.25/2003.11.20 |
| 希望小売価格 | 1400円/2200円 |
| 書評日等 | - |
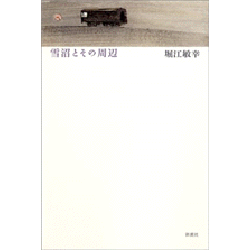
堀江敏幸の新刊が2冊、ほぼ同時に書店に並んでいた。一冊は小説で、もう一冊は長編エッセー。「魔法の石板」と題されたエッセーのほうには「ジョルジュ・ペロスの方へ」とサブタイトルがついている。
堀江敏幸は「熊の敷石」で芥川賞を受けているから、一般には小説家というほうが通りがいいのかもしれない。けれども僕にとっては、処女作の「郊外へ」から「おぱらばん」「子午線を求めて」へと至る、フランスの現代作家と作品をめぐりながら、現地での体験と思索をちりばめた魅力的なエッセー群の書き手としての印象が圧倒的に強い。
「熊の敷石」も、フィクション的な要素を取り込みつつも、それらの延長線上にあるエッセーとして僕は読んだ。だから芥川賞と知ったとき、それが賞に値するかどうかではなく、賞を出す側の問題として、えっ、あれが芥川賞なの?と感じたことを覚えている。
堀江にとってそんなジャンル分けはどうでもいいはずだが、その後、彼はフィクションとして読める「いつか王子駅で」を発表した。「雪沼とその周辺/魔法の石板」はその流れの上にあり、これは完全なフィクションと言っていいものだ。
一方、「魔法の石板」は、これまで文学論とも体験とも思索ともつかない(そこがいい)、筆のおもむくままに任せたようなエッセーを書いてきた堀江にしては珍しく、明確なテーマと構成をもったものになっている。
この2冊を一緒に取り上げてみようと思ったのは、2冊が同時に出たことばかりでなく、一方がもう一方の注になり、小説とエッセーがコインの表裏のように互いを支えあっていると感じられたからだ。
「雪沼とその周辺/魔法の石板」は、雪沼という架空の土地に住む何人かの住民を主人公に、山間の小さな町に日々を送る彼らのドラマらしいドラマもない日常の光景を、ある距離をもって切り取った連作だ。
冒頭に置かれた「スタンス・ドット」(川端康成文学賞受賞作)は、ボーリング場が廃業する最後の数時間の出来事(ともいえない出来事)を、オーナーの独白のかたちで描いたもの。主人公のオーナーは、ピンがボールにはじかれた瞬間に、ある時代遅れのモデルだけがかなでる「レーンの音楽」に魅了され、その数レーンの小さなモデルを店に据えてささやかに営業していたのだ。
ゲームをしにではなくトイレを借りに現れた最後の客のカップルと、ちょっとしたやりとりから一緒にゲームを楽しむことになったオーナーは、彼にボーリングの魅力を教えてくれたハイオクさんを思い出す。
ハイオクさんは元プロボウラーだったが、勝負がかかったときにも、アプローチに立ったときの自分の「立ち位置」を決して変えることをしなかった(ふつうは第一投でのピンの残り具合によって、床の「スタンス・ドット」を目印に自分の立ち位置を変える)。
「ただひとつ確かだったのは、ハイオクさんの投げた球だけが、他と異なる音色でピンをはじく、ということだ。……ほんわりして、甘くて、攻撃的な匂いがまったくない、胎児の耳に響いてくる母親の心音のような音。彼(主人公)はなんどかその音と立ち位置の秘密をさぐろうとしたのだが、スタンス・ドットは、立ち位置を変えるためのものではなくて、それを変えないためのものなんだよ、わたしにとってはね、と笑って答えなかった」
カップルに勧められて、オーナーは店じまいの前の最後の一投を投げることになり、学生時代から変わることのなかった「立ち位置」に立ち、「右からふたつめの印に右足のつま先を」合わせる。
「しかし本当にこの立ち位置でよかったのだろうか。あの音を一度も鳴らしえなかったこの位置でよかったのだろうか」
主人公がそう過去を振りかえり、迷うところで小説は終わっている。
この一編には、時代遅れのボーリング・モデルとかピンボール機とか、かつての村上春樹ふうな小道具が登場してきて、あれあれと思うのだが、連作が進むにつれ、そんな70年代ふうノスタルジーは影をひそめる。そこにあるのはノスタルジックな空気ではなく、かといって今ふうにクールな男と女の話でもない。
そこから漂ってくるのは、おだやかな日常のなかから立ちあがる孤独の匂いとでも言ったらいいだろうか。そんな彼らの生の核とでも呼べそうなものが、「レーンの音楽」とか、身体の変調によるわずかな傾きの自覚とか、雪空に舞う凧の、雪の白に埋没しない手漉きの紙の白さとか、日々のなかのささやかな、誰もが思い当たる微妙な感覚に仮託されている。
ところでこの「立ち位置」という言葉は、もう1冊の「魔法の石板」にも使われている。いわば2冊をつなぐキーワードといっていい。
「魔法の石板」は、ジョルジュ・ペロスという1978年に亡くなった現代フランスの「詩人でも小説家でもエッセイストでも戯曲家でもない」存在をめぐるエッセー。彼は「パピエ・コレ(貼り紙)」という3冊のアフォリズム集と、「ありきたりの人生」など2冊の詩集を残した。
どれも日本語に翻訳されてはいないから、専門家以外、この国で彼を知る人はほとんどないだろう。そんなマイナーな作家について1冊の本を書いてしまうところが、またいかにも堀江らしい。
パリの下町に育ったペロスは、長じて役者としてコメディ・フランセーズの一員に迎え入れられるのだが、自らその地位を投げすててブルターニュに移り住む。戯曲の下読みと書評でかろうじて生計を立てながら、後に「パピエ・コレ」にまとめられる覚え書きを書きつづけ、いったんはガリマール社から出版される話がまとまるのだが、それも断ってしまう。
その覚え書きは、チャンスを捨て自分を消そう消そうとばかりする自らの生き方や、書くことと考えること、孤独と友情などについての断片によって構成されている。そんなペロスを、堀江はこんなふうに描写している。
「ジョルジュを苦しめてやまない、またそれゆえに彼を豊かに揺さぶるあの孤独は、たったひとりでは成立しない。周囲に誰かがいて、彼らとともにつくりあげる存在の磁場のなかでしか、本当の孤独は熟成されないのだ」
「家庭のなかでの孤独を求め、必要としていたペロス。友情の網の目のなかで砂漠のような孤独を渇望したペロス」
「闘いは「ヴェルダン(第1次大戦の激戦地)ではなく、日常の、日から日への塹壕のなかで」続行されるべきなのである」
「「ありきたり」の日々の、身近な他者にたいして口を開かなければならない日々の模様が、言葉の流れに「ほんの少し」――そしてその「ほんの少し」が決定的な――「生きられた」厚みを与えている」
「あたりまえの、ありきたりの人間であることのなんというむずかしさ」
これはほとんどそのまま、「雪沼とその周辺/魔法の石板」への見事な注になっていないだろうか。「雪沼とその周辺/魔法の石板」は、堀江がペロスを読み、彼について考えることによって受け取った生の「立ち位置」を、フィクションというかたちで結晶させたものといえるのではないか。
そう考えると、この小説が架空の土地を舞台にしていることも、人々の日常を描きながら生活臭がまったくないことも、抽象的な言葉遣いはしていないにもかかわらずどこか観念的な気配がただよっていることも、よく理解できる。
僕はこの2冊を読みながら、小説を読んでいるとかエッセーを読んでいると意識したことはなかった。ただ堀江敏幸の文章を読んでいるとのみ感じていた。
彼の硬質でいながら柔らかい、センチメンタルなところのまったくない文章を読んでいるときの気持ちをなにに喩えたらいいのか、よく分からない。それは、酔っているというのではない。覚醒しているというのともちがう。その両方であり、両方でない。
例えば言葉でないものなら、ジョン・コルトレーンのバラードを聴いているときのような。あるいはホウ・シャオシェンの映画を見ているときのような……。その中心に硬い核があるのを常に感じながら、その核が静かで優しいものにくるまれている、そんな音や映像に身をゆだねているときの快感に近い。
堀江は「魔法の石板」のなかで、ある詩人がペロスに出会って「「近しいひと」をまえにしている」という感情をもったと書いている。僕もまた堀江に対して「近しいひと」という感情を抱く(むろん、才能の多寡は別として)。それが、僕が堀江敏幸を読みつづける最大の理由にちがいない。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





