武器としての「資本論」【白井 聡】
武器としての「資本論」
| 書籍名 | 武器としての「資本論」 |
|---|---|
| 著者名 | 白井 聡 |
| 出版社 | 東洋経済新報社(292p) |
| 発刊日 | 2020.04.23 |
| 希望小売価格 | 1,760円 |
| 書評日 | 2020.07.17 |
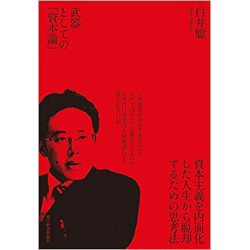
「武器としての『資本論』」というタイトルを見たとき、「武器」とは何のための武器なんだろう、という疑問が湧いた。少しでもマルクスをかじったことのある小生のような団塊の世代なら、当然のように「革命」とか「資本主義を倒す」ための武器といった言葉が思い浮かぶ。でもそうしたことを、いまこの国でほとんどリアリティをもって語ることはできない。笑われるのがオチだろう。ではこの本が、買い手の目を引くためタイトルに選んだ「武器」とは何のためか。白井聡は、「この世の中を生きのびるための武器」なんだと言う。われわれはなぜ毎日、満員電車に揺られて会社に行かなければならないのか。なぜみんなが苦しまざるをえない状態にありながら、その苦しみを甘受して生きているのか。『資本論』はそういうことに答えてくれるのだという。
いま、マルクスなんて時代遅れの代物だ、というのがおおよその一致する見方だろう。確かに社会主義を標榜する国家の崩壊や堕落ぶりを見れば、それもうなずける。でもマルクス、特に『資本論』は現実の政治や国家から一歩も二歩も下がって、資本主義というシステムを批判的に分析した書物。革命論としてでなく、資本主義批判の学としてマルクスをもう一度読み直すと、貧富の差が極端になり、差別と分断が暴力的な様相を呈する今の世界を読み解くヒントが得られるかもしれない。マルクスが19世紀ヨーロッパの資本主義を分析した手法で現代を、特に1980年代以降の「新自由主義」とよばれる現在を分析したらどう見えるのか。これが本書の「裏テーマ」だという。
この本は「『資本論』入門」と謳っているから、『資本論』からいくつかのキーワードを取り上げ、それを解説するスタイルを採っている。「商品」「包摂」「剰余価値」「本源的蓄積」「階級闘争」といった言葉。といっても小生が『資本論』第1巻(だけ)をなんとか読んだ半世紀前の古典左翼的な解釈でなく、その後のさまざまな研究成果を踏まえたものになっているようだ。
本書がその分析を「裏テーマ」とする「新自由主義」とは1980年代以降の「小さな政府」「民営化」「規制緩和」「競争原理」といった言葉に象徴される、現在までつづく資本主義のありかたを指す。それ以前、第二次大戦から1970年代まで(日本で言えば戦後から高度経済成長の時代)を白井は「フォーディズム」とくくっている。フォード社がベルトコンベアを導入して自動車を大量生産するシステムから来た言葉。大量生産した車は、少数の金持ちだけでなく、たくさんの普通の人びとに買ってもらわなければならない。そこでフォード社(に代表される資本家)は、車(商品)の価格を下げると同時に労働者の給料をアップして「労働者を消費者に変えようとした」。その結果、労働者の生活は豊かになり社会保障制度も整備されて、先進諸国では大衆消費社会が出現した。「労働者階級を富裕化して中産階級化するということが20世紀後半の資本主義の課題となり、相当程度実現された」ことになる。
でもこの流れは1980年代に逆流を始める。資本家は政府の介入を最小限にした市場原理主義で企業が自由に活動できる範囲を広げ、規制緩和などを通じて労働分配率を下げ、新たな剰余価値を生みだそうとした。日本でいえば「働き方改革」による非正規労働者の増大や、富むのも貧困も自己責任という考え方の浸透で90年代以降、格差が急速に拡大した。「無階級社会になりつつあった日本が、新自由主義化の進行と同時に再び階級社会化していった」ことになる。無論これは日本だけでなく、先進資本主義国に共通の現象だ。白井はデヴィッド・ハーヴェイの言葉を引用して、新自由主義とは「資本家階級からの『上から下へ』の階級闘争」「持たざる者から持つ者への逆の再分配」だと述べている。
彼はまたこの時代を分析するのに「包摂」という言葉を使っている。『資本論』で使われる「包摂」という概念は、労働者が自分の労働力を商品として売ることでしか生きていけないことで資本の下に組み込まれることを指している。生産の目的が商品を売ることによる貨幣の獲得になることを「形式的包摂」、生産過程全体が資本によって組織化されることを「実質的包摂」と呼ぶといった具合に。でも白井は「包摂」という考えを、人間の身体が資本に組み込まれた状態だけでなく、感性や思考といった人間の精神までも資本のもとに組み込まれることに広げて考えている。こうした解釈の背後には、近代というのは、それ以前のように暴力的に身体を罰する刑罰でなく、監禁・監視することで思考や意思を矯正する刑罰に転換し、また教育や軍隊で規律を訓練し内面化させることによって、従順な身体をつくることで人々を支配する時代だ、というミシェル・フーコーの考え方があるんだろう。
では新自由主義を内面化した価値観とはどういうものか? 一言でいえば、「人は資本(会社や仕事)にとって役に立つスキルや力を身につけて、はじめて価値が出てくる」という思想。若い世代には浸透している考え方だろう。それを白井は「資本による魂の『包摂』」と呼ぶ。新自由主義は人々の働き方だけでなく、考え方や感性までも変えてしまった。「このことの方が社会的制度の変化よりも重要なことだったのではないか」
人が内面まで支配されてしまったのなら、「資本に包摂された魂」がそこから脱却する道はあるのか? それがこの本の最後の問いになる。もちろんそれに対する筋道立った回答は用意されていない。でもその端緒として白井が考えるのは「『それはいやだ』と言えるかどうか」。お金になるかどうかのスキルで価値が決まるのでなく、スキル以前の人としての感性に照らして、生きていく上での条件の切り下げや不条理に対し、それは耐えられないとNOの言葉を発することができるかどうか。そんな「感性の再建」から始めなければならない、というのが白井の結論だ。
と、ここまで読んできて、学生時代に読んで今も記憶に残るマルクスの言葉を思い出した。「五感の形成はいままでの全世界史の一つの労作である」(『経済学・哲学草稿』)。五感、つまり視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚といった感性は動物として人間が生まれつき持っているものではあるが、その中身は人間の社会的活動のなかで形成された文化でもある。マルクスの先の言葉の後には、「心配の多い窮乏した人間は、どんなすばらしい演劇にたいしてもまったく感受性をもたない」という文章がつづく。働くことが自分にとって喜ばしいものでなければ(疎外されていれば)、人間は身体も精神も自分自身でなくなってしまう。その状態に歴史上例がないほど深く侵されたのが新自由主義の時代というわけだろう。でも五感は社会的なものであると同時に、自然の一部である人間が生まれつき備えているものでもある。そこを信頼し、人間的自然の底に立ち帰って感性をもう一度磨き上げよう。この本は、そういう呼びかけの書と見えた。
カバーは赤一色、カバーをはがすと表紙は黒一色という装幀が、中身に対応して直截なのがいい。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





