不便ですてきな江戸の町【永井義男】
不便ですてきな江戸の町
| 書籍名 | 不便ですてきな江戸の町 |
|---|---|
| 著者名 | 永井義男 |
| 出版社 | 柏書房(260p) |
| 発刊日 | 2018.04.26 |
| 希望小売価格 | 1,728円 |
| 書評日 | 2018.06.20 |
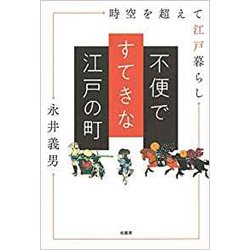
著者紹介には、作家・江戸風俗研究家とある。1997年に「算学奇人伝」で開高健賞の受賞を始め、小説や江戸風俗に関する著作が多く紹介されているものの、永井の著作は初めての読書となった。
本書は現代人がタイムスリップして過去の時代に生きてみるという小説。著者が「仮想実験」と言っているように、かなり挑戦的な試みである。例えば、「東海道中膝栗毛」の場合、十返舎一九という江戸に生きた人間が書いているので、現代人の我々が気になるところであっても彼にとって普通の事象であれば文章として表現されることは無い。一方、現代人が過去の時代で生きるという意味は、歴史的知識を持っているだけでは対応が難しく、過去で生きるための知恵が必要なのだ。だからこそ、現代人の視点で過去を体験するという狙いはスリリングで面白い。
タイムスリップ出来るとしたら、どの時代の何処に行ってみたいかと言う質問に、ほとんどの日本人は「江戸時代の江戸」と答えると著者は言う。確かに鎌倉時代は危険そうだし、平安時代として頭に浮かぶ源氏物語の世界は一握りの貴族の社会であり、庶民の世界に行けばとても生きて行く自信はない。とすると、江戸時代、それも後期となると、自分の七代前のご先祖様の時代と思えば、遠い様な近い様な微妙なところが、面白そうだと思うのは真っ当な感じがする。
この小説の主人公は、大学で日本近世史を専門とした研究者で大学を定年退職後、カルチャー・スクールで地方(じかた)文書を用いて文字の解読や用語の意味を教えているという男、会沢。相方はそのカルチャー・スクールの生徒で30才の大手出版社社員、島辺。この二人が江戸時代の文政八年(1825年)にタイムスリップして五泊六日の旅をする。その時代に行くための準備からこの小説は始まるのだが、最初から、マニアックな匂いがプンプンしている。
準備の初めは服装と髪型。これらは身分にも係わってくるのでなかなか厄介である。まず、二人は蘭方医とその弟子という身分想定で準備に入る。当時、医者は剃髪ということで二人は頭を剃る。次は、言葉遣いである。式亭三馬の戯作「浮世床」などで当時の会話が活写されているが、それは現代の落語の江戸っ子の語り口とは似ても似つかないものだ。従って、江戸っ子という設定は難しいので、地方から江戸に出てきた人をよそおって「ございます」式の丁寧な物言いをすることとする。第三は、当時の金銭を持っていくこと。間違っても文政年間にタイムスリップする人間が天保通宝を使ってはいけないという事だ。第四は、医者として振る舞うので薬を持っていくが、当時の病気のランキングによると一位の眼病から疝気、疱瘡、食傷、歯痛、風邪、瘡毒、痔、癪、とある。当時の漢方では細菌性の眼病を治すのは難しかったこと、疝気・癪などは寄生虫が原因の下腹部の激痛で不衛生の故の病である。これを参考に二人はドラッグストアーに行って目薬やら胃薬、痔の座薬などを買い込む。
こうした準備の状況を描くことで、多少理屈っぽく旅のイメージが読者に伝わってくる。
準備段階でもなかなか読んでいても面白いのだが、旅が始まると、二人を取り巻く人々の描写に加えて、「旅籠と木賃宿の違い」、「江戸の本屋事情」といった興味を惹かれる項目が、浮世絵とともに詳細に解説されている。ただ、江戸の基本情報だけでなく、不便さやエロ系を含めた裏事情を解説しているというのが歴史教科書とは違うところ。
さて、二人の旅で最初に彼らを襲った災難は草鞋による足の痛さである。裸足に慣れない現代人にとっては草鞋は辛い履物だ。当時、街道を行く旅は男であれば一日に十里、女性は八里歩いたといわれている。明け六つ(夜明け)に出立して八つ(午後二時)には次の宿にはいるというのが普通の旅程であるが、我々が靴下とスニーカーで旧街道を歩いたとしても一日40Kmは大変な距離だし、ましてや草鞋で歩くのは至難の業である。
次に二人が驚くのはお歯黒。既婚の女性は全てお歯黒で、吉原の遊女だけは例外的に未婚でもお歯黒をしていたと言われているが、現在の時代劇では既婚役の女優陣もお歯黒はしていない。時代考証のうるさい中で極めて例外的なことである。現代の美的感覚からすると、お歯黒だけは無視するのがTVや映画製作の暗黙の約束になっている。それだけに頭では判っていても現実にお歯黒女性の群れを目の前にするとギョッとするのは仕方がない。
そんな五泊六日の旅の冒頭は旅籠に二泊して、その間大店の旦那と娘の病気を持参した薬で治し、その結果旦那が長屋を無料で使わせてくれる替わりに町の人達を診療して、日常生活を体験しながら、吉原で遊び、侍を投げ飛ばし、大奥の奥女中とも知り合いになるという、些か無理筋を含めて超多忙な六日間が描かれている。
本書で描かれている社会の仕組みの中で再認識したものがいくつかある。その一つが、江戸のライフラインというか、長屋の共用施設として「調理用水を確保する井戸・男女の便所・ゴミ捨て場」が一カ所にまとまっていたというもの。現代人の目からすると不潔感極まりない状況であるものの、糞尿が商品として都市と農村を結び付けるという循環システムが江戸時代には完成していた。この点に関していえば、西欧や中国の都市では糞尿の垂れ流し、撒き散らしの状態だったことを考えると江戸の清潔度は高かったという事のようだ。
一方、江戸時代は廃棄物を回収して再利用するリサイクルが行き届き、ゴミはほとんど出なかったというイメージがあるが、それは幻想に過ぎないと指摘している。人件費は安く、物の値段が高かったので壊れかけた傘を始めとして、着物・衣服についても回収・修理・販売するのはビジネスとして十分なりたった。、所謂江戸の大店といわれる呉服屋(越後屋、白木屋など)が有名で我々も浮世絵などで知る機会は多いが、庶民はこうした大店で新品の着物を買うことはなく、街に多くあった古着屋で手に入れるのが普通だった。しかし、庶民の一般生活ごみは大量に捨てられており、江戸湾の埋め立てに使っていたとのことだから、それは昭和の時代まで続く江戸東京のゴミ廃棄サイクルである。
その他、長屋の構造、茶屋の種類、四ツ目屋といった解説は話のネタとしてもなかなか勉強になる。
二人の旅の最後は人情話となっている。大店の旦那が長屋に下女として連れて来てくれたお留という14才の少女。彼女が食事や買い物など万事面倒を見てくれている。健気に頑張るこの少女が明治維新を迎える時は57才になっていると考えると、これから少女が体験する混乱の時代と明治維新を無事に生き抜いてほしいと願う二人の気持ちは抑えがたい。しかし、少女にこれから起こることを話してやるわけにもいかない。そうしたタイムスリップの持っているもどかしさを上手く描いた小説としての側面を評価したい。
「江戸はゆたかで、自由で清潔だった」という江戸賛美は思い込みに過ぎず、現代人からすると不便・不潔と感じても、仮に文政八年の人が平安時代の京都にタイムスリップすれば、人々の貧しさや不衛生に愕然とするだろう。つまりは何処と比較するかである。そして、時代を知ることと、時代を生きることの違いを再確認した次第。そう考えると、100年後の人達が今の日本に来たらどう思うのかと想像するのも面白い。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





