月蝕書簡:寺山修司未発表歌集【寺山修司】
月蝕書簡:寺山修司未発表歌集
| 書籍名 | 月蝕書簡:寺山修司未発表歌集 |
|---|---|
| 著者名 | 寺山修司 |
| 出版社 | 岩波書店(226p) |
| 発刊日 | 2008.3 |
| 希望小売価格 | 1890円(税込み) |
| 書評日等 | - |
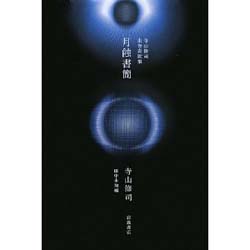
さながら亡霊のように現れてきた未発表歌集である。寺山が20歳台後半に出した「田園に死す」を最後にして歌集の発表は無かったと思う。その後、作歌を再開した1976年から1981年にかけて作られた短歌を採録したもの。劇団「天井桟敷」で寺山とタグを組んだ田中未知が編集している。
寺山が死んで何年経っただろうか。1960年代後半から1970年代半ば迄のほぼ10年間以降、寺山修司の存在は私の中からは長く抜け落ちていた。2004年に「'70 寺山修司」が世界書院から出版されたとき、久しぶりに寺山の文章に接し、懐かしさを感じながら目を通したものだ。拙宅の本棚には「青春歌集」や「書を捨てよ、町に出よう」などが並んでいるのだが、その後もまたその本を手にすることはなかった。
さて、作者の没後に未発表歌集を発刊するという仕事は寺山と付き合いの長かった田中といえども、草稿・遺稿から確定歌とすべきものを拾い、作歌途中の原稿なのかを選択するなど想像するだけで難しいことだと思う。残された原稿というかメモが巻末に写真で紹介されている。それを見ると、思いのほか丁寧な字体であるし、一部イラストめいた部分もあり、こうした形で詩歌が残っていると全て採録したくもなるだろう。しかし、寺山は「音を消す」「言葉を消す」という言い方で短歌を作ってきた。「個への退行を断ち切る歌稿 : 一首の消し方」という短文が本書に採録されている。
「・・・もともとあらゆる物語は語りつくされている。作者の仕事は消すという手仕事でしかない。どの部分を消し残すかということが作歌の楽しみである。三年のあいだ、私は自分の歌を消す作業ばかり熱中しているように思われる。それは所詮は孤立した個の中への退行の歩みに他ならないのだが一首の周辺から消して行くことで作者の内部を活性化するという試みが五を消し、七を消し、この歌も消してしまうことになる。・・・」
物語が語られ、言葉は消されていき、残る「言葉」はキュビズムの絵の断片のようだ。読み手として、その物語や内省を再構築して、追体験するという読み方を寺山はまったく期待していない。読み手が寺山の短歌に触発されて新たな世界をつくることが望まれているのだろう。彼にとって短歌とはそれ自体が完成された言語芸術ではないという事だろう。それだけに、遺稿集をノートから作り上げていく限界もあるはずである。もし、寺山が存命でこの歌集を「月蝕書簡」として完成させたとしても内容はかなり違ったものになるのだろう。
採録されている短歌を見てみると、以前からの寺山の短歌世界を色濃く残している歌も多い。例えば、「家族」。頻出するのは「父」と「義母」であり、「おとうと」「叔父」等。こうしたメタ的に使われている「家族」は寺山の少年時代からの大切なテーマであるといわれている。詠まれている状況はけして具体的でないが、個々の言葉は妙に具体的である。そのギャップが独特の不安定さを生む。佐々木幸綱にいわせると「シュール」ということなのか。
「父といて父はるかなり春の夜のテレビに映る無人飛行機」
「おとうとよ月蝕すすみいる夜は左手でかけわが家の歴史」
「履歴書に蝶という字を入れたくてまたうそを書く失業の叔父」
自己の存在が明確な歌もある。それでも、自分であるような、ない様な割り切れなさを切実に感じるのは、意識世界と肉体としての自己の葛藤が見えるからなのだろうか。「物語を抱え込む」と佐々木幸綱に言わしめた作風である。
「霧の中に犀一匹を見失い一行の詩を得て帰るなり」
「とぶ鳥はすべてことばの影となれわれは目つむる萱草に寝て」
言葉の持つ「説明性」をまったくそぎ落として作られた歌もある。個々の言葉の内的な意味を組み合わせた結果、新たに全体としての情景をつくるとでも言ったらよいのか。まるで、ダリの絵を前にしている様な気持ちになっていく。
「地平線描きわすれたる絵画にて鳥はどこまで墜ちゆかんかな」
「一夜にて老いし少女をてのひらで書物にかくす昼の月蝕」
「こけし買い子消しの冬の花嫁が書きくわえたる泣きぼくろかな」
解説によると、一度止めた作歌を1970年代半ばに再開する中で、寺山は「自分の過去を自分自身が模倣して、技術的に逃げ込む」過去の作歌に疑問を感じつつ、昔の歌に類似しないように努力していたとのことである。俳句・短歌から出発し評論・舞台・映画などを表現の場としてきた寺山がその活動を一巡させてまた短歌を詠む。作歌の方法論や技術論の問題ではなく、彼の考えが一貫して変化がない故に作り出される短歌は類似してしまうのだと思うのは乱暴なのだろうか。
いわく、「言葉に対峙するのは心ではなく、肉体である」。いわく、「個への退行を断ち切る」。こうした立ち位置で生きる限り、舞台であれ、映画であれ、詩歌であれ、寺山本人が類似を避けていたとしても、読者からするとその短歌は寺山修司の短歌であることを認識できてしまうのだが。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





