金融史の真実【倉都康行】
金融史の真実
| 書籍名 | 金融史の真実 |
|---|---|
| 著者名 | 倉都康行 |
| 出版社 | 筑摩書房 (237p) |
| 発刊日 | 2014.04.07 |
| 希望小売価格 | 842円 |
| 書評日 | 2014.06.15 |
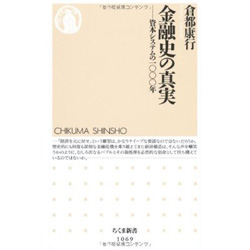
マクロ経済に関する本を手にするのは久しぶりだ。35年間の現場での仕事、10年間の経営の立場を通して、管理すべき数値は売上高、営業利益、顧客満足度、他社比成長率といった極めてミクロ的な指標を追いかけてきたこともその原因。当然、景況感とか市場動向、為替といった常識的な範囲でのマクロ指標に関する目配りもしていたものの、現場感覚で言えば「営業利益」こそ、自らが作り出した価値という分かりやすい達成感が組織の一体感を醸成していた。金融機関や投資家の方々が、企業価値とは経常利益や純利益だと言われるのはもっともではあるが、働いている人間にとっては自分の汗の結果こそ実感の源泉であった。そんな評者に対して、金融界に長く身を置いていた方から、読んでみたらと勧められたのが本書。「売上・品質・利益・競争」を卒業したからには、ゆっくりマクロ的視野で社会を見てみたらという助言なのであろう。
本書は経済システムの将来を考えるにあたって幾つかの論点を示している。
第一に、資本主義とか資本市場といった「マネー」が主役を演じる経済体系を「資本システム」と名付けることで、「主義」の議論を回避しながら、12世紀のイタリア都市国家成立から現代に至るまでの発展ブロセスを俯瞰していること。そのポイントは「歴史を学ぶことではなく、歴史から学ぶことである」として、現在の超金融緩和時代の出口戦略について歴史から読み解こうとしている。
第二は、その発展プロセスから学ぶべきキーワードとして、「リスク」と「金融危機の循環性」と「ヘゲモニー(覇権)」の関係を提示している。特に「金融危機」を食い止めるための重要な要素は「ヘゲモニー」と主張である。1920年代から1930年代にかけて、衰退する大英帝国の役割を代替する国がなかったため、大不況後、各国が保護主義に走り世界経済は混乱を深めた。その後、ヘゲモニーを握った米国も第二次大戦の後、冷戦が収束するとともにその力に陰りが見え、特に1980年代以降は「金融危機」に対する力の発揮は期待できない状態と言われている。それでは、現代のヘゲモニーたる「最後の貸し手」とは誰かというとIMFがその立場にあるというのが教科書的な解答なのだろうが、その力は一国の危機には対応出来ても、広範な地域の経済危機にはとても対応できない状態にあるというのも事実。
第三に、「過剰な中央銀行へ依存」しているリスクを繰り返し指摘している。特に現在、世界各国の中央銀行総裁は通貨価値を守るという伝統的なタイプの人間ではなく、積極的に通貨価値を落としていくべきだという正反対の考え方の人物が就任しているのは偶然ではないとしているのも、興味深い指摘だ。
そして、第四に、日本をグローバルな視点からの特殊性を示しつつ日本の金融の問題を提起しているのだが、この部分が著者の言わんとする重点と考えてよさそうである。
リーマン・ショックやサブプライム・ローンによる経済危機からの回復過程において、各国の政策運営は積みあがってしまった莫大な公的債務の負担の下では財政政策の打てる余地は限界があり、金融政策に依存せざるを得ないという事態になっている。しかし、金融緩和を続けた結果、金利を下げる余地がなくなってしまった各国中央銀行にとっては、まさに非伝統的な政策を通じて「より財政政策に近い役割」が要求されていると言われている。こんな見方を著者はしている。
「現代の経済社会は、経済成長の過程で金融は潤滑油の働きをしている。・・・だが、あまりに金融緩和の政策が肥大化して長期化すると、どんなに金融当局が『緩和は時間稼ぎの政策だ』と説明しても、人々は金融政策を潤滑油ではなく、動力そのものと見做すようになる」
ここで言う「人々」とは政治家や機関投資家だとすると、最早、それは経済金融問題ではなく政治問題だという指摘は正しいと思う。
加えて、現在の日本に目を向ければ金融緩和策の結果として、「政府と中央銀行が経済へ『金融カンフル剤』を打ち続ける過渡期的時代」とまで著者は言い切っている。確かに、日本の公的債務残高は245%と世界各国間でダントツの悪さである。二番手がイタリアの131%、三番手が米国の108%という数字からも異様な数字となっている。
もう一つ、気になる数字が紹介されている。それは自由競争についての認識が日本人において希薄だということである。「自由市場経済」に関する国民意識を主要21ケ国を対象として行われた調査結果である。上位は、ブラジル、中国、ドイツ、アメリカ、と続く。一方、下位層を見ると、最下位メキシコから次に日本、チュニジア、ヨルダンとなる。ここで示される日本の「市場嫌い」「競争嫌い」は明確だ。それは「国家の繁栄が個人の生活水準を上げるという成長方程式に沿って経済を眺めていたために、経済に逆風が吹くと、常に財政政策や金融政策の出動を願い、銀行が破たんしそうになると公的資金で救うのが当然」といった意識が強いというのを、以下のような歴史的経緯によって説明されている。
「結局、20世紀初めの大不況後の世界の資本システムは戦争(第一次大戦)という『不幸な公的システム』の下で稼働していた。この時期には民間資本の利益構造はますます『国益』と一致するようになる。この時期に初めて資本システムを輸入した日本に『国家が主導する資本主義』という経済モデルが定着し、今日までそれが生き延びている」
これは、第二次大戦後の1970年代初めから、ドルの兌換停止や固定相場制の終焉ととともに、日本の「公有化された資本システム」ともいうべき日本の特殊な資本システムに対しても、世界は強く変革を迫まり、金融自由化が進められた。しかし、「市場主義」や「競争」への対応は結果としてあくまで表面的で、意識の底では「国家主導の資本主義」が残存しているという見方だ。
そして、極め付けとして著者は、中央銀行と市場の対話力に焦点を当てている。
「黒田日銀総裁の『対話力』は就任以来、強気一辺倒の姿勢を保持し続ける同総裁の対話方法に懸念を示す向きは内外に決して少なくない」
日銀会見のニュースで見る黒田総裁の態度からは、ふてぶてしさを感じることはあっても、自信とか誠実さというものはまったく感じることが出来なかった。評者はそれを個人的な好き嫌いから、そう見えているのかとも思っていたが、グローバルの金融界からもそう受け止められていたとすると、自分の感覚にも納得がいく。
現代の日本が置かれている状況はグローバルに見て明らかに「悪い位置」に居ることを本書は指摘している。いわゆるアベノミックスの第一の矢である「異次元金融緩和」を語る黒田総裁の対話力欠如。第二の矢である「機動的な財政政策」を阻む公的債務の悪化状況。第三の矢である「規制緩和等、経済の活性化」を阻む日本人の変わらぬ意識構造。こう考えると、金融のリーダーたる日銀黒田総裁の限界だけでなく、任命責任者たる安倍首相も限界が見えてきたということか。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





