「この国のかたち」を考える【長谷部恭男ほか】
「この国のかたち」を考える
| 書籍名 | 「この国のかたち」を考える |
|---|---|
| 著者名 | 長谷部恭男ほか |
| 出版社 | 岩波書店(224p) |
| 発刊日 | 2014.11.27 |
| 希望小売価格 | 2,052円 |
| 書評日 | 2015.01.12 |
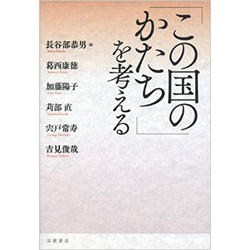
本書は、2013年の10月から2014年の1月にかけて、東京大学で行われた学術俯瞰講座の「この国のかたち - 日本の自己イメージ」をベースとしてまとめられたもの。当時、盛んになりつつあった憲法改正に関する議論を見据えて、日本国憲法を考えるための材料を提供するという趣旨で、法学(葛西康徳:古代ギリシャ・ローマ法、宍戸常寿:憲法、長谷部恭男: 憲法)・政治学(苅部直:日本政治思想史)・歴史学(加藤陽子:日本近代史)・社会学(吉見俊哉:メディア論・都市論)といった領域からの広範な視点で構成されている。本書の編者である長谷部はその意図を「人にそれぞれ人柄があるように、国にも国柄があります。現在の日本の国柄はどのようなものか、憲法のテクストを変えることは、その国柄にどんな影響を及ぼすことになるのか・・本書がそうした問題を考える手がかりとなれば幸いです」と記している。
苅部直は「この国のかたち」と言うタイトルの意味について、「わが国」とするとナショナリズムの空気をまとい、「形」とすると防衛白書みたいであるとして、中立的な柔らかい表現にしたという程度の選択であるとしている。一方、司馬遼太郎が「文芸春秋」に連載していた巻頭随筆をまとめて出版の際に、その本のタイトルを「この国のかたち」としたことに触れ、戦前に教育を受けた司馬の世代が「わが国の形」という言葉を目にすれば、教育勅語にあった「國體」という言葉に結びつくはずだという観点から話を始める。開国・明治維新を通して、過度な西欧化を恐れた明治政府は大日本帝国憲法制定(1989年)の翌年、天皇を中心とする国の道徳の徹底を強化する意図で教育勅語を発布した。
その後、1920年代には社会運動が盛んになるにしたがい、1925年に公布された治安維持法では「國體」の「変革」を目的とする運動に参加したものを重罰とすることになった。「國體」が道徳を超えた形で法制化された瞬間である。次の、天皇制の大きな転換は日本国憲法で天皇が「統治権の総攬者・祭政一致の体制」から「象徴」への変化をしていくのだが、「この国のかたち」と天皇制の変遷をたどり、考える面白さを十分堪能させてくれる内容である。
加藤陽子の「戦争の記憶と国家の位置づけ」では、歴史学の立場から、第二次大戦に至る、日本の戦争に対する記憶の役割に注目して説明している。多くの論点がある中で、その一つが、第二次大戦前(1941年)の日米交渉での外務大臣松岡洋佑の文書(1941年7月1日)である。松岡は日本が東アジア政策を堅持しなければならない理由を次のように述べている。「永年に亘り、幾多の困難を排除し、三度国運を賭し、二十余万の生霊と巨大なる国幣を犠牲として、漸くにして、その基礎を築き上げた」からとしている。日本政府・松岡の譲れない条件(この国のかたち)はこうした累積された戦争の記憶が重要な要素となっていたというのが加藤の言わんとするところであるし、1931年に国際連盟理事会の満州調査団を率いて訪日したリットンの言葉を紹介している。
「満州は日本の生命線であり、この点に関して、日本は非常に敏感であり、何人といえども日本のとれる立場を疑うことは許されないと言われました。我々は之を全て認めます。・・・しかし、他の国民もまた、それぞれ敏感なるべきものを持ち、誇るべきものを持ち、又日本が満州において感ずると同様に非常に強く感ずるところの在るものを持っていることを申し上げたいと思います」。この様に、松岡とリットンの言葉を並べることで、記憶の連鎖を自国の主張の軸にするリスクとグローバル視点の重要性という普遍性を示していると理解した。まさに加藤の言う「原資料」に基づく歴史理解の実践と言える。
吉見俊哉の「広告化する戦後と自己像の再定義」は、商品広告と憲法という相反する二つの関連性を明らかにするといった面白い試みである。1950年代には、新憲法は戦後の国民の「理想」を表現しているとして、新聞広告に憲法が引用されるという事例が紹介されている。
「日本の憲法、第二十五条には『国民の健康で文化的な生活をいとなむ権利がある』とうたわれています。この私たち国民のすべての願いが満たされていくもの----そのひとつに家庭の電化があります」
これは松下電器の広告で、ある一点を除いて、家電の広告に憲法の条項をストレートに使っているという珍しいもの。続く1960年代では、「この国のかたち」は「文化」と「技術」をライフスタイルの問題として表現され、この間に、日本人はメイド・イン・ジャパンの「技術力」に自信を持ち始め「この国」の価値を高めていった。東京オリンピックで戦後のこのプロセスは完遂されたと吉見は見ている。
次の1970年代は、「個人の詩・文学化」といった変化が広告において始まる。それは国鉄の打った「ディスカバー・ジャパン」キャンペーンである。それは都市化の中で「失われた自分」の再発見と「失われた日本の風景」の再発見を一対のものとして示した風景に出合う「私」をドラマ化したCMだった。メイド・イン・ジャパンのジャパンとディスカバー・ジャパンのジャパンのあいだには決定的な断絶が有る。前者では自明であった「ジャパン=自己」が後者ではそれはゆらいでいる。そのゆらぎを広告表現に取り入れて「ジャパン」を求める旅に人々をいざなっている、という指摘は同時代に生きた評者としては納得感のあるところだ。吉見の分析は21世紀の広告CMまで続く。面白い内容である。
宍戸常寿の「憲法の運用とこの国のかたち」では、まず、国民が日本国憲法に対してどんな態度をとったのかをこう説明している。「政治の側とは別に」、立憲主義の現れというより「生身の人間にとって大切なものを決めてある、というイメージ」で受け止められ、とりわけ敗戦後の貧しい状態においては平和・福祉といった「くらしを守り手」として支持されたのではないかとしている。この考え方は、戦後改革で若者として体験した世代に「護憲」が有力である反面、その成果を当然のものとして享受している若者世代が「改憲」に共感するという傾向を分析して見せている。
また、日本国憲法は条文・文字数が少なく、内容は弾力的で憲法付属法や最高裁の解釈などの運用に委ねられているという特性を持つ中で、日本国憲法施行以後1973年の尊属殺重罰規定裁判を初めとして最高裁で9件の裁判で「法律」を違憲とし、一票の格差について6件が違憲状態と判断していることから憲法運用の不安定さが増していると言う意見である。まさに憲法の担い手としての最高裁判所の存在感が高まってきているからこそ、政治プロセスが正しく機能しているのか、憲法の運用ないし改定が正しい処方箋であるのかを問い掛けることこそが「国民」が「この国のかたち」を考えることの意味としている。
長谷部は、憲法による戦争の抑制という観点を語っている。国と国が領土で争い、政治体制の是非をめぐって争いを続けているが、この二つの問題は関連しており、その対立が深刻になるのは、国境線の両側に異なる政治体制、つまり憲法原理を異にする国家が存在するからだ。逆の言い方をすると、全ての国家が同一の政治体制をとるならば国家間の深刻な対立・紛争は姿を消すはずと言う。EUを例にあげ、ヨーロッパ各国は相互の安全は、国境線を挟む軍事力の均衡ではなく、相互の透明性と監視によって保たれている。これらの国家は「近代主権国家」ではなく、「ポスト近代国家」であり、EU諸国に続いて、ポスト近代国家になる可能性を秘めているのは日本だと主張しているイギリス外交官のロバート・クーパーの考えを紹介している。しかし、日本が現在そうなっていない理由として、長谷部は、隣国に近代国家以前の帝国が存在するからだが、いつかその中国もリベラル・デモクラシーへと変貌するとしている。
その日がくるまで自由で民主的な政治体制の下での私たちの暮らしをどう守っていくか。それを冷静に考える必要があると結んでいる。長谷部の章は、他の人たちの章に比較して、彼の自論を前面に出している部分が目立つ文章になっている。東大での講座の内容に比して、本書を出版するにあたっての変更・付加された部分があると考えたがどうだろうか。その点を除けば、各章を担当する講師陣は、想定した論点を明確にするにあたって、かなり公平かつ広範に意見を提示していると思う。学術俯瞰講座と名付けられただけのことはあり、自論の展開だけに偏ることもなく、抑制された冷静な語り口で論理展開をしているのが良い意味で印象的だが、議論の先鋭化が少ない分だけ、妙に丸くなってしまっている部分が有ることも否めない。ただ、まさに俯瞰的に集団的自衛権、憲法改正など多くの議論が戦わされている現在、考えるヒントと言うか、考える気にさせてくれる一冊であると思う。それだけに、実際この講座を聴いた学生たちの感想も聞きたいところである。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





