キトラ・ボックス【池澤夏樹】
キトラ・ボックス
| 書籍名 | キトラ・ボックス |
|---|---|
| 著者名 | 池澤夏樹 |
| 出版社 | KADOKAWA(320p) |
| 発刊日 | 2017.03.25 |
| 希望小売価格 | 1,836円 |
| 書評日 | 2017.11.22 |
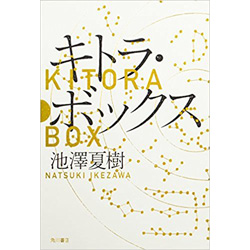
個人的な読書の傾向でいえばそのほとんどがノンフィクションで、小説やミステリーを読むことはあまりない。著者の池澤に対しては文学者・詩人・小説家といった分野のイメージが強く、最近であれば、河出書房新社の世界文学全集に続いて日本文学全集30巻の個人責任編集を行っているが、そうした統合的・企画的な仕事の印象がある。彼は若い頃にはミステリーの翻訳も手掛けていたようだが、まずは池澤とミステリーという取り合わせに惹かれて本書を手にした。
実は、ミステリーを読むのは疲れるという実感がある。登場人物の数が小説に比べて多いし、その立場や関係をしっかり覚えていなければいけない。また、情景描写や会話表現の中に巧みな形で謎解きのヒントが隠されてることもあって、丁寧に読まないといけないのがなかなかのプレッシャーだ。別の言い方をすれば、ミステリーは読者の勝手な読み方を許容しない。作者の計画通りに結論に到達する必要があるからだ。丁度、何枚もの地図を繋げてチェック・ポイントを確認して目的地に到達するのに似ている。そうした意味では小説とミステリーは根本的な違いが有るのだろう。
本書は三枚の銅鏡と一振の銅剣にまつわる物語で、時間軸は壬申の乱(672年)から現代まで、西域・ウイグルから唐・中国、そして倭国・日本という地域を広く俯瞰し、同時に、現在の中国が抱えている多民族国家の問題、独立運動を描いている。発掘考古学の手法・手順が丁寧に表現されていることや、過去の日本や中国の詩や文学作品に見られる心象表現の違いや竹取物語の婿取譚からの推論等を謎解きの一環として利用しているところなどは池澤の面目躍如の領域だろう。また、盗聴・傍受とその対策、暗号化、不審車両推定、人物特定など現代の情報技術の利活用の実例が多く盛り込まれている事はストーリーの現代性を印象付けている。
そのミステリーの主人公は可敦(カトン)という名で、母を中国に残して日本の国立民俗博物館に研究に来ている女性である。国籍は中国、民族としてはウイグル人とチベット人の混血という出自である。本人としては政治活動に関心はないが、兄がいて新疆ウイグル自治区の民族活動の指導者をしており、中国政府は彼女を誘拐して兄に圧力を掛けようとしていると可敦自身が自己紹介している。彼女はウイグル出土の銅鏡に関する論文を書いており、自身の考古学研究の進化を求めて日本に来ている。考古学のプロとしての技術と志の高さについて疑いはない。加えて、ウイグル出身という立場と母一人を母国に残して来ているという前提。
奈良県明日香村阿部山にあるキトラ古墳の被葬者を解明していくというのが、謎解きのとっかかりではあるが、被葬者は天武天皇の皇子である高市王子、百済王昌成、右大臣の阿倍御主人(あべのみうし)という三つの学説があり学術的には特定されていない。一枚目の鏡の出所について、キトラ古墳盗掘の物語から話は始まる。
古墳造成時(7世紀末)に土方として墓の石積に駆り出されていた男が仲間とともに20年後、すっかり木々に覆われたこの墓の盗掘を企てる。男は石棺の一部を外して中に入り、天井に描かれた星々に圧倒されながらも、一枚の銅鏡と一本の銅剣を盗み出す。この小悪党は逃げる途中、大峰山の楠の根元で休んでいた時にイノシシに襲われ死ぬ。年を経て、一人の修行僧が骸骨とその脇に銅鏡と銅剣を見つけ、それらを祀るための祠が建てられて、日月神社として以後1200年の間信仰されることになる。
日月神社から祠にあった鏡と剣の鑑定を依頼された考古学の教授藤波は、ウイグルの銅鏡に関する論文を発表していた可敦に鑑定協力を打診する。この銅鏡を見た可敦は自分が研究対象としたウイグル出土の銅鏡と同じところにキズがあることから同一の鋳型から作られた鏡と判断し、銅剣を見ると柄のすぐ上、刀身の一番下のところに丸い印がいくつか並んでいる。「北斗と輔星」らしきその模様を見た可敦はキトラ古墳の天文図を思い浮かべた。後日、瀬戸内海の大三島の大山祇(おおやまずみ)神社にある国宝の禽獣葡萄鏡が日月神社の鏡と似ているので調査をしようと藤波から誘いが有る。二人で確認するとこの鏡も同一の鋳型でつくられたものと判断され、ウイグルに一枚、日本に二枚の計三枚の銅鏡がそろうことになる。この鑑定後に可敦は大三島で二人の男に襲われたが、すんでのところで藤波に助けられる。
章が変わると、キトラ古墳に埋葬された男が一人称で自らの体験を語る。その男は左大臣・阿倍内麻呂の息子の阿倍御主人(あべのみうし)であると読者は知る。17才の時に学問を志し、唐への使節団の一員に加えてもらう。その遣唐使の規模、航海のリスク、長安での生活描写など詳細に語られる。ある日、長安の食堂で西方の文化や生活を知る男と出会う。ウイグル出身の「薬羅葛(ヤグラカル)」というその男は三日先のことを言い当てる占術に長けた男。帰るべき国が滅ぼされたとのことで「みうし」は「ヤグラカル」を日本に連れて行くことにする。
長安で二人が唐の言葉を学んだ先生から、日本に向けて出発する日に各々一枚ずつ鏡が渡された。加えて、もう一枚阿倍御主人に鏡を渡し、「古来、天下の大事を成し遂げるには、大丈夫が三人要るといわれる。君たちの人生にもう一人の丈夫が現れるときが来る。そのとき残りの一枚をその男に渡せ」と言われる。
日本に渡ったヤグラカルは竹田大徳と名乗り、朝廷の占術の部門で働くことになる。壬申の乱では阿倍御主人とともにヤグラカルは大海人皇子側について戦いに勝利する。その後、彼は死を前に阿倍御主人に鏡とともに、「私の鏡を次回の遣唐使に持たせ、長安の先生に渡し、故郷のウイグルに鏡を納めてほしい。占術に使う天文図を君に授ける。そして一振りの剣を作らせて、その刃に星々を象嵌させた」という手紙を届ける。
こうして、読者は三枚の鏡と一振りの銅剣の経緯が判るのだが、現代の可敦と藤波にはまだ学術的な立証は出来ていない。
藤波は可敦を拉致騒ぎから守るため、岡山県美作市の発掘現場のメンバーとして送り込んだものの、中国語を話す二人組の男に襲われ拉致されてしまう。拉致された可敦は二日後に犯人達をまわし蹴りと手刀で叩きのめして自力脱出してくる。この事件はウイグル・チベット族出身の反体制運動家の家族としてメディアにも大きく報道されることになる。
国立民俗博物館に戻ると「ロプノール 気付 高車」と書かれた書簡が可敦宛てに届いている。ロブノールとはウイグル人国際連帯組織でウイグル人の立場と主張を日本人に訴えてほしいという内容であった。
銅剣に対するX線やファイバースコープによる調査で、新たな資料が発見されて推理は進んで行く。最後に三枚の銅鏡と銅剣の持ち主を特定することに成功するのだが、最後に明らかになる可敦の正体もミステリーらしい筋書である。
日本における最大の内乱といわれる壬申の乱とその時代の世界が結ばれる。キトラ古墳の精緻な天文図、銅鏡、銅剣といった現存する遺物に夢を馳せる楽しさに加えて、古代と現代を交錯させるストーリーは複雑であり、このミステリーを構成する部品は数多い。これだけの歴史と文化を一つの物語に仕立て上げる池澤の知識・知見は広く、そして深い。ミステリーという緻密なパズルを創り上げる才能は、また特別の物だろうと思う。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





