苦海浄土 全三部【石牟礼道子】
苦海浄土 全三部
| 書籍名 | 苦海浄土 全三部 |
|---|---|
| 著者名 | 石牟礼道子 |
| 出版社 | 藤原書店(1144p) |
| 発刊日 | 2016.09.10 |
| 希望小売価格 | 4,620円 |
| 書評日 | 2020.10.17 |
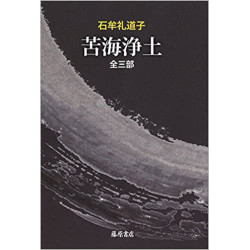
山田風太郎晩年のエッセイに『あと千回の晩飯』がある。いろいろな徴候から、晩飯を食うのもあと千回くらいなものだろう、という書き出しだった。このとき風太郎72歳。亡くなったときは80歳を超えていたから実際にはその倍以上の晩飯を食ったことになるが、僕自身も70歳をすぎて病気し、あと何回という思いがよく分かるようになった。本を読んでも、映画を見ても、あと何冊、あと何本という気持ちが湧いてくる。一冊も、一本も無駄にできないような気がしてくる。そんな心境になってくると、いつか読もうと書棚に積んである何十冊もの本が気にかかりはじめた。これらの本を、ついに読まずに終わるのか。
そんな積読本のなかで、いちばんオーラを発して手に取ってほしいと訴えていたのが石牟礼道子『苦海浄土 全三部』だ。漢和辞典のように厚いこの本の第一部『苦海浄土』が刊行されたのが1969年。その後、第二部『神々の村』が井上光晴編集の『辺境』に書き継がれたが雑誌の休刊とともに中断。第三部『天の魚』が先に刊行され、全三部が完結したのは石牟礼道子全集が出版された2004年のことだった。単行本として全三部を一冊にまとめた本書は2016年に刊行されている。第一部の出版から50年近く、著者が地方誌『熊本風土記』に書き始めてから60年近くの歳月がたっている。
第一部が刊行された当時は公害を告発するノンフィクションに分類され、桑原史成の写真をカバーや本文にあしらった造本もその方向で設計されている。僕もそのようなものとして読んだ。また第一回大宅壮一ノンフィクション賞に内定してもいる(辞退)。その後、彼女の仕事の全貌が明らかになるにつれノンフィクションの枠に留まらないその広さ深さが理解され、現在では戦後日本文学を代表する作品のひとつと評価されている。池澤夏樹が個人編集した世界文学全集(河出書房新社)では日本語の作品として『苦海浄土』ただ一冊が選ばれている。
そんな大きな存在に今さら言うべきこともない。でもせっかく1100ページを読みとおしたのだから、きれぎれの感想でもつけ加えておこう。
『苦海浄土』が文学として評価されるようになったのは、『チェルノブイリの祈り』のスベトラーナ・アレクシエービッチやボブ・ディランがノーベル文学賞を受けたように、世界的に文学の概念が広く考えられるようになった流れと無関係ではないだろう。でも三部作を読んで感じたのは、これは日本の近代文学、たとえば漱石や谷崎や三島とはまったく別の場所から出てきたものだな、ということだった。
まずは三部作の印象を一言ずつ。第一部はひたすら重く、深く考えさせられるのだが、なんとも美しい。途中中断した第二部は、掲載誌の休刊という外側の条件だけによるものでなく、苦渋に満ちている。それに対して第三部は、力強い。
第一部「苦海浄土」を読み始めて、50年前にもそうだったように、石牟礼道子が水俣病の患者やその親や爺さま婆さまの話に耳を傾け、彼ら彼女らになりきって語る、そのカタリの美しさに惹きこまれた。たとえば漁師の妻で患者であるゆき女のカタリ。
「海のうえはほんによかった。じいちゃん(亭主)が艫櫓(ともろ)ば漕いで、うちが脇櫓ば漕いで。いまごろはいつもイカ籠やタコ壺やら揚げに行きよった。ボラもなあ、あやつたちもあの魚どもも、タコどもももぞか(可愛い)とばい。四月から十月にかけて、シシ島の沖は凪でなあ──。/うちは三つ子のころから舟の上で育ったっだけん、ここらはわが庭のごたるとばい。それにあんた、エベスさまは女ごを乗せとる舟にゃ情けの深かちゅうでしょ。ほんによか風のふいてきたばいあんた、思うとこさん連れてゆかるるよ。ほらもうじき」
水俣の海では夫婦が夫婦舟で漁をする。青い海と空の下に浮かぶ小舟に乗って寄り添う二人の至福の風景。しかしそこで採る魚はチッソ工場が海に流した廃液の有機水銀で汚染されていた。苦海が即ち浄土であるような夫婦の愛情。こんなカタリが三部作を通して、さまざまに語られる。その純度の高さにうたれる。
石牟礼道子が患者になりかわって語る、そのきっかけとなった出来事が記されている。彼女がはじめて水俣市立病院を訪れたときのこと。「肘も関節も枯れきった木」のような腕と足で床にころがり、目も見えず言葉も発せず、しかし意識はあって自らの姿に怒り恥じている老患者、釜鶴松の姿を目の当たりにした彼女はこう書く。「この日はことにわたくしは自分が人間であることの嫌悪感に、耐えがたかった。釜鶴松のかなしげな山羊のような、魚のような瞳と流木じみた姿態と、決して往生できない魂魄は、この日から全部わたくしの中に移り住んだ」
そこから彼女は、ゆき女や江津野の爺さまや九平少年や、患者と患者の親、爺さま、婆さま、そして死者に憑依して病気のこと自らのことを語る。その文体から受ける印象はノンフィクションというより、たとえば琵琶法師が琵琶にあわせて語った物語が文字化された『平家物語』に近い。などと訳知り顔で言わずとも石牟礼は自ら、これは浄瑠璃のごときものと書いている。
その一方、当初奇病といわれた水俣病の原因が特定されるまでや、患者の要望に対するチッソ企業の木で鼻を括った回答については、科学的あるいは法律的文章がまるごと引用されている。客観性を装っているだけに、たとえば1959年に結ばれた「契約書」の「乙(患者互助会)は将来水俣病が甲(チッソ)の工場排水に起因する事が決定した場合においても、新たな補償金の要求は一切行わないものとする」といった文面から浮かび上がる鉄面皮と傲岸が際立つ。
水俣市はチッソとともに発展してきた。チッソに勤める者は「会社ゆき」として尊敬され、市民の上層・中層を占めている。行政にも影響力をもっている。そんな地域共同体のなかで水俣病患者の補償を求める行動は会社をつぶすものとして村八分され、奇病は貧しさから腐った魚を食べたせいと差別され、孤立してゆく。それだけに石牟礼の描く、主に零細漁民たちからなる患者になりかわってのカタリが胸をうつ。
第二部でもこの美しいカタリは随所に顔を出すけれど、そこに何本もの亀裂が入ってくる。第一部で夫婦舟を語った患者のゆき女は、夫から捨てられている。市役所に、患者と思しい者から同じ患者の不正受給を訴える密告が届く。そうしたことどもを石牟礼は静かに記す。さらに、患者互助会が二つのグループに分裂する。補償と救済を国の中央公害審査会に一任する一任派と、裁判で争おうとする訴訟派と。
石牟礼は訴訟派に寄り添って、訴訟派の患者がチッソ株主総会に一株株主として出席し、社長と直に話をしたいという行動に同行する。患者のその動きは、裁判になれば社長が出てくる、偉い人と直に話せば分かってくれるはずだという期待と裏腹に、代理人と代理人によるやりとりがつづく法廷に不満を募らせた結果だったようだ。患者たちが白い巡礼着に身をつつみ、鈴をならし、御詠歌を歌い、黒地に「怨」を染め抜いた旗を立てて株主総会に出席し社長と対峙する場面が第二部のクライマックスとなる。
第三部では、一任派でも訴訟派でもなく、新たに水俣病と認定された新認定患者が主役となる。裁判ではなく会社との自主交渉を求める新認定患者たちは、水俣の工場や東京駅近くのチッソ本社内に座り込む直接行動に出た。そのリーダーで、父親も自らも患者である川本輝夫は、水俣近在に潜んでいた患者を掘り起こし、説得して仲間をつくり、座り込みを提起してゆく。石牟礼はその行動に同行した。「自ら(地べたに座る)非人(かんじん)となり、故郷やこの国への疫病神となって」社長にカミソリの刃をつきつけて血書を迫る、石牟礼の描写する川本は、あたかも神話のなかの荒ぶる神のようだ。彼らの直接行動は、学生運動が高揚し挫折してゆく1970年前後という時代背景もあったにせよ、それ以上に、会社や国の「偉い人」の誠意を信じた一任派や裁判という形式に飽き足らなさを募らせた訴訟派の無念と怒りをも背負って、その底から噴き出した自然としてあったろう。
石牟礼は、地域から孤立した初期の患者たちに寄り添い、裁判でたたかうことを選んだグループに寄り添い、さらに直接行動を選んだ尖鋭なグループにも寄り添った。それは患者たちを支援する市民団体のなかで、いろいろな軋轢を生じさせたのではないかと想像する。また、患者を支援する団体のなかで政党や新左翼の政治的な動きもあったろう。
そうした政治的季節のなかで書かれたものは、その時代の価値観のなかでいっとき輝くにしても、時代が変われば往々にして古び、忘れさられてゆく。でも『苦海浄土』三部作が今にいたるまで新鮮な生命力を保ち、いよいよその輝きを増しているのは、石牟礼が時代の価値観に目もくれず、ひたすら患者を見つめ、彼らの声に無条件で耳を傾けつづけたからだろう。
第二部に印象的な場面がある。訴訟派と行動を共にしていた石牟礼が、余命いくばくもない一任派のリーダー、山本亦由を病院に見舞う。
「この人(山本亦由)の全身像を心の中心に据えながら、動き出した事態の中で、見かけ上は、路線のちがう方向へ、心ならずもついてゆかざるをえなかった。/『小父さん』/かろうじてわたしはそう言った。妻女に助けられて顔をあげ、その人は苦悶の表情のまま、かすかにうなずき、じっと私を見た。それがお別れだった。/一人の人間に原罪があるとすれば、運動などというものは、なんと抱ききれぬほどの劫罪を生んでゆくことか。人の心の珠玉のようなものをも、みすみす踏みくだかずにはいないという意味で、そのことに打たれ続けることなしに、事柄の進行の中に身を置くことなど、出来なかった」
チッソ本社内に座り込む自主交渉派といても、裁判でたたかう訴訟派といても、石牟礼の心には一任派のリーダーである山本亦由の存在がその「中心」にいた。それは、初期の水俣病患者が差別と偏見にもがき苦しんでいた時期に、山本がどんなふうに患者たちの面倒を見ていたかを石牟礼は傍らでつぶさに見ていたからだろう。ある女性患者は半狂乱で「小父さん、世論に殺されるばい」と山本宅に飛び込んできた。水俣病を発症した自分の娘だけでなく、ゆき女はじめ、目にあまる患者たちを親切に看病してまわった。一任派の患者たちは、地域共同体の地縁血縁に十重二十重に絡めとられて悩み苦しんだあげく国の斡旋案にハンを押した人々だった。そんな、地域共同体の底にいる人々とそのリーダーの姿が石牟礼のなかには常にある。
『苦海浄土』三部作は、そんなふうにフィクションでありルポルタージュであり、カタリであり歴史の原史料でもあるような多面体として存在している。そのスタイルと中身について常に自覚的だった石牟礼道子は、この作品の成立にかかわるふたつの印象的な言葉を記している。
「私の故郷にいまだに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を階級の原語と心得ている私は、私のアニミズムとプレアニミズムを調合して、近代への呪術師とならねばならぬ」(第一部)
「私が描きたかったのは、海浜の民の生き方の純度と馥郁たる魂の香りである」(全集版あとがき)
「近代への呪術師」であろうとしたからこそ、『苦海浄土』三部作はこの国の近代が生みだしたものに根底的な疑問をつきつけることができた。都市や企業や法などというものと無縁に生きた「海浜の民」のカタリがあるからこそ、この作品は不変の生命をもつことができた。1世紀をこえる歴史をもつこの国の近代文学のなかで、こういう場所から生まれたものはたぶん他にないと思う。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





