マゼラン船団【大野拓司】
マゼラン船団
| 書籍名 | マゼラン船団 |
|---|---|
| 著者名 | 大野拓司 |
| 出版社 | 作品社(272p)) |
| 発刊日 | 2023.11.05 |
| 希望小売価格 | 2,970円 |
| 書評日 | 2023.12.15 |
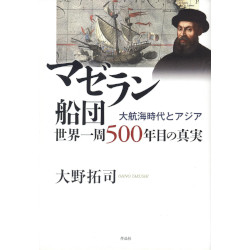
マゼランと聞けば、われわれの世代はすぐに「世界一周」と反応する。でも、最近の若い人からは「マゼラン、誰?」という反応が返ってくるかもしれない。今の教科書ではマゼランという英語表記でなく、マガリャンイスというポルトガル表記が使われている。彼を派遣したのはスペイン王だが、マゼランはポルトガル人だったからだ。ついでに言えば、マゼランは航海途中にフィリピンで殺されてしまったから、初めて世界一周したのはあくまで「マゼラン船団」で、個人名で言うならマゼラン死後に船団を指揮したエルカーノということになる。
ところで日本ではこの時代を「大航海時代」と呼んでいる。でも欧米では「発見の時代 Age of Discovery」が一般的であるように、15~17世紀のヨーロッパによる海外進出についてはまだまだ西欧的な視点で語られることが多い。われわれ自身も、文明を発達させつつある西洋と遅れた東洋の出会い、といった偏見に囚われていたりする。著者の大野拓司はフィリピンに留学し、その後、ジャーナリストとしてもこの地に滞在した。そこで多くの資料に目を通し、マゼランの足跡を訪れ、フィリピン、ひいては東アジアという視点からマゼランの航海をたどったのが本書だ。
まず大前提として押さえておくべきなのは、中世末期のこの時代、王侯貴族はともかく庶民レベルでヨーロッパは貧しく、それに対しアジアは比較的豊かだったこと。自然環境に恵まれた東アジアは少なくとも飢えから遠かった。一方、寒冷地のヨーロッパの生活は厳しく、食物は「想像もつかぬほどまずかった」。ヨーロッパ人が命懸けで香辛料を求める航海に出たのには、そんな背景があった。
セビリアを出発したマゼラン船団が南米大陸南端の海峡を抜けて「南の海」(太平洋)に出、3カ月余航海してフィリピンに到達したのは1521年。はじめて上陸したのはホモンホン島だった。マゼラン一行はこの島に漁に来ていた住民と出会い、友好的に帽子、鏡、麻布と魚、バナナ、ヤシ酒を交換した。一行はそこからセブ島へと移動し、マゼランはこの島のラジャ(首長)フマボンと「血盟」の契りを結ぶ。
この航海を記録したピガフェッタによれば、一行は各所で酒食に招かれたが、人びとは「たいへん陽気でおしゃべり」「ものすごい大酒飲み」で、時には若い女性が打楽器を演奏してくれたりした。「(彼女らは)かなり美しく、そして色白だった」。フィリピン人をよく知る著者によれば、「陽気でおしゃべり。飲み食いを楽しみ、勧め上手で、エンターテイナー。何だか、今日のフィリピンの人たちとほぼほぼ同じようではないか」。
両者の出会いは、もちろん最初から友好的だったわけではない。セブ島に入港するとき、マゼランは和戦両様の構えを取った。船団の三隻は満艦飾を施して威厳を示し、戦闘隊形を取り、「全門の大砲を一斉に発射」した。フマボンも住民も「非常な恐怖」におののいた。その一方、フマボンも交易商人との扱いに通じていたからひれ伏したわけでなく、「港に停泊する船は、すべて税金を納めることになっている」とマゼランに告げる。西洋人がこの島にやってくるのは初めてだったが、セブ島にはすでにイスラム教徒のシャム商人も出入りし、ミンダナオ島やルソン島、ボルネオ島、中国、インドシナ半島などを結ぶ交易ネットワークのなかにあり、「ヒト・モノ・情報が集まるビジネスのハブ」になっていた。
マゼランと血盟の契りを結んだフマボンは、妻とともにカソリックの洗礼を受ける。このときの「老若男女を合わせて八百人」の改宗が、現在八千万人を超えてフィリピンが世界屈指のカソリック国になる端緒となった。そのフマボンがマゼランに、スペイン国王への臣従を拒んでキリスト教徒にならない首長がいると告げた。そのマクタン島の首長ラプラプを討つ、とマゼランは決めた。「マゼランは、西洋パワーを示威する絶好の機会と受けとめたに違いない。……西洋兵器の威力を、フマボンはじめ広く周辺地域の有力者や住民に見せつけることで、スペインに反抗すればどうなるかを思い知らせておくチャンスと見たのではないか」。
ところが、自信満々フマボンの加勢を断ったマゼランが手勢60人でマクタン島に向かったところ、1500人に囲まれマゼランはあっけなく殺されてしまう。その首長、ラプラプが「ヨーロッパ人の侵略を撃退した最初のフィリピン人」として民族の英雄になったのは、1946年の独立後のことだという。フィリピンはマゼランの死後、400年余にわたってスペイン、その後アメリカにも統治されたが、アメリカ統治時代でも教科書には「マゼランは原住民に殺された」とあるだけだった。マクタン島の公園にはスペイン統治当局がつくったマゼラン記念碑があるが、独立後に民族主義が強調されるようになった1951年、記念碑のそばにラプラプの立像がつくられた。今では警察や消防隊のワッペンにもラプラプが描かれている。
われわれが教科書的な記述でしか知らない事実のディテールがフィリピンを視点に描かれるのがこの本の面白さ。でもそれだけでなく、いささかトリビアになるがフィリピン人のアイデンティティーにかかわるいくつものエピソードに触れられているのが、また興味深い。
2021年はマゼランの航海から500年に当たり、フィリピンでもこれを記念した行事が開催された。そのポスターにはマゼランではなく一人のアジア人船員の姿が描かれている。そこからも「発見された」側からマゼランを見る視線の複雑さが感じられる。男の名はエンリケ。マゼランが以前マレー半島へ出征したとき連れ帰った奴隷で、エンリケはマレー語を話すのでフィリピンの住民(マレー語圏の一部)と話が通じ、マゼランの通訳を務めたという。ということは、エンリケはマゼランの奴隷としてマレー半島からスペインに渡り、さらにマゼラン船団の航海で大西洋と太平洋を航海してフィリピンにやってきた。マゼランはそこで殺されてしまうから、実は世界で最初に地球を一周した人物はエルカーノでなくエンリケということになる。マレー語圏ではエンリケを主人公にした小説や映画もつくられているという。
ところでフィリピンという国名は、マゼラン以後にスペインが送った遠征隊が、サマール島やレイテ島を「ラス・イスラス・フェリペナス(フェリペの島々)」と勝手に名づけたことから来ている。スペイン王フェリペⅡ世にちなんでのこと。だから独立後には、スペイン植民地時代を想起させるこの国名を変更しようとする議論が何度か起きている。
一方、「フィリピーノ(フィリピン人)」という呼称は、もともと植民地時代にスペイン本国出身者に対しフィリピン生まれのスペイン人を指す呼び方だった(地元民をスペイン人は「インディオ」と呼んだ)。フィリピーノはやがて地元や中国系の有力者と婚姻して混血し、19世紀半ばには「混血層も包摂してフィリピーノ・アイデンティティが広がり、存在感を増す」ようになった。彼らは「フィリピーノにもスペイン人と同じ権利を認めよ」と主張し、その代表がスペインによって銃殺されたホセ・リサールだった。リサールは現在、国民的英雄になっている。
もうひとつ、われわれの心をざわざわさせる話題がある。ジパングとはどこか、ということだ。ジパングという島は、マルコ・ポーロ『東方見聞録』のなかで極東の黄金の島として記述された。以後、世界地図には「Cipangu」「Zipangu」などとして描かれるが、場所は北半球の赤道付近であることが多い。「ジパング=日本」説は、17世紀にイエズス会士が唱えた説がヨーロッパで定着したものだという。しかし近年の研究で「ジパング=日本」説には矛盾が多いことが明らかにされている。そこで登場するのが「ジパング=フィリピン」説。古地図に描かれた黄金島も現在のフィリピンに近いし、金も産出する。ある日本人研究者は「黄金島はフィリピン諸島を中心にした多島海地域を指す」と結論しているそうだ。
われわれの知識やものの見方は、明治以来100年以上におよぶ近代化や教育のなかで、無意識のうちに欧米のそれを下敷きにしていることが多い。アジアの国々やそこに暮らしている人々について語るときも、それは言える。今は世界のいろいろな場所から、また欧米の内部からも西洋中心の歴史の「見直し」を図る流れが生まれている。この本も、そうした動きのなかの一冊として、穏やかにしかも面白く、われわれの眼を開かせてくれる。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





