VANから遠く離れて 評伝石津謙介【佐山一郎】
VANから遠く離れて 評伝石津謙介
| 書籍名 | VANから遠く離れて 評伝石津謙介 |
|---|---|
| 著者名 | 佐山一郎 |
| 出版社 | 岩波書店(312p) |
| 発刊日 | 2012.03.24 |
| 希望小売価格 | 3,360円 |
| 書評日 | 2012.05.11 |
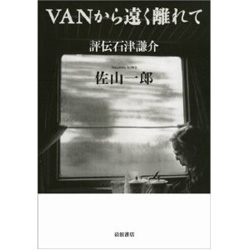
戦後、「VANジャケット」を率いて、青年の服装文化に大きな影響を与えた石津謙介の評伝である。今年公開された「三丁目の夕日’64」では主人公堀北真希がデートする相手はバリバリのIVYルックで身を固め、デートの場所は銀座みゆき通。団塊の世代よりも年上の東京オリンピックに大学生ぐらいだった人達にとってはVANが与えたインパクトの大きな流行だったと再認識させられる映像だった。石津謙介が「ヴァンジャケットの総師」や「アイビー・ルックの提唱者」と言われていた期間は十年から十五年間ぐらいのものだったのではないだろうか。
評者の認知していた期間で言えばもっと短い期間だったと思うのだが、服飾の領域だけにかかわらず若者文化としての発信をしていたからこそ大きな流行をつくりあげたと思う。しかし、著者の佐山はその限られた期間の石津謙介のみならず、石津の人生の全体像に迫りたいという気持ちで本書を書いたのではないか。
「・・明治末生まれの謙介はTPO(Time, Place, Occasion)の啓蒙などで、VANを愛する人々のゴッド・ファーザーとしての役割を引き受けていた。氏の提案するスタイルが男の理想や常識を生み出すことは判っていても、いつかどこかでそれを脱ぎ捨ててしまわぬことには少年期を終えることができなかったのである。それゆえこの伝記は・・・・VANという属性を相対化することによって浮かび上がるはずの何ものかを求めての(時間旅行)に近い。表題の通りで、いったんVANから遠く離れてみることなしに正確なアプローチは難しいと私は考えている。・・・」
佐山は石津の生誕からの精緻なトレースを開始する。それだけに本人・家族・関係者への多くのインタビューを実施し、関連書籍・雑誌・資料なども多岐に渡って分析されており、石津謙介と意見を異にする人たちの話も取り上げているところは評伝としての完成度を高めていると言える。
アイビー・ルックをどう捉えるのかという命題にいくつかの見方が紹介されていて面白い。写真家の峰谷秀人はアイビー・ルックについてこう語っている。
「アイビーはうんちくとご法度だらけのファッションです。自分で規則を遵守し、相手に対してはご法度がないか重箱の隅をつつくように探しまくる。・・・ある日ふと思いました。アイビー・ルックとライカは同じじゃないかと。ライカを持つとまずレンズを含め純正パーツという規則に縛られます。そして純正パーツにも『ボディと時代が違ってはいけない』というご法度に苦しめられます。・・・ライカを頂点とするLマウントカメラの宿命とTPOにつながる関係性である」
後年、石津はVANのブランド・コンセプトを「VANが最初にやったアイビー、あれはファッションではなく伝統的なスタイルなんです。だからVANは最低でも10年着られる。それが説得力をもったのです」と語っている。しかし、そのインタビューからも佐山は厳しい目を向けている。
「・・・その口調とは裏腹の動揺もかい間見てしまった。条件反射のようになっている連想---石津VAN-----高級そうな若者アイビー風俗-------背後にあるアメリカという信仰-----は同時に成功と誤算に彩られたVANの一般評価でしかない・・・」
ビジネスとしてみれば、ヴァンジャケットは購買層の世代をフォローしていくことに失敗しているのは事実である。「メンズクラブ」という男性向服飾雑誌とのタイアップを通して、車、スポーツ、ジャズなどアメリカ文化を紹介し続けた。しかし、アメリカに対する信仰に近い憧れはビートルズの出現とともにその勢いを失って行く。加えて、70年安保・ベトナム戦争は若者たちの視線をアメリカから背けさせることはあっても、そこから輝かしい未来を見つけることはなかった。そうした時代背景だけではなく、石津の考え方に反感も生まれていた。昭和四十年「ヨーロッパ退屈日記」を著した伊丹十三はIVYを否定的に語っていた。石津の言う「わたしたちは品物を売るより前に、まず思想を売るのだ」というビジネス哲学に対して、思想で生きる人達から多くの反発が出た。そのひとりが作家の夏堀正元である。昭和42年に書かれた文章が紹介されている。
「・・・これはキザなハッタリとして、こちらに嘔吐感をもようさせるような言葉である。だが、彼は一向に羞恥もなく、てらいもみせないで平然とおさまりかえっている。なるほど、最近の日本は思想がない。思想が乱れに乱れて、嘆かわしい状態にある。とはいうもののまさか『服屋が思想を売る』とは思ってもみなかった。そこまで日本の思想は安手になったということなのか。・・・それにしても、彼のいう思想とはたかだか服飾のイロハの常識にすぎないのではないか。・・・」
遡って、昭和十四年に石津は妻と子供三人とともに天津に行っている。戦時とはいえ、ある種の自由社会である租界が持つ文化は独特のものであったようだ。この天津で大川洋行という日本租界の洋品屋の営業部長から事業を広げ、各国租界の人々との交流を深めつつ服飾ビジネスの才覚を身につけ成功の味も知った。ここで体感した大陸的な人間観は石津謙介・昌子夫妻の将来の生き様に強く影響を与えた。終戦とともに、石津は英語・中国語・日本語が話せるということで米軍憲兵隊の手伝いをするなどして天津での生活を乗り切り、昭和二十一年には一家無事に帰国している。
そして、レナウンの前身にあたる株式会社佐々木営業部に籍を置き、昭和二十六年に独立を果たした。「有限会社石津商店」の誕生である。その後、VANという商標の起源や舞台俳優に商品を提供して宣伝に努めるなど興味が尽きないエピソードが続く。
昭和三十四年週刊サンケイの「怪物VANという阪僑」という特集でマスメディアに登場し、以降、昭和三十九年の東京オリンピックから昭和四十年代末ぐらいの十年間がVANのピークだったのではないかと思われる。この時期の日本は戦後の混乱を乗り越え、成長を果たしたものの直面した状況は大学紛争、七十年安保、ベトナム戦争という新たな混乱期であり、VANやJUN・Edwardsといった若者向けの服飾ブランドが林立していた時代から一挙に若者たちの「好青年を演じるファッション」が終焉を迎える時代に突入していく。それはジーンズが市民権を獲得していった時期に重なる。
服飾ビジネスという視点からすると明らかに、団塊の世代が学生から社会人になっていく時代をVANは乗り越えることが出来なかった。評者の体感としても、日本のビジネス・シーンにおいてはまだまだ服装は保守的であり、仕事着の観点から脱却していなかったという記憶が強い。「Brooks Brothers」や「J-Press」「Paul Stuart」といったブランドが堅実なビジネス需要をカバーしていた米国とは大違いで、必然的にそうした米国ブランドが大人向けに日本上陸を果たして行ったのは皮肉な現象である。石津が叩き込んだおしゃれ感覚を持った青年達はサラリーマンとして「予定通りVANから離れていった」のである。
昭和五十三年、ついにヴァンジャケットが倒産というニュースを社会人八年目の評者は感慨深く聞いた記憶がある。この倒産後の石津の活動は本書ではじめて知ることが多かった。天皇制に対する発言・食に関する発信、そして多くのイベントにも狩り出されるなど、石津謙介のスタイルを十分に貫いて生活していたようだ。その一つが、本書のトリガーとなった、平成二年「エスクァイア日本版:44年ぶりの天津再訪」という企画だ。
読み終えてみると、石津謙介とヴァンジャケットについて評者が知っていることは、ほんの一部分、ほんの一瞬でしかないと良く理解できる。しかし、高校時代のその一瞬の出会いから、今もリーガルの靴を履き、横浜に行けば元町のPoppyに立ち寄る65歳のオヤジが出来上がっているのも事実。VANのロゴの下に小さく書かれていた「 for the young and the young - at - heart」という言葉が心ならずも体内に残存しているということである。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





