物は言いよう【斎藤美奈子】
物は言いよう
| 書籍名 | 物は言いよう |
|---|---|
| 著者名 | 斎藤美奈子 |
| 出版社 | 平凡社(336p) |
| 発刊日 | 2005.3.17 |
| 希望小売価格 | 1600円+税 |
| 書評日等 | - |
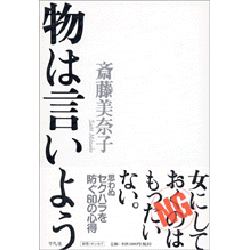
いま、斎藤美奈子ほどに痛快な文章を書く物書きはいない。この場合の痛快の「痛」とは自分流に解釈すれば、彼女の文章が的の中心を正確に射抜いているということ。だから誰かさんを俎上に載せている場合には、その相手にとってなんとも「痛」い。「快」は、その文章が読む者にとって喝采したくなるようなエンタテインメントに仕立てられているということ。
斎藤美奈子はここで、FC(フェミコード)というキーワードを提案している。FCとは、「性や性別にまつわる「あきらかにおかしな言動」「おかしいかもしれない言動」に対するイエローカード」のことだ。
「物は言いよう」は、FCに触れそうな政治家や物書きの発言・文章を取り上げて、「鑑賞のポイント」「FCチェック」「難易度」「心得」といった具合に論じた「実用書」。「実用書」というのは、次のような意味合いを指して言っている。「要は社交上の問題なのだ。あなたが自室で何をいおうと、何をしようと勝手だが、社会的な場では社会的なルールがある」。
「フェミコードは政治的な運動の道具ではないし、まして宗教上の戒律でもないから、意識のありようまではとやかくいわない」。「ただし、心の中と外は有機的につながっているから、外面だけ取り繕おうとしても、内なる意識が外にこぼれ出るのはよくあること。……家で妻を抑圧しといて、外で男女平等を標榜しようったって、そうはいかの塩辛だ。本音は日ごろの言動にポロリと出る」。
取り上げられた言動は60例。「「女の涙には勝てん」問題」「「女は家にいろ」問題」「「女は女らしく」問題」「「男はスケベだ」問題」「「女だからこそ」問題」「「女に政治はわからん」問題」「「女はだまっとれ」問題」という分類をみれば、ああ、あの発言だなと見当はつく。
「森喜朗「産まない女」発言」「太田誠一「元気な男」発言」「福田康夫「黒ヒョウ」発言」「西村眞悟「強姦魔」発言」「小泉純一郎「女の涙」発言」などなど、最近の記憶に残る発言はもれなく収録されている。
ここらへんの迷言妄言は取り上げられて当然といったものばかりだけど、この本の射程が長いのはそれだけではないこと。
男性社会に順応して生きてきた女性の言動がチェックされるかと思えば、他方で「業界」「党派」と化したフェミニズムの言動も批判される。かと思うとFCに敏感だと思われる物書き、池澤夏樹や大江健三郎にまでイエローカードが出される。
世代的にも若い世代から熟年まで、あらゆる年齢層がターゲットにされる。ただただ面白がって読んでいると、その矢は必ず読んでいる自分に向かっても飛んでくることになる。これがまた「痛」い。
僕にとって「痛」かったものを紹介しよう。ひとつは団塊=全共闘世代に矢を放った世代的なもの。流行の女性ファッションを批判した「どれも「女らしさ」の象徴みたいなアイテムばかり」(宮谷史子「「金曜日」流スローライフのすすめ」)という表現から、筆者が勧める「スローライフ」を取り上げて美奈子さんはこう断ずる。
「「スローライフ」は……70年代に流行った近代批評の今様バージョン、全共闘世代のリベンジ・ゲームみたいなところがある。効率主義からの脱却だ、豊かさの見直しだ、伝統への回帰だとかいってるけど、結局それは金と時間と精神にゆとりのある有閑階級の発想で、学生運動→市民運動と流れてきた層が、老境に入ってたどりついた「癒しの思想」に思えてならない」
「ブラジャーやガードルやオールインワンがいくら窮屈そうだと笑ってみても、「週刊金曜日」の、特に男性読者は痛くもかゆくもなく、結果的には若い女の「娼婦みたいな服」に眉をひそめる「保守的なおじさま」と何も変わらない。……「週刊金曜日」の読者に向かって、いま投げかけるべきせりふはコレだろう。「男よ、スカートをはいて会社に行け」」
いまひとつは、「僕」という一人称をめぐってのもの。東浩紀の「僕は僕の関心を惹いたものについてだけ、僕の得意とする方法で語りたいと思う」という文章を取り上げて、こんなふうに言っている。
「「ったく、僕僕僕僕、連呼しよって。よっぽど僕が大事なんだな」である。そんな風に感ずるのは、第一には彼らが自分語りに必要以上に熱心だからであり、第二には、当たり前だが、中性化された「私」ではなく、男のジェンダーが刻印された一人称=僕(ぼく/ボク)を使用しているせいである。……軽い甘えと幼さと感傷を含んだ僕(ぼく/ボク)には微妙に鈍感な感じがある」
雑誌(「噂の真相」)連載時に、この一文はかなりの反響を呼んだらしい。一人称に「僕」を使っている書き手が「もう「僕」を使わない」と宣言したり、美奈子さんになぜ「僕」を使うかをレクチャーしたり、「僕」から「私」に変えるきっかけがないと悩みを打ちあけたり……。
この本ではそんな後日談を紹介しながら、「みなさん、いいんですよ、気にしないでつかってください、「僕」。/「僕」の効用を、もちろん私は熟知している。「僕」は文章に浮力を与えるのである」と文芸評論家としてフォローしている。
かくいう僕も一人称は主に「僕」を使い、時に応じて「私」や「自分」を使いわけている。一時、「私」にしようとしたけれど、しばらくしてまた「僕」に戻ってしまった。「私」だと、それでなくとも硬いと自分で感じている文章がいよいよしゃっちょこ張ってしまって、いただけない。でも美奈子さんが指摘するように「僕」に「甘えと幼さと感傷」が孕まれていることも確かで、おおいに迷うのだ。
それにしても美奈子さんの啖呵は気持ちがいい。女だてらに(←NG!)、裾をくるっとまくって(←NG!!)、男勝りの(←NG!!!)胸のすくようなせりふを吐く。いまどきの男にはとても太刀打ちできない。
「大丈夫なのか、三浦雅士。自分で何いってるか、わかってる?」
(「このあたりの素直な見解は、いかにも若い女性研究者である」と書く山本博文・東大助教授に)「「このあたりの素直でない見解は、いかにも中年の男性研究者である」/なんて失礼なことを申し上げたら助教授は憤慨なさるだろう」
「一般論としての批判がいちばん「差別的」なのだ。ふんどし、落ちかかってるぜ」(大月隆寛に対して)
そんな小気味いい彼女のエッセーを楽しんでいるうちに、気がつけば読者は「実用書」であることを超えて、知らぬ間に斎藤美奈子流フェミニズムに洗脳されてしまっているのだ。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





