民族という虚構【小坂井敏晶】
民族という虚構
他の集団と区別するための幻想
| 書籍名 | 民族という虚構 |
|---|---|
| 著者名 | 小坂井敏晶 |
| 出版社 | 東京大学出版会(206p) |
| 発刊日 | 2002.10.10 |
| 希望小売価格 | 3200円 |
| 書評日等 | - |
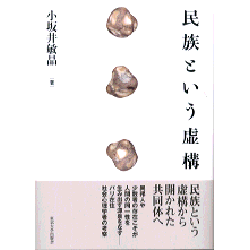
ずいぶんむずかしい本を読んでしまった。友人に面白いよと勧められたからだが、読みはじめてちょっと後悔した。勤め人を30年以上もやっていると、日々は雑用の積み重ねで過ぎてゆく。ものを考える、しかも抽象的にものを考えることなんかほとんどない。最後まで読んだのは、なかば友人への意地のようなものだった。そして読み終わって、読んでよかったと思った。
著者はまずはじめに、こう言っている。「民族同一性は虚構に支えられた現象だ」。つまり、僕らが何の疑いもなく使っている日本人とかフランス人とかいう場合の民族というものは、実はうそっぱちだということだ。
なぜうそっぱちなのか。それが、理解しやすい歴史的な文脈や社会的な文脈ではなく「認識論」的レベルで語られている。著者はパリ第八大学の助教授だそうだから、フランス現代思想の空気をたっぷり吸っているわけだ。
だから僕にこの本を「書評」などできるはずもない。その代わり、雑用と実用の詰まった僕の頭が(今この原稿も、仕事の合間に会社のパソコンで書いているのだ)、この本をどう読んだか、というよりどう誤読したかを僕なりに整理してみることにする。
普通、僕らが例えば日本民族というとき、日本人として共通の祖先を持ち、共通の血が流れ、共通の言語や宗教や文化を持っていると考えている。でもそれは、何の客観的根拠もないのだ、と著者はいう。なぜならーー。
言語。例えば著者の住むフランスでは、20世紀初めまで、フランス語以外にドイツ語、アルザス語、ブルトン語、バスク語、オック語、カタロニア語、コルシカ語を話すフランス人がいた。
宗教。例えばイスラエルは、世界各国から色々な宗教を信ずるユダヤ人が集まっているが、単一民族として認識されている。
血。例えばこの100年間に生まれたフランス人のうち、3割以上が外国出身者の親から生まれているが、彼らはれっきとしたフランス人である。
つまり共通の血、共通の宗教、共通の言語などというのは幻想なのだ。確かに、僕らが日本民族として共通に持っていると思っているものを、日本人はいつ成立したのか?日本語は?日本人の宗教とは?と突き詰めて考えてゆくと、最後にはあいまい模糊としたものになってしまう。にもかかわらず、日本民族というものがあることは疑えない。
民族というものに、客観的な根拠はない。そうではなく、ある集団が、別の集団と対立したとき、自分たちの集団を他と区別するために民族という幻想をつくりだす。その根拠とされるものは、血でも言語でも宗教でも、その時々で皆が納得でき、相手に主張できるものならなんでもよい。
そのようにして生まれた集団が、ひとつのまとまりとして、ある適当な時間を過ごせば、もともと多種多様だった集まりも自分たちはひとつの民族だと信じこむようになる。
著者の言い方を借りれば、こういうことになる。「人々を対立的に差異化させる運動が境界を成立させ、その後に、境界内に閉じこめられた雑多な人々が一つの国民あるいは民族として表象され、政治や経済の領域における活動に共同参加することを通して、次第に文化的均一化が進行するのである」。
雑用と実用頭の僕は、こうした現代思想っぽい表現より、次のような鋭い指摘に刺激を受けた。
「「ユダヤ人国家樹立に際して最も強い原動力となったのは、実は疑いなくヒトラーなのだ」と、あるイスラエル人歴史家は述べているが、民族の誕生するからくりがこの言葉に集約されている。ユダヤ人を救おうと努力してきたシオニズム運動が成就する上で最大の貢献をしたのは、皮肉なことに反ユダヤ主義だった。しかしそれは単なる偶然ではない」
もっとも著者はこのような主張を、民族という虚構から目をさませ、と政治的文脈で語っているのではない。そうではなく、人はそもそも虚構なくしては生きられないものだと言っている。とは言っても、民族の誇りを回復せよといった右翼的な文脈で語られているのでもない。もっと根源的に、人間が生きていられるのは虚構に支えられているからだ、と言うのだ。
ここから先の議論は、正直言って分かりにくい。いよいよ認識論の深みに入ってゆく。興味ある人は現物に当たってもらうとして、僕が面白いと思ったのはルソーの社会契約論に触れた部分だった(僕も遥か昔、政治学専攻の学生としてルソーを読んだことがあったので)。
ルソーの社会契約論は近代民主主義の原点とも、逆に全体主義の危険をはらむ理論とも言われている。そのくらいはぐうたら学生だった当時の僕にも理解できたが、この本が独特なのは個人主義(政治的には民主主義)と全体主義を対立するものとしてではなく、個人主義が成立したがゆえに全体主義が出てくると考えているところだ。
社会契約論を生んだ近代の社会は、個人の自由や主体性を重んじて、村や教会、職人のギルドといった伝統的な共同体を解体した。別な言い方をすれば、「神」という虚構を捨てて、個人と社会を合理的に結びつけようとした。その結果、個人と社会(国家)の間には中間的な媒介がなくなり、両者が直に向かい合うことになった。
「近代政治哲学は、共同体の<外部>に位置する神という虚構に頼ることなく、社会秩序を合理的に根拠づけようとした。しかしそのように虚構を完全に排除すると、各個人の生命・財産をお互いの横暴から守り、平和共存を図るための唯一可能な手段として、警察権力を始めとする、あからさまな暴力しか残らなくなってしまう」「個人主義を貫徹させようとしたからこそ、ルソーの理論は全体主義に向かわざるをえなかったのだ」
民族は、こうして個人と社会を直に対面させないための虚構として人間には必要なものなのだ、と著者は言う。民族という虚構なくして人は生きられない。しかし民族が虚構だとしても、その虚構は現実におびただしい対立や差別や流血を生みだしている。
それを避けるためにはどうしたらいいのか。著者は社会的・歴史的文脈で議論を展開してはいないから、具体的な提案をしているわけではない。でも、著者の議論をそうした文脈に置きかえてみると、次のようなことになるかもしれない。
民族のアイデンティティーに根拠がない以上、その中身は時代や場所によって変化する。問題は、構成員にとってその変化が強制されていると感ずるか、自発的と感ずるかである。強制されていると感ずれば、民族のアイデンティティーは失われたと考えるだろうし、自発的に変わったと感ずるなら、変わったにもかかわらずアイデンティティーは保たれている、と考えるだろう。
つまり、少数民族が多数民族に強制される形ではなく、自ら変化したい方向に変化できることが大切なのだ。自分のアイデンティティーが保たれていると感じていれば、異文化・多数派文化に対する拒否反応は弱くなり、異文化に接して自らが変わっていくことも可能になる。そのことによって多数派も、実は少数派の影響を大きく受けて変わってゆくのだ。
このような考えを、著者は多民族・多文化の共生とも違う第三の道と考えているようだ。多数民族と少数民族が互いに与える影響についても、常識とは逆に、少数派が多数派に与える影響・変化のほうが大きいという「実験」結果を示している。
しかし、それはあくまで少数の人間集団で試みた実験であって、少数派と多数派の割合が圧倒的に違う場合、例えば人口70万人の在日韓国・朝鮮人と1億人の日本人を考えてみれば、言語的・文化的にはすでに少数派の在日は日本人に溶けてしまっているといっても過言ではない。著者の議論を借りれば、多数派の日本人が法的にも日常的にも彼らを差別しているからこそ、在日韓国・朝鮮人の民族意識が辛うじて残っているのだ。
少数派と多数派が互いに影響を与えながら変わってゆく「開かれた共同体」という未来図は、確かに美しい。でもそれは、ゆっくりと少数派が多数派に溶けこんでゆくのを待つ百年河清の「ソフトな支配」とも言えるかもしれない。それが新しいルソー理論にならない保証はないのではないか。僕は僕なりの経験から、美しい政治論を素直には信じないことにしている。
いま、著者の住むフランスなどEU諸国やアメリカでは、少数民族の言語や文化を尊重した多文化・多民族主義が取られている。例えばフランスに暮らす少数民族の人々の姿には、堀江敏幸の深く静かな叙述で触れることができるけれど、著者はそうした多文化を認める政策が、結果としてはゲットーを生みだし少数派を隔離していると言う。
その経験が、多文化主義を超えようとするこうした試みを生みだす素地になっていることは確かだろう。でも、少数派に対して多文化主義以前の抑圧的な政策を取っている日本に住む僕らの感覚からは、美しい未来図よりはゴッタ煮の混在のほうがましなんじゃないの、と思ってしまう。
さらに言えばーー。このような議論は、著者や僕たちが住む、政治的に安定した「北」の諸国でのみ通用するものだろう。現に民族が血を流しているコソボやルワンダやアフガニスタンでは、こうした議論以前の、民族の生存を賭けた争いが繰り広げられているのだから。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





