東海道ふたり旅【池内 紀】
東海道ふたり旅
| 書籍名 | 東海道ふたり旅 |
|---|---|
| 著者名 | 池内 紀 |
| 出版社 | 春秋社(352p) |
| 発刊日 | 2019.01.07 |
| 希望小売価格 | 2,592円 |
| 書評日 | 2019.02.26 |
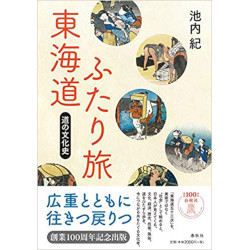
本書は歌川広重の「東海道五十三次」に表現されている宿場の風景を読み解きつつ、生活、文化、社会など、街道にまつわる文化をまとめたもの。従って、タイトルの「ふたり」とは著者池内自身と広重ということになるのだが、読み進んでいくと、もっと巾広く浮世絵に登場する旅人たちを含めて「一人ではない」という意味の様にも思えてくる。
広重の浮世絵に描き込まれている人物や風景に対する著者の繊細な視線は、驚くばかりに図柄の細部を掘り下げている。広重の東海道五十三次を「鑑賞」するのではなく、虫眼鏡で「観察」したと言っている様に、その緻密さは圧倒的だ。これに、著者の旧東海道と宿場を旅した体験と街道の成り立ちといった歴史的知識が加わる事で、江戸から京都までの五十三次の中から三十七宿と日本橋と三条大橋を題材として、当時の文化を紡ぎ出すという旅の一冊になっている。この東海道の旅は、日本橋発のいわゆる「京のぼり」の旅である。
さて、本書の第一章は五街道の起点であり広重の五十三次のトップを飾る日本橋「朝之景」を紹介しつつ、今の日本橋を語っている。1603年に架橋された日本橋が時代の変遷とともに、その風景が変貌してきた経緯を象徴的に表現している。
「南の木戸から橋を正面にとらえた構図で、左に高札場、右は木戸に隠されているが罪人のさらし場であった。……橋の北詰は日本一威勢がいいといわれた魚河岸で広重では、仕入れてきた江戸前の鮮魚をたらいに入れた棹振り(行商人)が今しもそれぞれのお得意先へと向かうところ。……橋には擬宝珠が見えるこれは「格の高い橋」の印だった。……関東大震災で魚河岸は築地に移り、日本橋を取り巻く風景は徐々に変わっていったものの、昭和39年高速一号線が通ることによって、風景から日本橋が消えた。……ここに日本の名だたる橋が消滅したことを、誰も何とも思わなかった。以来、日本橋は橋であって、橋以下のものになり果てた」
私の旧東海道歩きの旅は、考えてみれば残されているもの(遺構・遺跡)を辿って歩いていたと思う。その意味では、本書の「広重の五十三次」を友として歩くという視点は読者に歴史や文化を示すだけでなく、同時に失ったものを示しており、私の街道歩きとは逆の発想だ。
広重の浮世絵を宿場ごとに追いながら本書は章を進めて行くが、「広重の浮世絵が大人気を博したのは哀愁をおびる風景の中に小さな物語が封じ込められていたからである」とその特徴を著者は語っている。広重の絵には自然風土だけでなく、食べ物や土産物といった特産物が描き込まれていることも多い。丸子宿の「名物とろろ汁」、その先の宇津野谷峠の「十だんご」など。旧道歩きをしていても土地の名物を食べ歩く楽しみは広重の時代と変わりない。そして、旅人は街道沿いの茶屋で名物を食べながら、行く道筋で信仰、産業、地勢、風習などを見聞きして歩き続ける。加えて、広重が描いているのは「旅する人」だけではなく、「土地の人」「職人」「人足」が登場して物語を創り上げている。
それらを著者の独特の視点から、連想を広げていくというのが面白い所。例えば、庄野宿の「白雨」は「五十三次」の中では数少ない雨の風景をモチーフとしている。当時、旅人は晴雨に係わらず笠を常に身に付けていたのも、江戸時代の旅では三日を開けず雨の心配をしていたからである。当時の旅の厳しさを見て取るのは私の様な凡人で、この絵から著者の発想は「ふんどし文化」へと飛んでいく。
「この絵を社会の写し絵として眺めてみた時、奇妙なことに気付く。雨降りのシーンで良く判るが、上半身はそれなりに包んでいても、下は恐ろしく無防備である。尻丸出しは雨のせいだけではなく、ほぼ常時そうだったことは日本橋の棒振り(行商人)や藤沢の問屋の前の人足たちの姿からも見て取れる。……こうした職人や飛脚・人足たちの仕事着は冷え性の元であり平均年齢30才という当時の早死の要因だったのではないか」
広重のモチーフ選びの特徴も色々あるが、街道を歩いていく旅のシリーズということもあり宿場の商家をあまり描かれていない。例えば、小田原宿は華やかな街並みでいくらでもモチーフが得られたであろうに、広重が描いたのは宿場の風景を一切無視して、宿場の手前にある酒匂川の徒渉の風景を描いている。その点を著者はこう語る。
「今、小田原は旧宿場らしい風情は感じられない町並みが続く。小田原が歴史的建造物の保全に冷たかったということではない。米軍の空襲で焼き払われた結果である。昭和20年8月15日の終戦の朝、アメリカ軍のB29の大編隊が残った全ての爆弾を投下していったという。400軒に及ぶ旧宿場の建物は焼き尽くされた。……そんな浮世の後世を広重は予見していたのかも知れない」
確かに、私が小田原を歩いた印象は旧道と言いながらも古い町並みは感じられず、拡幅された道が続いていたことを思い出す。広重が予見していたかどうかは別としても、こうした歴史的事実を突きつけられると、街や社会は100年単位で徐々に変化するというだけでなく、一夜にして変化させてしまうという悲劇もあるという事だ。
江戸時代、一本道の宿場を棒に見立てていて、入口・出口を棒鼻と称し四角い柱が建てられていた。藤川宿の絵が「棒鼻之図」と題されている理由だが、そこに描かれている図柄は広重の五十三次の中で私が一番好きなモチーフである。この絵を著者はこう語っている。
「幕府に馬を献上する一行が着いたところで、宿の町役人がかしこまって出迎えている。旅人も同じく土下座の姿勢を取らなければならない。犬が三匹いて、二匹は取っ組み合いをしているが、もう一匹は人間と同じく座ってお出迎え」
この絵に広重の洒脱さが良く出ていると思う。馬の登場も二宿先の知立宿は馬市で有名であったことなどからも上手いモチーフだと思う。そして、著者は馬と人間との係わりを馬の原種に遡って説明していて、「世界的に言えば、馬の歴史は兵器や乗り物として活用してきたことから、馬には走る能力が要求されて来た。しかし、日本の街道では荷を運ぶ馬もポクポクと人間の歩調に合わせる。そして日本では街道を馬は走らない」という視点は日本的と言ってしまえばそれまでであるが、そこから馬子唄が生まれたという指摘にもう一段興味が深まるというものである。
そんな道の文化のエピソードが本書では数多く語られている。歩いているだけでは得られない感覚を楽しめる。私が歩いた旧東海道の印象は日本橋から歩き始める「京のぼり」の方向風景がイメージとして残っている。例外的に、私が振り返って見た地点は薩埵峠の頂上で由比の海岸線から富士山を望んだくらいかもしれない。例えば宿場の商家の看板は京都から江戸に向かっては漢字表記、江戸から京都に向かって歩くと看板は「かな表記」である。こうした上りと下りの表記の違いが有るのは橋の名前も同様で、道路起点から渡るときは橋の名前は「漢字表記」であり、逆に道路起点に向かって渡るときは「ひらがな表記」の橋の名前が書かれている。同じ坂を歩いても上りの景色と下りの景色はまったく違うように、歩く方向は旅の風景の違いを作りだす。この10年間で色々な街道を一人で歩いて来た。その時の気分に従って歩く楽しさは、一人旅の自由度と自己責任が根底にあると思う。
「歩きながら考えるのは、こよなく楽しいことだった。連想が膨らんで、連想の糸が思いがけないことに結びつく」という本書の一文がこころに響く。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





