津波の霊たち【リチャード・ロイド・パリー】
津波の霊たち
| 書籍名 | 津波の霊たち |
|---|---|
| 著者名 | リチャード・ロイド・パリー |
| 出版社 | 早川書房(336p) |
| 発刊日 | 2018.01.25 |
| 希望小売価格 | 1,944円 |
| 書評日 | 2018.12.16 |
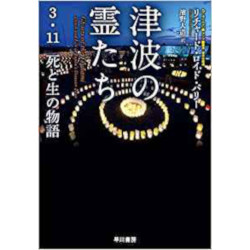
ブック・ナビで取り上げる本はずっと新刊本を対象にしてきたけれど、ここ2年ほどはときどき旧刊も取り上げている。書評のプロではないので幅広く目配りするわけでもなく、何冊か読んでも心が動く本が見つからない月がある。新刊ばかり読んでいるわけでもないので、そんなときは旧刊でも面白かった本について書くことを主宰者から許してもらった。『津波の霊たち 3.11 死と生の物語』も、そんな一冊。
書店でこの本を見てリチャード・ロイド・パリーという名前に見覚えがあった。カバー袖の著者紹介を見ると、ブック・ナビでも取り上げた『黒い迷宮 ルーシー・ブラックマン事件の真実』の著者。英国『ザ・タイムズ』紙の東京支局長で、20年以上東京に暮らすベテラン・ジャーナリストだ。
原著『Ghosts of the Tsunami :Death and Life in Japan’s Disaster Zone』は2017年にイギリスで出版された。2011年3月11日の東日本大震災以来、6年の歳月をかけて粘り強く現地に通い、何人もの被災者と信頼関係を築いたからこそ生まれた仕事。震災と原発事故の関連本は直後こそたくさん出版されたが、このところ書店の新刊棚で見かけることがめっきり減っている。だからこそ、被災者のその後と現在を追いかけたこの本には大きな意味がある。また『黒い迷宮』でも日本の裁判制度の奇妙さが指摘されていたように、「外部の目」から震災後のこの国がどう見えるかという興味もあった。
本を開いたのっけから、地震と津波で18,000人以上の死者が出たことを「長崎への原爆投下以来、日本で起きたひとつの災害・事故による死者数としては過去最大」という表現に出くわす。あらゆる家屋と車と樹木を飲み込んだ津波が引いた後の何もない風景から、広島・長崎の惨状を思い浮べた人は多いはずだ。本書でも被災者のひとりがそう語っている。でも僕の記憶する限り、テレビでも新聞・雑誌でも津波後の風景を広島・長崎を引き合いに出して語る場面に出くわしたことはない。広島・長崎を参照することは、日本人ならば広島・長崎に対しても津波の被災地に対してもどこかためらいの感情が働くからだ。でも「外部の目」でそう指摘されると、そうか、これは歴史的に見れば長崎以来の惨事なのか、と小さく納得する。
本書には大きな流れがふたつある。ひとつは、宮城県石巻市大川小学校で犠牲になった74人の生徒とその遺族の物語。もうひとつは、震災後目立って増えた被災地での心霊現象や幽霊譚や憑依と、その除霊を行った僧侶の物語。互いにまったく別の次元に属する事柄ながら、微妙にからみあい、ふたつの方向から被災地の「死と生」が語られてゆく。
著者は大川小学校で亡くなった生徒の母親たちに繰り返し会い、話を聞いた。そして、「津波の生存者たちから、全員の悲しみが異なるということを私は学んだ」。ある母親は娘を失ったが、家族と家は無事だった。別の母親は子供と家を失っていた。また別の母親は、家族全員と家を失った。そしてそれぞれのグループのなかでも、遺体が早く見つかった者といつまでも見つからない者のあいだには「残酷な区別」があり、「友情や信頼関係の破綻」があった。
末娘の千聖(ちさと)ちゃんを失った紫桃さよみさんは、間もなく娘の遺体と対面できた。「眼には泥がついていました。タオルも水もなかったので、私は千聖の眼を舌で舐め、泥を洗い落としました。それでも、きれいにすることはできませんでした。泥がどんどん出てくるんです」。遺体を埋葬した紫桃夫妻は、次のステップへと進んだ。なぜたくさんの教師がいた学校で74人もの生徒が死ななければならなかったのか、という疑問だ。同じように子供を失った遺族とグループをつくり、地震が起きてから津波が押し寄せた51分の間に学校で何が起こっていたのか、子供たちはどのように死んだのかを調べはじめた。
平塚なおみさんは娘の小春ちゃんを失ったが、いつまでも小春ちゃんと対面できなかった。津波から3カ月たち、いまだ遺体が見つからない子供は10人ほどになったが小春ちゃんはその一人だった。捜索隊の規模が縮小されたとき、中学校の英語教師であるなおみさんは重機オペレーターの資格を取り、重機を借りて自分で泥をかきわけ娘を探しはじめた。平塚さん以外にも、自分で重機を操作して子供を探しつづける父親がいる。小春ちゃんの遺体は11年8月に見つかったが、この本が出版された17年現在でもまだ重機を操作して子どもを探しつづける親がいることを著者は記している。
大川小学校で何が起こったのかを調べはじめたグループの行動は、やがて訴訟に発展してゆく。校庭に接した裏山があり、何人かの生徒が「先生、山さ上がっぺ」と訴えたのに、なぜ北上川沿いの堤防に避難することになって津波に襲われたのか。教師たちのうちただ一人生き残った教諭が、説明会で本当のことを語らず、その後、姿を隠し何も語らなくなってしまったことへの怒り。当日、不在だった校長が保身と官僚的な答弁に終始していることへの怒り。そんな怒りと、なにより「子供たちの最期の姿を知りたい」思いが彼らを支えた(地裁判決は遺族の勝利だったが、生き残った教諭への証人尋問要請は却下された)。
大川小学校の遺族をめぐるこうした流れのなかに、突然のように心霊現象をめぐる物語が挿入される。宮城県内陸部の禅寺・通大寺の金田諦應住職の元へひとりの男がやってきた。男は地震と津波の被害を受けていなかったが、家族を乗せ車で被災地の様子を見にいった。途中でショッピングを楽しみ、被災地の浜辺をアイスクリームを食べながら歩いた。車のフロントガラスに、制止されないよう「災害援助」の嘘の貼り紙をしていた。その夜、男は突然に飛び上がって四つん這いになり、畳と布団を舐め、獣のように身をよじらせて「死ね、死ね、みんな死んで消えてしまえ」と叫んだ。さらに表へ出て「みんなあっちにいるぞ。見ろ」と絶叫し、「あんた方のところに行きます」と叫んで畑をさまよった。家族が連れ戻したが、身悶えと叫び声は三晩つづいた。
金田住職が男を本堂に座らせて般若心経を唱え、お清めの水を振りかけると、男は我に返ったという。男が軽い気持ちで被災地を見物に行き、その現実にショックを受けた罪悪感が、おそらく憑依を引き起こしたのだろう。生き残った者は多かれ少なかれ死者に対する罪の意識を持たざるをえない。金田住職は他の僧侶たちと、被災者の話に耳を傾ける「カフェ・デ・モンク」を組織して被災地を回った。そこでは男のような憑依や、心霊現象、幽霊を見たという話がたくさんあった。
著者は金田住職だけでなく被災地の牧師らにも話を聞き、こんな言葉を引き出している。「多くの人が幽霊を見たと訴えているのは、トラウマのせいなんです。幽霊を見たを話していますが、実際には家庭でのトラブルのことを話しているんです」「私は霊魂の存在を信じていませんが、誰かが幽霊を見たと言うなら、それでいいんです。それ以上詮索する必要はありません」。
著者は立場と利害の異なるたくさんの被災者に話を聞き、あたうかぎりその人たちに寄り添って記述を進めている。一方で、絆の強い共同体の裏側で何が起こっているかもきちんと見つめている。大川小学校では避難してきた地区の組長が「津波の心配はない」と言い張り、教頭も組長の意見を無視できなかったこと。自身被災者であり、個人的には心優しい人々であるのに、組織の一員となるやお役所言葉に身を隠す教育委員会の職員。生き残った教諭の説明の矛盾を指摘した住民が経営する自動車整備工場へ、証言のあと公的な仕事が来なくなる「村八分」が起こったこと。霊能者を騙って金をかすめとる者たちが出現したこと等々。
著者はきわめて冷静で、どんな人間にも公平な態度を保っているけれど、「外部の眼」が思わずその冷静さの殻をぶちやぶってしまうこともある。たとえば、こんな記述。「私としては、日本人の受容の精神にはもううんざりだった。過剰なまでの我慢にも飽き飽きしていた。……日本は平穏な心と自制心に満ち満ちていた。そんな日本にいま必要なのは、紫桃さん夫妻……のような人達だった。怒りに満ち、批判的で、決然とした人々。死の真相を追い求める闘いが負け戦になろうとも、自らの地位や立場に関係なく立ち上がって闘う人々だった」。次の瞬間、パリーの筆はまた冷静さを取り戻すのだが、こんな感情の爆発がまた著者の個性を浮き上がらせる。
震災の記憶の風化が言われる。震災を伝える遺構の取り壊しもつづいている。この本を読んで、考えたことがある。記憶を持ちつづけ、伝えるとは、まず「その時」「その後」に何が起き、何が起こっているかの事実を知ること。いっときでいいから被災した人々の立場に立ち、その場から世界がどう見えるかを想像してみること。その作業に本書は役に立つ。今年読んだ最高のノンフィクションだった。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





