徒然草Remix【酒井順子】
徒然草Remix
| 書籍名 | 徒然草REMIX |
|---|---|
| 著者名 | 酒井順子 |
| 出版社 | 新潮社 (205p) |
| 発刊日 | 2011.11.22 |
| 希望小売価格 | 1,470円 |
| 書評日 | 2012.02.08 |
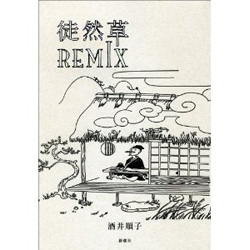
徒然草に接するのは何十年ぶりだろうか。受験勉強の名残として冒頭の文章だけはそらんじているものの、著者、吉田兼好の人物像にまで思い馳せことはなかった。本書は「Remix」と題している通り稀代のエッセイストである兼好と徒然草を素材として酒井順子が兼好像を現代の目線から探り出していこうというもの。結果、兼好はイキイキとした生身の人間として表現され、同業者(エッセイスト)としての酒井の感性も伝わってきて面白く読んだ。
酒井があの「負け犬の遠吠え」で脚光を浴びたのが2003年。未婚・未出産という女性層を「負け犬」と称したこの作品で声高にそうした女性を誹謗したり、逆に無理な論理で擁護するということもなく、彼女たちへのエールを送るという姿勢が広く受け入れられ、その年の流行語大賞にも選ばれてから10年近く経った。課題に向き合う間合いの上手さが著者の特徴だと思っているのだが本書でもそうした良さは生かされていて兼好への理解を押し付けがましくなく、自身の意見を主張していて、いい意味の軽さ、歯切れの良さが出ている。
全体の構成は徒然草の中で使われている代表的な言い回し、例えば、「あらまほし」「あはれ」「をかし」「つれづれ」などや、「女」「老い」「子供」「自慢」といったカテゴリーを採り上げて、各段での表現を丁寧に積み上げ、兼好の本音を掘り下げている。また、特徴的な形式として「清少納言」をもう一人のエッセイストとして登場させていることだろう。酒井が「自分より千年年上の女性」と表現したりしているぐらいだから、かなり読み込んだ対象の人物。平安時代の清少納言、鎌倉・南北朝の武家台頭期の貴族の身分から出家した吉田兼好という異なった時代の二大エッセイストを並べて擬似対談をやらせるなど手が込んだ表現をとっているとともに、読み進んでいくと、そこに三人目のエッセイストとして現代の酒井順子が透けて見えてくるというのが本書の仕掛けである。
「つれづれなるままに、日くらし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。」というかの冒頭の文章で、酒井は「あやしうこそものぐるほしけれ。」というフレーズこそ、兼好が発している唯一真実の言葉と言っている。それは兼好が30歳で出家したとか、徒然草はさみだれ式に書き残したものを後年まとめたのだとか、そもそも人に読まれることを想定して書いたものではないことなどの見方を踏まえつつ、兼好の「人の嫌な所をよく判ってしまう」という性格や、そこから来るある種の孤独感の表れとして、この部分を次の様に解釈している。
それは「何をしているんだかなあ、俺」とでも表現すべき「ひねりの入った孤独の客観」というのが酒井の主張である。孤独という言い方が強いとすると、人嫌いとでも言うべき兼好の性格を見ているのだろう。清少納言の場合は、孤独さえ「いとおかし」としてしまうような、あっけらかんとした楽天性がある。こうした違いなど、兼好vs清少納言という比較が随所に飛び出してくるのが本書面白さのポイントの一つである。
「随筆という表現手段をとった二人の資質には共通した部分がある。・・・しかし、そこには決定的な違いもある。・・・男好みの、男ならではの感覚がそこには満ちている・・・・この作者(兼好)の心の中には常に『○』の札と『×』の札が用意されているのだ・・枕草子においても、○と×の区別はくっきりとついています。・・・・『心ときめきするもの』の後につづられるのは清少納言が『○』と思っていることの数々。対して『見苦しきもの』のあとには『×』の物事が続く。徒然草の○と×の処理法とはそこが違う。兼好は・・・『これは○だがこちらは×だ』とか○と×を感じた理由を説明して、『だからやっぱり人間こうあるべきなんですよ』と意見を提示する。この手の男性は今でもしばしば見られる。好き嫌いを言いっぱなしにせず『べき論』もつい語ってしまう・・・・」
曖昧な発想は抱かず必ず判断を下す。そこに読者は引き付けられる。それが徒然草の魅力であるという酒井の評価に納得しつつも、「仏門に入った兼好でさえ『べき論』を振り回して、やっぱり男ってやつは・・・・」という素直な感覚を示されてしまうと、理屈っぽい団塊の世代男子としては忸怩たるものがある。
もう一つのポイントは、時代背景の違いによる面白さと兼好のエッセイストとしての素直さに対する見方である。和歌詠みの兼好は当然のことながら、平安の雅な王朝文化に支えられた和歌全盛時代を最上としていたものの、自分が生きている時代に、野蛮な田舎者(東国武士)が幅を利かせる世の中になっていくことに対して無念に思う気持ちは徒然草全体を覆っている感覚だ。その前提で、現代の我々からするとギャップを感じる部分を酒井は解説している。
まず、「心にくし」という言葉。酒井は現代人としてこの言葉は、ほめ言葉であり、相手のしたことは気が利いていて「一本とられた」感を抱いたときに使うものとしている。片や、兼好はこの「心にくし」という言葉を、ほめ言葉であると同時に「一本とられた」というよりも相手の知的な部分や都会性・文化性に対する尊敬と「もっと知りたい」という気持ちを込めた称賛であるとしている。この知的と都会性に対する兼好の「○」感は、他の言葉で置き換えると「身分」であったり「いにしえ」という言葉によっても徒然草の中で表現されている。
ただ、そうした兼好の「○」感を他者に対するプラス感情として素直に表現しているところを酒井は評価している。他人の悪いところや嫌な所に対して人並み以上に敏感に気づいている兼好であるが、同時に良いところにも気づく才能を持っていたからこそ、徒然草が後世も人々に好んで読まれる随筆になったとの解釈は納得感がある。
また、兼好の現実主義者としての側面を明確に表しているところとして、第百十七段が示されている。そこには、「・・・よき友三つあり。一つは物くるる友。二つには医師(くすし)。三つには智恵ある友」とある。「あわれ」や「をかし」の世界からかけ離れた、あまりの現実主義というか、情緒のないストレートな表現に圧倒される。
読み終えて、文化や時代背景をどんどんそぎ落としていった先にある兼好の人物像になにか違った見方が出来たように思えた。日本文学を代表する「徒然草」のガイド・ブックとして一癖あるものの面白い一冊に仕上がっている。なにしろ、帯のコピーは「徒然草は枯れてない。同業者の視線で読めば、兼好の肉声が聞こえてくる。・・にじみ出る自意識。あふれ出る自慢話。」とある。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.


