贖いの地【ガブリエル・コーエン著】
贖いの地
町の描写に命をかける風俗小説
| 書籍名 | 贖いの地 |
|---|---|
| 著者名 | ガブリエル・コーエン |
| 出版社 | 新潮文庫(460p) |
| 発刊日 | 2003.5.1 |
| 希望小売価格 | 705円 |
| 書評日等 | - |
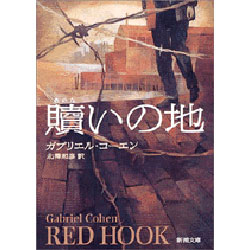
僕がミステリーを読む楽しみのひとつに、地図を手元に広げての「脳内映画」と一人で勝手に呼んでいるやり方がある。
小説の頭から100ページくらいまで、文章に出てくる公園や市役所、病院といった建物、それから街路の名前を片っ端から地図で確認していくのだ。はじめは読むリズムが寸断されるし面倒なのだけれど、ある程度がまんしてやっていると、そのうちに街のかたちがくっきりと脳内スクリーンに映しだされ、ああ、いま主人公の車はこの角を左折して北上しているのだな、と分かるようになってくる。
脳内映画を楽しむには、いくつかの条件がある。まず、それが警察小説かハードボイルドであること。というのは、これらの小説は街のディテールを描写することが、場合によっては犯人探しやナゾ解きより大切な要素になっているからだ。警察小説やハードボイルドは、街と、そこに暮らす人々のリアルな姿をうつしだす良い意味での風俗小説なのだ。
もうひとつの条件は、舞台になっている土地について、多少の情報があること。情報は映画や小説でもガイドブックでもいいし、もちろん実際に行ったことがあれば、それでもいい。もっともあくまで「多少」であって、まったく情報がなくては街をイメージする手がかりがないけれど、実際の街を知っていると逆に想像する面白みに欠ける。
さらにもうひとつ、適当な地図を手に入れること。僕はランド・マクナリー社の都市地図を使っている。この地図は、都市のどんな短いストリートにも名前が入っているし、建築物や公園などもあわせてインデックスがついている。もっともこいつは詳しすぎて、実際の町歩きにはあまり役に立たない。
ニューヨークのブルックリンを舞台にした警察小説である「贖いの地」は、僕にとってこの条件をすべて満たした作品だった。このところ、アメリカでもプロファイリングや科学捜査の出てこない昔ながらの警察小説やハードボイルドは、あまり書かれなくなっていると聞く。そんななかで、久しぶりに脳内映画を堪能できた。
まず、ブルックリンというところがいい。マンハッタンならどこにどんな建物があるか、町並みをある程度は知っているけれど、ブルックリンには一度しか足を踏みいれたことがない。それも観光客としてブルックリン橋を歩いてわたり(ウォーカー・エバンスの素晴らしい写真に惹かれて)、橋のたもとのカフェでお茶を飲み、あたりをちょっと歩いただけの経験だ。
あと僕にとってブルックリンの情報といえば、ずいぶん昔に読んだ「ブルックリン最終出口」という小説、それにスパイク・リーの何本かの映画ぐらいのものだ。ブルックリン・ハイツの褐色砂岩の住宅街を舞台にした恋愛映画を見た記憶もあるが、題名も役者も思い出せない。いわば適度の情報。
小説の冒頭、死体がころがっているのはガヴォナス運河の岸辺である。地図で探すと、ガヴォナス運河は港から1マイルほどでどんづまりになっている、過去の遺物のような運河だ。
「ガヴォナス運河は胆汁を思わせる緑色だった。昔、ブルックリンの子どもたちは、そのせまい堤防から叫び声としぶきをあげて跳びこんだものだが、隣接する工場群から一世紀以上にわたって流れこんだ未処理下水と汚染物質のせいで、ある種の藻と、キリーフィッシュと呼ばれている小さくてひねくれた種をのぞいて、あらゆる生物は水には住めなくなっていた」
いい出だしだなあ、と思う。「胆汁を思わせる緑色」。こういう描写一発で、僕は小説世界に引きずりこまれる。地図を見ると、ガヴォナス運河はレッド・フックと呼ばれる地域を流れている(原題「RED FOOK」)。かつて港として栄え、イタリア人、アイルランド人、ポーランド人、ロシア人移民などが住んだ下層労働者の町。主人公の刑事は、ここで育ったユダヤ系ロシア人だ。
「港のすぐ対岸には、マンハッタン南部の高層ビルが狂ったように林立しているのに、レッド・フックはひっそりと静まりかえっていて、ただ風が吹きわたるばかりだった。風は玉石敷きの通りのうえでささやき、ひっそりとした倉庫群のまわりをゆったりと流れた。遠くのほうから、移動遊園地でミスター・フロスティーのアイスクリームを売っているトラックのかすかな鐘の音、港のほうで鳴るブイの音が聞こえるかもしれない」
これは52ページ目にある描写だけれど、このへんから僕の脳内スクリーンには、小説の舞台であるレッド・フックのさびしい風景がくっきりとイメージされてくる。
主人公のオフィスはブルックリンの南端、コニーアイランド(映画や小説でおなじみの場所。最近ではウッディー・アレンの「ギター弾きの恋」に出てきた)のボードウォークから2筋はいったマーメイド・アヴェニューにある。このあたりの描写も色彩感と音楽にあふれて素敵だ。
「彼は駐車場をあとにして、ブルックリンの通りのざわめきに乗りいれた。交差点では、黒人やヒスパニックの若者たちが、たむろしたり、ポテトチップやポプシクルを食べたり、自転車に乗って後輪走行をしたりしていた。テイクアウトの中華料理店と酒屋のあいだでは、三人の小太りな女たちが大型ゴミ収納器のまえで金切り声の口論を楽しんでいた」
このシーンなど、本当に映画を見ているように脳内スクリーンに音と映像が踊る。ともかくこの小説、町の空気を伝えるのにありったけの力を注いでいるのだ。処女作だというが、なかなかの腕と見た。
ストーリーは単純で、レッド・フックの再開発計画にからんだ連続殺人。凶器のナイフによる傷口に主人公の幼児期の記憶らしきものが呼びさまされる。死体を見て嘔吐し、ベテラン刑事が新米刑事の前でうろたえる。そんな中年男の悔恨と痛みがレッド・フックのさびれた風景に重なり、この小説の基調低音をかたちづくっている。だから、ここでは会話のユーモアもほろ苦い。
「ふたりの刑事が梯子をのぼって道路にもどると、鉛色の空から雨粒が落ちてきた。「マーフィーの法則だな--雨の日、死体はつねに外にある」」
「「すばらしい、ラリー(葬儀屋)、あなたに大きな借りができました。そうだな、死ぬときは、あなたのところにある最高の棺を注文しますよ」」
町の描写に命をかける風俗小説の定石どおり(?)、物語は二転三転などせず、すんなりと結末をむかえてしまう。主人公の幼児体験の秘密はあっさり明らかにされるし、事件も予想外の展開はない。
それでも読み手を最後まで引っぱってゆくのは、こちらが主人公の心象風景にすっかり感情移入させられているからだ。バツイチ中年男と未亡人である40代の女の不器用な愛や、父と子のぎこちない会話も身につまされる。
蛇足をふたつ。ミステリーを読んでいよいよ終わりに近づくと、主人公の身が危険にさらされることが多い。主人公危うしということろで、最終ページまでまだ10ページや20ページ残っていると、きっと主人公は助かって、いいエピローグが用意されているにちがいないと安心する。
でもこの小説は、主人公がそのような状態におちいったとき、あと数ページしか残っていなかった! ああ、こいつは殺されてしまうのか……。その予感が当たっていたかどうかは、読んでのお楽しみ。
蛇足の2。脳内映画の主人公はニコラス・ケイジあたりの役どころか。あまりにはまり役でありすぎるような気もするが。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





