終わりなき対話【谷川俊太郎・中島みゆき】
終わりなき対話
| 書籍名 | 終わりなき対話 |
|---|---|
| 著者名 | 谷川俊太郎・中島みゆき |
| 出版社 | 朝日出版社(224p) |
| 発刊日 | 2025.04.15 |
| 希望小売価格 | 1,980円 |
| 書評日 | 2025.08.18 |
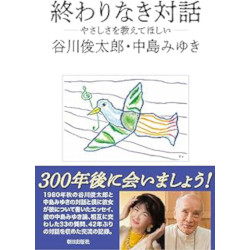
谷川俊太郎(1931年生)が昨年末に逝去した。詩人としてだけでなく、楽曲の歌詞も手掛け、日本レコード大賞作詞賞受賞や「マザーグースの歌」など翻訳の分野でも活躍してきた。本書の相方は中島みゆき。中島と谷川との出会いはひょんなところから始まっている。中島が1972年にニッポン放送主催の「フォーク音楽祭」に出場した時に、谷川の「私が歌う理由」という詩に曲をつけるという課題が出場者に出され、そこで評価されたことが音楽に進むきっかけになったとのことだし、藤女子大の卒論のテーマに谷川俊太郎を選んでいることを考えても中島にとって谷川に対する想いは強いことが理解出来る。
1980年に行われ、本書のサブタイトルにもなっている「やさしさを教えてほしい」というテーマで谷川が対話をしたうちの一人が中島。その対話と2022年に42年振りに行われた二人の対話とお互いを綴った文章を中心に本書は構成されている。1980年は49歳と28歳で、2022年は91歳と70歳になった谷川と中島の対話は時間の経過によっても変わらぬ二人と変わって行く二人が素直に語り合っているのが印象的である。
私にとって「時代」(1975)が耳にした最初の中島の歌だったと思う。「今はこんなに悲しくて涙も枯れ果てて・・・あんな時代もあったねと、きっと笑って話せるわ」という歌詞は日夜働きづめの生活の切り替えスイッチになっていた。その後も「わかれ歌」(1977)、「世情」(1978)、「悪女」(1981)など独特な歌いまわしと歌詞に惹かれていた。こうした中島自身が歌った曲だけでなく、研なおこの「あばよ」(1976)、「かもめはかもめ」(1978)といった曲も好きだったが、中島のプライベートに興味を持つこともなく、ライブに行くとかラジオ番組などを聞くこともなかったので、歌唱を通しての中島みゆきという理解でしかない。本書を読んでみて中島みゆきの性格・人生観などが谷川の視線を通して垣間見えたと思う。また、谷川俊太郎については、詩を読んだことはあるものの哲学者谷川徹三の息子という位置づけが私には強かったこともあり、両者を新たな視点で知ることの出来た一冊になった。
1980年の対話では「自分が好き」「歌を書くときの気持ち」「好きと愛してる」といったテーマのもと、谷川が質問して中島が応えるという流れの中で、中島の頭の中でぐるぐる回っている多様な言葉たちが断片的に零れ落ちて来るという印象が強い。
谷川「あなたの生き方は」
中島「なにかと罪を重ねているでしょ。償うなんてことが追っつかない。」
谷川「どういう罪ですか」
中島「罪状ってきりがないから」
谷川「抽象的に言わないで、具体的になに?」
中島「いっぱいあるから・・・・・」
こんなやりとりを通して、谷川が一生懸命に中島の良さというか特徴を引き出そうとしているのが良く判る。中島はこの対話について「夢のような」仕事だったと後に語っている。特に谷川からの「あなたは子供を持たないの?」という質問に対して返答に窮した挙句に「子供は恐ろしい。私の悪い所ばかり持って出て来るような気がする」と気の利いた答えをしたつもりだったが、谷川から「それは子供に失礼です」という言葉を受けた。そこから威圧や軽蔑といった冷ややかさではなく、温かいシャワーのように感じたと書いている。
かたや、谷川はこの対話の後「大好きな私」と題した文章で、中島の性格を掘り下げるとともに、歌と詩の関係について語っている。歌は言葉とともにメロディやリズム、歌い手の声によって構成されて聴く側に届く。そして、歌は言葉の持つ感情を増幅させる。それだけに谷川は「活字になった歌詞は抜け殻と言うか、歌が肉体であれば歌詞は骨格」と言い切っている。たしかに、歌を聴くことと、歌詞を読むことでは違った感情が湧いてくるものの、私は「抜け殻」というほどの極端な感覚はない。
そして中島のようなシンガーソングライターの歌について、「『夜曲』を聞く人たちはそこに登場する『私』を中島みゆきととらえているのだろうか」という視点から、詩、曲、歌唱の全ての源の中にはいくつもの中島や私が重なり合っているし、演技も虚構もある。「『あなた』と呼びかけられ、そこに歌を聞いている『自分』を置いたり、『私』という一人称を『自分』にしたりする。そうした計算もされている」という風に中島の作り上げている構成と聴く側の「自分」を描いて見せている。歌の力を「歌は決まりきった言葉に新しい感情を与える。慣れ切った感情に新しい言葉をもたらす。歌を書く者も、聞く者もそうやって未知の『私』を発見し続けていく」として中島のパフォーマンスの魅力を伝えている。
谷川は「自己愛をあっけらかんとのろけのように言う人は珍しい。この臆面の無い自己陶酔やうぬぼれも歌い手にとっては有利になっても不利にはならない。歌というものを支える生命力そのもの」と中島を評している。また、中島の歌唱から我々が受けとめる「報われぬ愛に苦しむ女」とコンサートなどでの語りで見せる「笑うのが好きで、出来るだけ当たり前の感覚や生活を失うまいとしている女」という二面性について、どちらが本当の中島かをうんぬんするのは意味もなく、商売上の要請もあるだろうし「中島みゆき自身が大好きな『私』をひとつの限定された役割の中に閉じ込めまいとしている」と考えている。
そして、2022年の42年ぶりの対話は、谷川が前回の対話で印象的だった中島の「自分が一番好き」という話題について、「今もそう?」、「相変わらず」という応答から始まる。「日常薬」「歳を取って来ての気付き」「読んでいる本」など、老父と娘的な会話が続くのだが、私は谷川の生き様について面白く読んだ。谷川は42年間の変化について、「死んだら無になると言っていたが、今では魂はあると思っている。親しい友達が死んだりすると心とか精神では間に合わない。魂という言葉を使いたくなってきた」。
そう語る谷川に中島は「楽しみですね」と返す。「何が?」と問う谷川に中島は「今後、いつ会うかって、三百年後?」と笑って終わりなき対話の区切りを付けている。
谷川はこの対話について「42年前は『やさしさ』について色々考えていたが、それは『生きる態度』とも言い換えられる。そして91歳になり何かを無条件に受け入れる大切さを思うようになった。・・・ぼくは『いま・ここ』の人なのです。過去は忘れちゃう。本当にリアルなことは『いま・ここ』 だっていうこと」という言葉の重さが伝わってくる。
1970年代から半世紀以上、中島みゆきは音楽の世界を走り続けている。世代を超えて広く共感を生み出しているのは、人の心を揺らす根源的な言葉や表現の力なのだろう。活動領域の広さだけでなく、今も全国各地でコンサートを開催し続けているのは凄い事だと思う。最後に、本書の中で谷川は「歌を聞く」と表記している。一方、私は「歌は聴く」という表記が馴染んでいる。谷川の「聞く」という言葉への思い入れを詳細に、聞いてみたかった気もする。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





