石の虚塔【上原善広】
石の虚塔
| 書籍名 | 石の虚塔 |
|---|---|
| 著者名 | 上原善広 |
| 出版社 | 新潮社(287p) |
| 発刊日 | 2014.08.12 |
| 希望小売価格 | 1,620円 |
| 書評日 | 2014.12.17 |
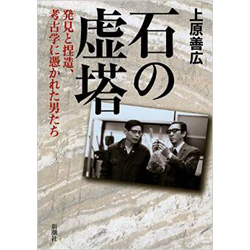
戦後日本の考古学を俯瞰すると、1947年の群馬県岩宿遺跡の発見により大きく進歩した一方、2000年に発覚した旧石器発掘捏造事件によって、その権威も信用も大きく毀損してしまった。本書は、この二つの事象を連続した一つの物語として在野の研究者や学者達の行動や発言を詳細に描き出し、まさに「石に見せられた者たちの天国と地獄」の60年間に亘る物語を創りだしている。
著者は1973年生まれというから、団塊の世代の子供達といった世代にあたり、2010年に「日本の路地を旅する」で大宅壮一ノンフィクション賞を受け、その後も活発に著作を発表している。しかし、考古学を取り上げたのは本書が初の試みであるようだ。本書が対象としているのは考古学そのものではない。したがって、旧石器の遺跡写真が掲載されているわけでもなければ、石器の形式学的図表が示されているわけではない。考古学という学問領域の舞台に立った多くの人々を、まさに群舞のように描いて見せた作品である。
ノンフィクションであることから、想像や仮説を排除して、著者自らが追跡した事実によってひとつの物語を完成させているのだが、そうは言っても全ての事象を洗い出すことは不可能で、仮に全てを洗い出したとしてもひとつの物語に完結させるためには事象の取捨選択が必須となる。そこには、より多くの事実を客観的かつ公平に見る力と一連の事実をストーリーとして構成する見識が問われていると思う。著者はその点、当事者や関係者とのインタビューや文献からの情報を、その発言のバイアスに左右されること無く、極めて抑制された視点で受け止めているという印象を受けるのだ。
戦後60年間に亘る考古学界の「裏面史」をセンセーショナルに書こうと思えばいくらでも書けるのだろうが、そこは著者の冷静に筆を運びつつも、巻末の参考文献の膨大さを見るとその範囲の広さに圧倒されるばかりであるし、戦後考古学の裏面史を300ページの一冊にしようとするとその登場させるべき人物も多く、そのプロセスを著者は「ドキュメンタリー映画を作っている感覚」と称しているのも判る気がするのである。セリフは無いがしっかりと画面に映っている人達がいるように。
考古学に関しては評者も以前から興味のあった分野なのだが、石器や個別の遺跡という視点はあっても、考古学界という見方ではなかった。本書の日本の考古学界を支えてきた学者や在野の研究者たちの師弟関係、人的交流、はたまた性格の違いといった点はなかなか機微なポイントであり、初めて知るところも多かった。学閥や性格の相違からくる親分・子分関係や誹謗中傷の類はどんな社会でも多かれ少なかれ存在するものではあるが、それにしても学術という論理の世界と生臭い人間関係という本来であれば相関しない事象が絡み合ってしまうところに人間らしいと言うか、そこに考古学の持つ「発掘のギャンブル性」と言われる特徴によって増幅される要素になっているのかとも感じるのだ。
登場する主要な人物を本書の中から評者なりに絞り込んでみると、群馬県の岩宿遺跡を発見した在野の研究家の相澤忠洋(1926 – 1989)。その岩宿の発見を論文として発表し、学会では考古学上の発見者とされている、明治大学の杉原荘介(1913-1983)。杉原は戦後すぐに登呂遺跡の発掘で明治大学を考古学界の一角としての地位確立のために東大・慶応大などと競い合った「動であり・激烈な火」と称される激しい性格と学歴主義の権化といわれた考古学者。
杉原の明治大学の後輩で、杉原と比較される形で「静であり冷静な水」と称された芹沢長介(1919-2006)。杉原と袂を分かって東北大学に転じ、前期旧石器研究の前衛を走り続けた男である。そして、芹沢の知古を得て遺跡発掘に参加していた在野の藤村新一(1950 - )。この男が1981年の座散乱木遺跡での前期旧石器発掘に始まり、次々と日本の旧石器の年代を更新していった「ゴットハンド」と呼ばれた男。そして、岡村道雄(1948-)と竹岡俊樹(1950-)の二名が評者としては重要な配役と思っている。
本書は、著者が2010年に福島県南相馬市に藤村を訪ねるところから始まる。捏造発覚後に精神を病んだ藤村は「ゴッドハンド」と呼ばれた自らの右手の人差指と中指を鉈で切り落としている。そうした藤村から自らの経緯を語らせたところで意味は無い。著者は藤村の発掘捏造を始めた経緯を、結果論で言えば、あの岩宿遺跡を発見した相澤忠洋の人生を模倣したと指摘している。ただ、藤村の口からは芹沢長介の名前が神様のように語られる。芹沢は学歴主義と言われた杉原に対抗するように在野の研究者を支援し、積極的にその貢献を認めてきた。芹沢は論文を書く時には必ず発見者の名前を冒頭に付して彼らの栄誉を称えた稀有の研究者であったという。
そして、時代を戦争直後に戻して、60年間を本書はゆっくりと俯瞰していく。1947年相澤が発見した岩宿の石器発見から、1949年の明治大学の考古学研究室の杉原荘介が論文を発表するに至り、「岩宿遺跡」の発見者は誰なのかという栄誉の奪い合いがはじまったとされる。杉原の論文には「相澤忠洋君にわれわれ(明大考古学研究室)の発掘調査についての斡旋の労をとっていただいた」という簡単な謝辞が記載されているだけで、相澤を発見者とは言っていない。論文上では第一発見者は杉原荘介となっている。以後、相澤は杉原だけでなく、明治大学を目の敵としていく。加えて、相澤が最初に石器を携えて相談した相手は、戦後復員し、肺結核の入院加療後に明治大学に戻った芹沢だった。こう考えると、芹沢は岩宿の相澤を見出した人間であり、いわば「相澤忠洋の発見者」である。功を取られたのは実は相澤ではなく、芹沢だったという著者の指摘も以後の杉原と芹沢の確執の深さを見れば納得できるのだ。
芹沢は後に東北大学に移り前期旧石器文化の発掘に注力していくのだが、彼の先鋭的な行動は学界の中でも孤立感を深めていく。その間の遺跡発掘で芹沢の後輩でその考え方に異を唱えた男がいた。それが岡村道雄(1948-)である。彼は芹沢の助手を務めていたが数カ所の遺跡発掘とその検証の結果、師の説に異を唱えて芹沢の下を去り、埋蔵文化財行政を司どる文化庁主任文化財調査官についた秀才である。しかし、その岡村でさえ後に捏造の舞台となった発掘現場に立ち会いながらも、その捏造を見破ることは出来なかった。アマチュアの力も活用して発掘研究を進めていく手法は、アマチュアの研究者を育てると言うよりは、「アマチュアは掘って発見する人。専門家はそれにお墨付きを与える人」という棲み分けを作り上げてしまったという著者の指摘は残念ながら正しいと言わざるを得ない。また、芹沢に代表される「層位(地層)は形式に優先する」考え方にとらわれ過ぎた結果として、捏造を見抜けなかったということだ。その二点がモンスター藤村新一を生み、学界のみならず、地方やメディアが何年にも亘って前期旧石器の連続する発掘劇に狂乱することになる。
もう一人、冷静に石器形式学の観点から異を唱えた男が紹介されている。それが、竹岡俊樹である。彼は、明治大学から筑波大学大学院に進み、フランスのパリ第六大学で考古学を学んだ男だ。1988年に竹岡は「旧石器考古学」という専門誌に藤村の石器に対する批判論文を日本で初めて載せた人物である。こうした動きは当時の考古学界からは無視されただけでなく、芹沢を含め藤村が発掘した前期旧石器といわれた発掘石器の実物を見ることさえ許されなかったという。捏造が発覚し、日本中が騒然となった際に日本考古学協会の中に検証委員会が作られたものの、当初から捏造を主張していた竹岡にはこの委員会から招集を受けることは無かった。その結果「この検証委員会は藤村に騙された者たちだけで構成されていた」という厳しい見方をされることになる。竹岡は現在に至るまで日本の大学の考古学関係の教職に付けていない。共立女子大学の非常勤講師でいるのだが、ちなみに、共立女子大には考古学専攻はない。この学界の不思議さというか、相変わらずの閉鎖性というべきか。
また、評者として、この事件発覚を強く印象付けられたのが岡本道雄の著作である。講談社により企画された全26巻の「日本の歴史」の第1巻として2000年10月24日に刊行されたのが岡本の「縄文の生活誌」であるが、この刊行直後、11月5日に捏造発覚のスクープが飛び込んで来るのである。この本の第1章を読むと、藤村の発掘成果に殆ど依存しており、刊行後10日をして販売停止に追い込まれることになる。2002年10月に改訂版が刊行されたが、改訂版の序文は岡本の厳しい自己反省で満たされているのが辛い。加えて、講談社は旧版所有者に改訂版の無料交換をしたのだから。本書のタイトルである「石の虚塔」は、その岡本の言葉からとられている。
「遺跡というのはね。発見した人の人生そのものが出るものなんだ。相澤さんは学者にはない純粋な目と不屈の精神で岩宿を発見した。芹沢先生は単純なところが有ったから、とにかく深くいけと掘り下げていった・・・藤村は全てがニセモノの遺跡だった。それを近くに居て見抜けなかった私も幻の遺跡を掘らされていた。我々はまさに『石の虚塔』にいたんだ」
本書によって、久しぶりに旧石器捏造事件に目を向けたのだが、この事件を契機として日本の考古学界は変わったのかと問われると、本書を読む限りその体質が大きく変わったようには思えないのだが。 (内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





