遺稿集【鴨志田穣著】
遺稿集
| 書籍名 | 遺稿集 |
|---|---|
| 著者名 | 鴨志田穣 |
| 出版社 | 講談社(384p) |
| 発刊日 | 2008.3.6 |
| 希望小売価格 | 1680円(税込み) |
| 書評日等 | - |
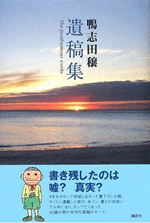
この本を手にするまで、鴨志田穣なる人物を私は知らなかった。ある作家の文章に初めて接するのが遺稿集というのも珍しい経験だ。奥付をみると沢山の本を出している。その中の数冊に目を通し、同時に彼の妻であったマンガ家・西原理恵子の作品にも目を通した。
まず、鴨志田の略歴を年譜から拾ってみる。
1964年川崎市生まれ、1970年に父親の仕事の関係で札幌へ。大学浪人生活を含め札幌で過ごす。1985年上京後、インド・ネパールを旅してヘロイン中毒となる。写真家吉田吉郎に師事しカメラマンを目指す。各国戦場を取材。1995年勝谷誠彦氏のお声掛りでバンコックにて西原理恵子と出会う。翌年、アマゾン取材時に西原にプロポーズ、結婚。一男一女をもうける。アルコール依存症による入退院を繰り返す。2003年取材中吐血・入院・離婚。2006年アルコール依存症を克服。その後、癌が発見され、2007年3月腎臓癌にて死去。享年42歳。
こうしてみると、無頼且つ破滅的に人生を駆け抜けたとでも言うべきか。
本書に収録されている作品は、いわく、「未完の長編」、「小説のような事実のような」と形容されていて読み手の想像を掻き立てているが、「事実」と言ったところで書き手の主観が入るわけだから、過度な客観性を求めることもなくどんどん読んでみた。その結果、感じられるのは、文章のそこかしこに妻・西原の影が見えてしまうということだ。そのように読まれてしまうことは作家鴨志田穣にとって不幸なことだと思うのだか、それとも、彼は西原とのペアとしての表現者と割り切っていたのかもしれない。
いずれにしても、二人が出会いの当時、西原はすでにマンガ家としてしかるべきポジションを確立していただけに、彼女が鴨志田という男をどんな風に見ていたのか、なにがお互いをひきつけたのかというところに視点が行ってしまいがちなのは彼の責任ではないにしても、読者が一様に気にするところだろう。
西原の「ぼくんち」は破滅型で追い詰められた人物たちが最後のギリギリのところでかろうじて人間として存在しているところを描いている名作なのだが、その追い詰められた中での人の素直さは、納得感があるわけではないのだが迫力がある。そんな西原の作風に対して鴨志田も負けないくらいの無頼派の人間だったのだろう。もっとも西原はメジャーな社会評価を得ることが出来た、ブランド化された無頼派だと思うが、その点、鴨志田は本質的な無頼派だった。ヘロイン中毒や強度のアルコール依存症と聞くと一般人の感想としては、十分に破滅型且つ自己管理の出来ない人なわけで、かなりその段階で腰が引けてしまう。
最初の文章の「カモがんばらないで」は彼がアルコール依存症を克服後、癌が発見され、都立有明病院に転院するところから始まる。そこで、治療方針決定のために担当医から話を聞く直前までの一週間を描いている。そこで語られる家族への眼差しは、限られた時間という制約の中でこそ淡々と書かれている。その落差にアルコール依存症の怖さも見えてくる。閉鎖病棟であった精神病院から、開放型の有明病院に転院して、気持ちの自由さも楽しげに書いている一方、もと妻との会話はお互いを思いやる気持ちが素直に伝わってくる。そんな会話が成り立つ男女でなぜ離婚することになってしまったのかとも思う。それだけにアルコール依存症の怖さに戸惑いながら読むことになる。最後、医師に話しを聞く直前の状況が綴られている。
「日本だとマグロ船に乗るか、が脅し文句だけれど、インドネシアじゃサクセス・ストーリーなんだよ。・・しかし、その中で失敗した男達の話ってのを取材したくなってね」
「あんたじゃないの。まんま、あんたの人生そのものです」
「そうかなー。お、俺は、俺たちは二人とも漁師だと思っていたんだけど」
「あはは、そうかあ、二人とも漁師だあ。先のことなんて考えられないもんなあ」
彼女は急にしんみりした顔になった。くり出した言葉を頭の中で蘇らせてみる。゛未来゛という言葉から゛命゛につながったようだ。
「まあ、これから説明があるからさ。よく咀嚼して一番良い方法を考えようよ」
「そうね、それとくれぐれも言っておくけど、焦らないでね。先を急いだって意味はないわけよ」
「そんなこと、判ってるよ。漁師だもん」
「フフッ、そうだったわね。二人とも」
「そっ、二人とも」
「・・一緒にいろいろな所。たくさん行きましょうね。そう、たくさん・・・」
そして、彼のサイトに載っていた最後の文章は2007年3月13日から3月20日の命日まで綴られていたものだ。「妻はマンガ家だった。・・」という書き出しで始まるその文章は、自らバンコックでの西原との出会いを「邂逅」している。衒いも嘘もなさそうだ。マンガや小説で表現されてきた二人の性格と比較するに、大変純粋な表現であることに驚く。
「・・・・はじめて会って仕事をしただけなのに彼女に会う次の日を待ち遠しく思えてならない気持ちになり自分の心に戸惑った。翌日の晩餐は、皆のことを考えて地元のものが通うシーフード・レストランを選んだ。最終日ということもあり、さすがの妻もテンションが下がっていたが、質問は辛辣そのものであった。
食事も終わり皆席を立った頃、彼女はそっと近づき小さなメモ用紙を渡してよこした。「滅多にないことなの」そういい残して、女性の輪に加わり走っていった。メモには彼女の私用の電話番号が書かれてあった。
でも、それから一度も彼女に電話を掛けることはなかった。恋心が戦場での足を鈍らせると思ったのだ。
ただ、神様をこの目で確かに見た。
丁度、一年後。僕たちはアマゾンで一緒に仕事をしたのだ。
取材も終わり、日本に帰る機中、一人ビジネスクラスにいた彼女が「一人じゃ寂しいの」そう言って自分の横に座った。
「いろいろ考え過ぎるんだよ」僕はそうささやきながら彼女の手を強く握りしめた。
それから二人はずっと手を離すことはなかった。」
元妻・西原は元夫・鴨志田の生きた印を残すためにも本書を出版したかったのだろう。この夫婦は「二人とも辛辣・毒舌・無頼」だったのかもしれないが、本書と西原の「毎日かあさん、出戻り編」の両方に目を通すと夫婦や家族の相互の視線が切なく理解できると思った。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





