何が映画を走らせるのか?【山田宏一】
何が映画を走らせるのか?
| 書籍名 | 何が映画を走らせるのか? |
|---|---|
| 著者名 | 山田宏一 |
| 出版社 | 草思社(568p) |
| 発刊日 | 2005.11.30 |
| 希望小売価格 | 3800円+税 |
| 書評日等 | - |
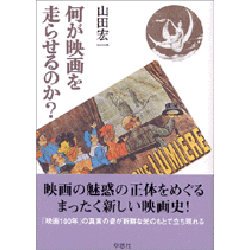
一年半ほど前から「Days of Books, Films & Jazz」というブログを始めて、本や映画や音楽の感想めいたことを書いている。
活字の本はともかく、映像や音について言葉を使って語る作業は、やってみてはじめてそのむずかしさがわかる。いままで何十年と見たり聴いたりしてそれなりに感じたり考えてきたことはあるつもりだったけど、いざ活字でそれを表現しようとなると、どうやってもうまく伝えられなくて七転八倒することになる。
で、手本になるようなものはないかと本棚を探してみた。淀川長治さんから現代思想用語を使ったものまで何十冊かある映画本のなかで、読んでいちばん楽しく、納得でき、しかもこういう語り口で映画を語れたら最高だなと思えるのが山田宏一だ。
「映画 この心のときめき」「美女と犯罪」「わがフランス映画誌」、映画論ではないけれど「カイエ・デュ・シネマ」誌の友人たちとの交友を記録した「友よ映画よ」。
映画論というのは誰もがそれなりに語れるからだろうか、作品の素材になった政治や時代状況を語ったり、現代思想のタームを応用しただけの分析だったり、映画をダシにして別のことを語っているものも多い。そんななかで山田宏一の映画論(論なんて言い方もふさわしくない)は、あくまで映画の中身に寄り添いながら、そのディテールにわけいって映画そのものの魅力を達意の文章で伝えてくれる。
もちろん山田宏一を手本にするといっても、こちらの分はわきまえているつもり。土台、質量ともに映画的教養が違いすぎる。山田宏一は古今東西の映画を、しかも系統だって万の単位で見ているにちがいない。こちらが過去に見た映画の数は、映画少年になった小学校高学年から年に平均60本として45年間で3000本弱。しかも彼はフランスに滞在した1960年代にはヌーヴェル・ヴァーグの母体になった「カイエ・デュ・シネマ」誌の同人で、トリュフォーなどともつきあいがあった。いわば雲の上の存在。
そんな著者の「映画史の読み直しの試み」が「何が映画を走らせるのか?」。面白くないわけがない。映画史といっても、国やジャンル別に系統立てた堅苦しい歴史ではない。あっちへ跳び、こっちへ跳び、監督や女優のゴシップめいたエピソードを散りばめながら、今日の目で見た映画史の「読み直し」という視点をきっちり押さえている。「プロの映画ファン」と自称する山田宏一ならではの仕事だろう。
目次からアトランダムに項目を拾いだしてみる。
「Focus on the money!」は、そもそも産業としてはじまり「興行価値こそ神」だった映画のなかで、客を呼ぶ力がない映画に「芸術的な評価」を与えることによって新しい興行価値を生み出した「呪われた映画」の誕生(例えばエーリッヒ・フォン・シュトロハイム、ジャン・コクトー、オーソン・ウェルズ)。
かつてはそれこそが映画の真髄だといわれたモンタージュ理論を相対化して、ワンカットで撮られた映像の力を強調することで現代的な映画(ネオ・リアリズモ)がはじまったことを語る「モンタージュに明日はない」。
「身代わりの女優史」の登場人物は、ヒッチコック映画のヒロインたちだ。
ヒッチコックが「クールなブロンド美女」に執着したことはよく知られている。最初のヒロインはイングリッド・バーグマンだったが、「ヒッチコックを捨て、ハリウッドを捨てて、イタリアのロベルト・ロッセリーニのもとへ走ったことは(彼は)絶対に許さなかった」(トリュフォーの談話)。次のヒロインはグレース・ケリーだったが、彼女はモナコ王妃となって銀幕を去った。
以後、ヒッチコックはヴェラ・マイルズ、キム・ノヴァク、エヴァ・マリー・セイント、ティッピ・ヘドレンと、何人ものブロンド美女を起用する。でも彼女らはみな「グレース・ケリーの代用品」にすぎず、その映画群は「もうひとりのグレース・ケリーをつくりだそうとするヒッチコック自身の悲痛な物語」と読むことができる。
いくつかの評伝が、ヒッチコックは個人的にもブロンド美女に執着したとか、彼女らを口説いて拒絶されると映画への興味を失ったとか記述しているのに対して、ヒッチコックを愛する山田宏一は、「評伝作者もずいぶん下劣で無礼で冷酷な見方をするものだ。……映画だけしか頭になかったヒッチコックなのである!」と珍しく熱くなって擁護している。
山田宏一の映画の好みは、一方にゴダールがいて、もう一方にハワード・ホークスがいる。
彼がいちばん好きなゴダールは、アンナ・カリーナをヒロインとした「豊穣な60年代ゴダール」。5月革命以後のラジカルな変貌には「ついてゆけず」、「ゴダールの映画史」を頂点とする現在のゴダールには「判断停止をきめこむしかない」。
その「豊穣な60年代」について山田宏一は、ゴダールにとっての「詩神(ミューズ)であり夢の女」であるアンナ・カリーナが体現していたのはハリウッドのメロドラマの要素だったと言う。
「アンナ・カリーナをとおしてハリウッドの最もよき「映画的な」伝統が、メロドラマが、ゴダール映画のなかに流れこみ、受け継がれていたのである」。僕もアンナ・カリーナをヒロインとする何本ものゴダール映画が大好きだけど、ハリウッドのメロドラマ性とはね、そうか、そういう見方があったのか。
とすれば、彼がハワード・ホークスをハリウッドの最もよき代表とするのも納得がゆく。ホークスは男性アクション映画と女性喜劇を得意とした。ホークスのアクション映画の男たちは、「さっそうたるヒーローであり戦士でありチャンピオンでありプロフェッショナルである」。
一方、コメディになると男は「女にふりまわされ、敗北あるのみという滑稽な存在だ」。そしてヒロインたちは「おおらかで愛すべき」「いきいきとして自由な」「はつらつとして行動的」な「夢の女」たちだった。「ロマンチックといえばロマンチック、荒唐無稽といえば荒唐無稽――それがハリウッド映画であり、ハワード・ホークスの映画だ」。
「気狂いピエロ」の印象的なシーン、地中海の青い海を背景にアンナ・カリーナとジャン・ポール・ベルモンドがかわす「知的オノロケのような対話」の素晴らしさを語りながら、山田宏一はこうも言う。「映画のおもしろさについてはいろいろな定義があるだろうが、なんといっても「映画的」に単純におもしろいのは、通俗的ながら(いや、それゆえにこそ)、やはり、文句なしにハリウッド映画なのである」。
「気狂いピエロ」が、ハリウッドのアクション映画へのゴダール流オマージュであることはよく知られている。そのなかに登場するB級アクションの巨匠サミュエル・フラーが言うセリフ、「映画は戦場のようなものだ。愛であり、憎しみであり、アクションであり、暴力であり、死であり、一言で言うなら感動だ」という言葉はあまりにも有名だ。
山田宏一の「映画史の読み直しの試み」は、サミュエル・フラーのセリフに象徴されるヌーヴェル・ヴァーグとハリウッドが交錯した地点から始められているように見える。そこから、彼はヌーヴェル・ヴァーグ以後の「作家主義の功罪」に目配りし、ヌーヴェル・ヴァーグのもうひとつのルーツをイタリアのリアリズム映画にたどり、「マーロン・ブランド以後」の役者(と、彼らを主役とするハリウッド映画)に違和感を表明する。
「豊穣な60年代ゴダール」から、ゴダール自身ははるか遠くの場所にまで行ってしまった。一方ハリウッドも、ハワード・ホークスが代表していた「ハリウッド映画」はクリント・イーストウッドを最後の一人としてほとんど絶滅しかかっているように見える。
両者、あるいは両者が象徴する映画たちが、もう一度交錯することが果たしてこれから先あるだろうか。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





