捏造の科学者【須田桃子】
捏造の科学者
| 書籍名 | 捏造の科学者 |
|---|---|
| 著者名 | 須田桃子 |
| 出版社 | 文藝春秋(383p) |
| 発刊日 | 2015.01.07 |
| 希望小売価格 | 1,728円 |
| 書評日 | 2015.02.17 |
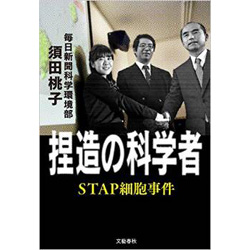
振り返ってみれば、2014年という年は「STAP細胞」から始まったと言える程、1月のあの記者会見は華々しく・センセーショナルに報道された。しかし、わずか一年間で画像の疑義や捏造の指摘・ネイチャー論文の撤回・論文共著者である笹井氏の自殺・理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)解体提言・STAP現象は再現出来ず検証チームの打ち切り等、あっという間の事態の推移に一般人の科学に対する信頼は大きく揺らいだと言ってよい。本書は、毎日新聞科学環境部の記者である須田桃子によって書かれたもので、同紙で生命科学やノーベル賞などの領域を担当し、「STAP細胞事件」でも発表記者会見当初から記事を書いて来た。そうした取材実績をベースに、笹井氏や若山氏をはじめとしたCDB関係のキーマン達への取材やメールでのやり取り、一連の記者会見などの状況等を紹介しつつ時系列に事件を描写している。それは同時に科学ジャーナリスト須田桃子が自らのSTAP細胞報道に対しての反省も含めた検証作業をしているかのように本書を読んだ。
本書は公式のインタビューだけでなく、メールによる取材、匿名や記事化しない前提での取材など、科学記者として築き上げてきた人脈を駆使した内容が特徴的である。特に今回の問題の中心の一人である笹井氏については「私にとって笹井氏は、それまで優れた研究成果を出してきたトップサイエンティストであると同時に、会えばいつでも基礎科学の魅力を関西弁で生き生きと語ってくれ、科学取材の醍醐味を感じさせてくれる研究者の一人だった」という関係が前提となり、1月28日の記者会見の前に「記者発表については完全に緘口令になっています。しかし、須田さんの場合は『絶対』に来るべきだと思います」とのメールを笹井氏から受け取り、会見に出席したという因縁の経緯から本書は始まる。
発表の内容が持つ革新性とともに若い女性科学者が彗星のように現れ、笹井をはじめとした理研の錚々たる学者達が「真摯な研究姿勢」や「実験能力の高さ」など手放しで称え、須田自身も高揚した気持ちで会見を終え、記事にしたと振り返っている。しかし、わずか二週間後にはネイチャー誌論文への多くの疑義が浮上する中でも笹井氏とメールのやり取りは笹井氏の自殺の三週間前まで続き、その間の笹井氏の心情の揺らぎも生々しく書かれている。こうした一連のメールに加えて、関係者に対する多面的な取材に基づく描写は関係者の生の声として多く取り上げられている中で「笹井さんは小保方さんのメンター(助言者)の立場とオーサー(著者)の立場がごちゃごちゃになっていた」という理研の人間の言葉に、この問題の本質の一端を感じた。
また、今回の事件で須田が引っかかっている点は、論文の内容に関わらず共著者としての笹井氏や若山氏がすでに研究者として高い評価を得ており、あえて捏造に加担するとも思えないし、彼らの知らないところで捏造が有ったとしても一連の研究過程や論文執筆過程で誰も見抜けないとは思えなかったというものだ。この点に関する見解の一つが、外部の有識者だけで構成された理研改革委員会が提出した理研改革案である。この改革案発表の記者会見は「すでに、この不正事件は世界の三大不正のひとつに認識された」という厳しい言葉から始まったのはインパクトがあったが、その要点は、「IPS細胞研究を凌駕する画期的な成果を獲得したいという強い動機に導かれて、小保方氏を採用した可能性が極めて高い。採用過程はにわかには信じがたい杜撰さ・・」と批判し、CDBの成果主義が負の側面がこの問題を生み出す一つの原因とした。
論文作成過程では笹井氏が秘密保持を優先した結果、「外部からの批判や評価が遮断された閉鎖的状態だった」こと。データ記録・管理の杜撰さは理研としても研究者まかせであり組織的取組はなかったことから「研究不正行為を誘発する、あるいは抑制できない組織の構造的な欠陥があり、・・トップ層のなれあい関係によるガバナンスの問題」としたうえで、CDBの解体や管理者の更迭などが提言された。
そして、小保方氏個人の資質や能力について須田は多角的に記述している。理研調査委員会による論文における研究不正の断定に対して「『悪意のない間違い』であるにもかかわらず、改竄・捏造と決めつけられたことは承服できません」という「悪意」の有無に根拠を求める小保方氏の反論や、4月9日の小保方氏個人の会見で、須田は画像の切り貼りに対する、その行為の不適切性について質問したが、回答は「結果自体は正しく表示されているので問題ない」との小保方氏の発言に「科学者としては誠実さや論理性に欠ける」との思いを語っている。加えて、2012年にSTAP細胞論文はネイチャー・セル・サイエンスという著名な科学雑誌三誌に続けて投稿されているが、全て不採用となっている事実を須田は重く指摘している。
雑誌に投稿された論文は査読と呼ばれる数名の科学者(匿名)によって読まれ、採用・不採用の提言が雑誌になされるとともに、コメントが著者に返される。通常はこのコメントは著者本人以外には開示されないが、この不採用となった論文の査読資料を須田は独自に入手し、論文とともにコメントも全て読み込んだ結果からの分析は本書の白眉であると思った。須田が示した最大のポイントは、査読で不採用となった結果コメントは小保方氏によって次の論文に生かされた形跡がみられなかったという事実だ。この結果、同種の指摘が別の雑誌の査読コメントで繰り返されている。それは「新たな万能細胞の存在を根本から疑い、別の現象の見間違いである可能性を指摘」しているものや、「根拠となるデータやその分析が不十分さ」に言及するコメントであるが、これらは理研の検証委員会が再現検証の結果から指摘している点にいくつも重なっている。
もし、この査読のコメントを小保方氏が真摯に受け止めて、論文の完成度を上げる努力をしていれば、論文の完成がなかったとしても、今回の問題は起きなかったはずである。科学における伝統的な手法である「論文」による進化のブロセスは生きていたのだ。しかし、この査読コメントについて調査委員会の質問に小保方氏は「コメントは精査しておらず、その具体的内容についての認識はない」と言うものだった。小保方氏の科学者としての倫理観や誠実さといった知識以前の部分の欠落は明らかで、いろいろな小保方氏の人物評価の意見が本書でも示されているが、つぎのコメントが最後まで心に引っかかっていたと須田は書いている。
「画像の使い回しや画像の反転などの行為を本当にやったとしたら、小保方さんは相当、何でもやってしまう人ですよ。無断引用もね」
こうした、多くの問題を抱えているSTAP事件は論文撤回、小保方氏の理研解任、STAP細胞再現検証の失敗、といった形で幕を閉じようとしている。しかし、須田は、「科学は本来論文という形式で成果を発表し合い、検証し合うことで発展してきた。研究機関自らが社会の関心のみに配慮して論文自体の不正の原因調査を軽視して、先送りしたことは、科学の営みの在り方を否定する行為で、理研の対応はコミュニティーを心底失望させた」として警鐘を鳴らし続けている。また、科学記者須田の気持ちは「初期の大々的な報道に対する批判もあった、私自身何度も当初の取材を振り返り、自問自答した。・・・再び1月下旬に時が戻ったとしても、STAP論文の不正やデータの曖昧さを見抜き、記事を書かないようにデスクに進言できる自信はない」という。
しかし、この事件の中心人物の一人である笹井氏を欠いてしまった今、「このまま幕引きを許せば、真相は永遠に闇の中に葬り去られる。それは日本の科学界、及び科学ジャーナリズムの敗北」という須田の意見を彼女自らも含めて、どんな具体的な行動にしていくのか科学界・ジャーナリズムの双方が大きな荷物を背負っていると思う。
加えて、評者としてこの事件で感じるのは、インターネット社会にあって我々が膨大な情報の渦の中に存在しているとともに無数の人の目に晒されているということである。画像の切り貼りや転用といった不正行為もPCのプレゼンテーション・ツールであるパワーポイントを活用して、画像の反転・色調調整さえ素人が簡単に「操作出来る便利さ」があだになっているし、博士論文の20ページにわたるコピペについても、インターネットで世界中の論文からキーワード検索をしてほしい内容の文章を一瞬でコピーできる気楽さに、「罪の意識の希薄化」が生じ易いという側面もあるだろう。こうした、不正する側の利便性がある反面、その論文が公表されたとたんに、全世界の人々の目に晒され、わずか二週間で疑義や不正の告発が世界を駆け巡るのだ。これはメディアやジャーナリズムの側、理研をはじめ組織の側もそのスピードに翻弄されている状態が本書からも見て取れると思った。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





