肉とスッポン【平松洋子】
肉とスッポン
| 書籍名 | 肉とスッポン |
|---|---|
| 著者名 | 平松洋子 |
| 出版社 | 文藝春秋社(266p) |
| 発刊日 | 2020.07.16 |
| 希望小売価格 | 1,650円 |
| 書評日 | 2020.11.15 |
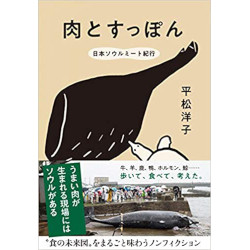
食に関して多くの著作を残してきた平松洋子の一冊。タイトル通り、肉を食べる楽しさを語り尽くしているのだが、本人は「制御しがたい悦び。・・・いま確かに猛々しい生き物と親しく結び合っている名状しがたいナマの感覚」と書いている程の自称肉好きである。そして「美味い肉は作られる」というのが結論だ。
元来、人間は狩猟と採集で獲得したものを食べて、自然と一体化して生きてきた。天武天皇の肉食禁止令や、仏教の殺生戒の教えによって日本ではおおびらに獣肉を食べられなかった時代が長い。しかしそれでも「薬食い」と称して人々は肉食を続け、馬肉は「さくら肉」、猪は「山くじら・ぼたん」、鹿肉は「もみじ」など隠語で語られるのも庶民の知恵というか反抗心の表れと平松は指摘する。しかし、我が国の牧畜の仕組みは明治期に作り上げられたことを考えれば、長い間、庶民の肉食は野生種を狩りで捕獲するという。自然との共生が保たれていたことに他ならない。しかし、こうした共存の仕組みが長い時間の中で生活様式とともに変化した結果、現代では新たな課題が提起されている。「人間の食料が畜産で使われる飼料として奪われている」「動物の保護」「肉食による生活習慣病の多発」といった多様な議論の根源は、我々が動物との共存時代とはかけ離れてしまっているところに存在しているということなのだろう。
著者はこうした、日本の肉食文化の歴史を踏まえながら、狩猟、牧畜、屠畜、解体といった活動の知恵などを探るために全国の現場を訪れて、それらに携わっている人達から話を聞いている。羊、猪、鹿、鳩、鴨、牛、馬、スッポン、鯨といった生き物たちと向き合っている人達の仕事からは、伝統的な技術承継とともに日々の進化でもあることも語られている。そして、各々の肉を美味い料理にして提供する店にも足を運び、素材の活用の技を紹介している。日本の伝統食にこだわらず、世界の料理の知恵を含めて現代の日本人の食肉文化を俯瞰して捉えている。
本書で取り上げている野生種は猪、鹿、鴨、鯨であるが、各々の捕獲から消費までの環境の違いとともに、仕事・事業としての成り立ちも様々であることが興味深い。
島根県邑智郡美郷町では、猪の被害に苦しんでいた農家がプロの狩猟家に頼らずに自ら狩猟免許をとって、役場と連携して駆除捕獲と同時にそれを資源として活用しているケース。捕獲した猪は「おおち山くじら」というブランデイングをして「夏イノシシ」の淡泊な味を売り物にするとともに、婦人会は猪のなめし革を活用して、クラフト製品を作り、加工食品を含めての肉の販売も積極的である。自治体と住民の一体型の形態はユニークである。
また、石川県加賀市の鴨のケースは伝統の承継に立脚したアプローチである。この地では昭和期には鴨は魚屋で吊るされて売っていたというし、鴨のつがいをお歳暮や結婚式の引き出物にしていたというから、伝統的な食文化として定着していたことが判る。当地の片野鴨池にシベリアから飛来する鴨を「坂網猟」という、日没直後の池から飛び立った鴨をY型の網を宙に投げ上げて捕獲する猟が行われている。この伝統の技術を継承する組合を設立し捕獲量の管理することで持続性が担保されている。
猪、鴨に加えて鹿といった野生種の美味い肉の確保の手順は共通しているようだ。例えば、箱わなで捕獲したイノシシは、ストレスを与えない様に素早くとどめを差し、喉の左側を突いて血液を排出させ、内臓を取り出すことで体内ガスの発生を抑える。こうして一時間以内に解体を終える。屠畜から始まる、こうした素早い作業が鍵である。
一方、飼育して美味い肉を作る努力も紹介されている。北海道の羊飼育は軍服の原料として羊毛を利用するため明治期に函館で始まり、大戦後は1950年代に羊飼育のピークを迎えたものの、1962年に羊肉が自由化され国内飼育はビジネスチャンスを失った。現在の羊肉の自給率は0.5%という。
こうした状況で北海道白糠の「茶路めん羊牧場」が紹介されている。帯広畜産大学で牧畜を学んだ青年が1987年にスタートさせた牧場で現在800頭が飼育されている。飼料には北海道産を使い、取引先の用途によって性別・月齢などによる肉の特性を考慮して屠畜し出荷している。羊は牛や豚と異なり公的な等級や格付がないので、生産者のこうした知見が必要とされるとともに、生産者毎の肉の美味さが消費者から問われることになる。
北海道襟裳岬の短角牛の牧畜は海と陸の連携で成り立っている。明治期に南部牛(短角牛)が襟裳岬に導入されたものの、大戦の影響もあり草原も荒れ、コンブ漁にも大きな影響が出ていた。その襟裳岬の草原や森林の再生事業が1953年に始まったが、豊かさを失っていた隣接する海の再生でもあった。この結果、1965年頃から成果を上げ始めた。著者は半コンブ漁・半牧畜の三代目が経営する「高橋ファーム」を訪ねている。コンブ漁で忙しい夏場には牛は放牧して手は掛からず、冬場は里に連れて来て世話をするといったサイクルである。黒毛和牛は脂肪の甘さと肉の柔らかさを売りにしているが、短角牛は放牧されて育った赤身の肉が特徴である。この短角牛の国内の牛の飼育頭数の1%でしかないが、この1%こそ多様性の意義と語っているのも印象的である。
こうした、日本のソウルミートを利用した料理についても詳しく語られているのだが、具体的な店の名前とともにレシピなども紹介されているので、食べに行ってみようと思わせるガイドブック的な要素もある。一例として「パッソ・ア・パッソ」というレストランのシェフは鳩を解体すると肉の状態から屠畜される前の2-3日間の気温などを知ることが出来ると言う。肉を捌きながら、料理するときの熱の伝わり方や肉の水分をどう抜くのかが判るという。そうした季節感の理解を含めて「肉にも旬がある」という指摘になるのだろう。
鳩の胸肉は肉の中に脂が入る肉質ではないので、外から強火で熱が入ると短時間でウェルダンになってしまうという特性がある。また、馬刺しでは、真っ白なサシが入っているのにしつこさを感じないのは馬肉は脂肪の融点が低いからと言われている。こうした、肉質の違い、脂肪の質の違いは当然調理に差が出ることになるのだろうし、その違いを楽しめる料理を作ると言うのが文化としての肉食の歴史と知恵だと思う。
スペインでイベリコ豚の生ハムを切り分けて皿に出されてすぐ食べようとして怒られたとの話も聞いたことが有る。イベリコ豚の脂肪は室温でとけるので、脂肪が溶けだしてから食べるのが一番美味いというもの。ここまでくると、美味いものを食べたいと言う欲の素直な現れという事だろう。
こうした、各種の肉に関する繊細な感覚は我々日本人の一般的な感覚領域にはないのではないか。我々のタンパク源の主力が魚介であった歴史が長く、現在も肉に比較すれば、非常に多くの種類の魚介を多様な手法で口にしている。私は、本書で取り上げられている獣や鳥の肉は全て一度は食べたことが有る。しかし、日常的に食べるわけではなく、特別な食材だ。ただ、本書を読みながら短角牛のすね肉を手に入れてビーフシチューを作ってみようという気持ちになった。時間を掛けて煮込むと美味そうである。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





