日ソ戦争【麻田雅文】
日ソ戦争
| 書籍名 | 日ソ戦争 |
|---|---|
| 著者名 | 麻田雅文 |
| 出版社 | 中公新書(292p) |
| 発刊日 | 2024.04.25 |
| 希望小売価格 | 1,078円 |
| 書評日 | 2025.01.18 |
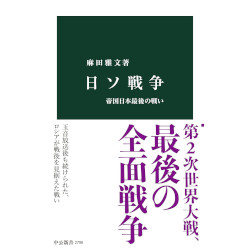
『日ソ戦争』とは第二次世界大戦末期、1945年8月8日にソ連が日本に宣戦布告し、日本がポツダム宣言受諾を表明した後も9月上旬まで続いた戦争を指す。昭和期の中国との戦争は「日中戦争」、米英との戦争は「太平洋戦争」とも呼ばれるが、この戦争には正式にも通称としても名前すらついていない。だから「日ソ戦争」とは、著者による命名。
「日ソ戦争」は、戦争にいたった経緯や戦闘の推移について、一般にはあまり知られていない。「戦史の空白地帯」とも言われる。そして戦争の結果としての満洲移民の苦難やシベリア抑留、中国残留孤児、北方領土問題といった「戦後問題」ばかりが大きく取り上げられてきた。本書は、戦後日本に大きな課題をもたらしたそれらの原因としてのソ連との戦争について、著者が発掘した史料も交えてその全体像を描こうとしたものだ。私も戦争の経緯をよく知らないので、著者の書くところを追ってみる。
ソ連が日本に戦争を仕掛けたについては英米、特にアメリカの動向が深くかかわっている。1943年、ローズヴェルト米大統領とチャーチル英首相は、ソ連の最高権力者スターリンに対日参戦を求めた。1945年2月、三者のヤルタ会談でスターリンはおおむね合意し、ソ連による大連の租借、満洲鉄道の中ソ合同経営などを定め、ドイツ降伏後2~3カ月以内に参戦するという秘密協定が結ばれる。
3月に沖縄へ上陸した米軍は、九州上陸作戦を11月と決めていた。沖縄の激戦で増え続ける死傷者に頭を痛めた米国は、日本を一刻も早く無条件降伏させるために、ソ連の参戦と原爆の開発という二つのカードを求めた。
一方、日本はこの時期になっても日ソ中立条約を結ぶソ連に和平仲介の期待をかけていた。内閣も陸海軍も宮中も、天皇をいただく「国体」を守るため無条件降伏だけは避けたいことで共通していた。開戦前日まで日ソの交渉は続いていたが、8日、クレムリンで色よい返事を期待する駐ソ大使に読み上げられたのは宣戦布告文だった。
ドイツが降伏し、大きな兵力を西部戦線から東へ移した極東ソ連軍が侵攻したのは、日本軍が駐留する満洲国、日本領だった朝鮮、南樺太、千島列島の四方面だった。
満洲国では、ソ連軍は三方から攻撃をしかけた。西からは大興安嶺の山岳地帯や内モンゴルの砂漠を越えて、戦車を中心とする機甲部隊が南満州を目指した。関東軍は極東ソ連軍の10分の1の戦車しか持たず、機甲部隊は大きな戦闘もなく1日100キロを超えるスピードで進軍した。日本軍は爆弾を抱えて戦車に飛び込む「陸の特攻」で抵抗し犠牲者を出したが、成果は乏しかった。北からの部隊は、シベリア鉄道を守りつつハルビンを目指した。東からは、沿海州の国境を越えたソ連軍がハルビン、新京を目指した。ここでは激しい戦闘が繰り広げられ、激戦の末、牡丹江を占領したソ連軍はハルビンに向け進軍した。
朝鮮半島への侵攻は北東部の国境から始まり、清津での激戦を経て、8月末までに平壌、新義州、9月17日には米ソが定めた軍事境界線である北緯38度線以北の占領を終えた。
スターリンは8月18日に極東ソ連軍に停戦命令を出している。しかし、現実には戦闘はその後も続いた。その理由について、著者はこう書いている。
「ソ連軍は、局地停戦に応じるよりも進撃を優先し、各地で衝突を招いた。これは、ソ連軍が停戦より占領地の確保に重点を置いていたためだ。ヤルタ会談で約束された利権を確実に手中にするのがソ連軍の最大の戦略目標で、日本軍の無条件降伏をゴールとし、それが実現してからは流血を避けた米軍とは異なる」
もともと南樺太と宗谷海峡は米軍が重視していた。ここは友軍ロシアへの補給路に当たるし、北日本への爆撃基地にもなる。米国はソ連に再三、南樺太の攻略を求めていた。宣戦布告後、南樺太へのソ連軍の侵攻は北の国境からと西海岸への上陸の二方向からだった。熊笹峠での激戦を経て最大の都市・豊原が占領され、8月末に戦闘が終わった。南樺太には日本人だけでなく朝鮮人もいて、朝鮮人と結婚した日本人を含め在留邦人・朝鮮人の問題は戦後長く尾を引いた。
千島列島も、米軍にとってオホーツク海を安全に航行するのに重要で、たびたびソ連に共同作戦を呼びかけていた。ソ連が千島列島の占領に動いたのは日本がポツダム宣言受諾を通告した直後。当初、北から順に攻めて得撫島(択捉島の北)までを占領した。このとき、スターリンは米国に対し北海道の北半分の占領を望んだがトルーマン米大統領に拒絶され、北海道上陸作戦に予定されていた部隊が択捉島など「北方領土」を占領した。結果として、アメリカが北海道を占領した代わりに千島列島を「ソ連へ差し出した」かたちになった。「現在も北方領土問題にアメリカが消極的なのは、こうした過去と無関係ではない」と著者は書く。
日ソ戦争に参加した兵士はソ連軍が約185万人、日本軍も100万人を超える。「全面戦争」である。ソ連軍の戦死傷者は3万6000人。日本軍の死者は、ソ連の史料によると7万8000人。しかも日本は兵士より民間人の犠牲が多く、約24万5000人の多数にのぼる。
著者も「ソ連を対日戦に引き込んだのはアメリカ」と書くように、日ソ戦争は日本とソ連だけでなくアメリカの意図と行動を視野に入れておかないと、双方の動きをうまく理解できない。専門家の本書への評価がどういうものか分からないが、一読者にとっては、日ソ戦争をそのような三者のせめぎあいという構図のなかに描き出しくれたことが大いに勉強になった。
著者が最後にちょっとだけ触れているのはソ連、というよりロシアの「戦争の文化」についてだ。
「日ソ戦争は同時代の米英との戦いに比しても、さらに陰惨な印象を受ける。それにはソ連そしてロシアの『戦争の文化』が関係している。自軍の将兵の命すら尊重せず、軍紀が緩い。こうした第二次世界大戦におけるロシアの『戦争の文化』が、今世紀のウクライナでも繰り返されている感覚を覚えている」
著者の言う「戦争の文化」とは、具体的には民間人の虐殺や性暴力、強制連行、領土の奪取など。そうした「文化」が過去から現在へと継承されているとすれば、それは現在は存在しないソ連という国家やスターリン個人にとどまらず、その底に流れるロシアの歴史にまで踏みこまないと理解できないことになるだろう。
本書は今年度の司馬遼太郎賞受賞作だが、その司馬には『ロシアについて』という著作がある。著者もこの書に影響を受けたという。私も本書を読んだことをきっかけに、数十年ぶりに『ロシアについて』を読みかえしてみた。これは、『菜の花の沖』『坂の上の雲』という日露関係を扱った2冊を書くため10年以上にわたってロシアという主題を考えつづけた結果として、司馬がつかんだ「ロシアというものの原風景」についてのエッセイだ。それは「タタールのくびき」と呼ばれる、モンゴル人のキプチャク汗国に数百年にわたって征服・支配された歴史と深く関わっている。
「外敵を異様におそれるだけでなく、病的な外国への猜疑心、そして潜在的な征服欲、また火器への異常信仰、それらすべてがキプチャク汗国の支配と被支配の文化遺伝だと思えなくはないのです」
麻田のいう「戦争の文化」もまた、こうした歴史的遺伝の20世紀的展開として捉えることができるのだろう。現在のウクライナをめぐるプーチンの言説と行動もまた、おなじ文脈のなかにある。
『日ソ戦争』と『ロシアについて』は、そのスタイルでも共通するものがある。麻田が日ソ戦争を考える際、常にアメリカを参照軸にしたように、司馬の思考も単に日露の二国だけでなく、常にロシアとモンゴル、そしてモンゴルの背後にある中国という四者の関係のなかで日露の交渉史を考えている。そのように複眼的に物ごとを見ることが、相手への好悪の感情のみを肥大させる単純な二分法に囚われることなく、広く長い視野で歴史や現在進行形の事態を考える態度につながっていくのだろう。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





