なぜ、生きているのかと考えてみるのが 今かもしれない【辻 仁成】
なぜ、生きているのかと考えてみるのが 今かもしれない
| 書籍名 | なぜ、生きているのかと考えてみるのが 今かもしれない |
|---|---|
| 著者名 | 辻 仁成 |
| 出版社 | あさ出版(288p) |
| 発刊日 | 2020.08.26 |
| 希望小売価格 | 1,430円 |
| 書評日 | 2020.10.17 |
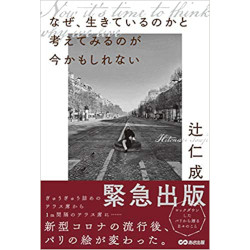
本書は「ロックダウンしたパリから贈る日々のこと」とあるように、パリ在住の著者が2020年2月1日から6月18日までのコロナ禍の体験をネットにアップしていた文章をまとめたもの。私はこの本を手にする迄、「辻仁成」という人物を知らなかった。プロフィールを読んで1997年の芥川賞を受賞していることを知り、16才の息子と二人きりでパリで生活しているということなど、何やらいろいろな人生を辿った人だということは想像に難くなかったが、テーブルの上に置いておいた本書を見て、家人が「中山美穂の亭主だった人」と教えてくれた。
このコロナという未体験の状況下で、どう考え・どう生活するのかを迷う事も多いものの、終息が見えない中ではその正解は見出しにくいし、世代の違い、文化の違いの中でこの感染症への考え方の違いもあるだろう。そう考えると、家族と共に住み慣れた日本に居る私と違って、著者の置かれた状況は異なった文化、ロックダウンという制約、父親と息子の二人きりの生活といった条件はメンタルにも大きな影響を与えることは容易に想像がつく。それだけに本書から正解を得ようとは思わず、辻仁成の一個人の体験として読んだ。そして自分を振り返って、今をどう生きるかについて考える刺激には事欠かない読書であった。
コロナ禍の半年で、家で考える時間が多く、物事の整理の時間が確保出来たことなど、自粛期間の時間は有効に活用出来たと私は思うのだが、逆に引きこもりストレスが溜まったと言う人も沢山いる。平時の日常生活においても人により疲れ方が違ったり、ストレスの個人差が有る。そうした個人差や環境の差が極端に振れてしまうのが、ロックダウンや自粛の時代なのだろう。辻は「価値観の変化、異常事態をどう受け止めるのか、絶望から希望を取り戻す方法、親子で力を合わせて頑張った日々、これらを書き留めてきた。書くことで希望を手に入れようとしていたような気がする」と記している。
3月17日から5月11日までのパリのロックダウン期間中の体験を読むと、武漢の「都市封鎖」と東京の緊急事態宣言下の「自粛要請」の間の様に思える。パリのロックダウンは外出制限であり、外出禁止ではない。食品・薬品の買い物は出来るし、自宅から1km以内で1時間以内の運動や犬の散歩などは許されている。ただ、外出理由を書いた書面を持っている必要があり、これに違反すると罰金が科せられる。警察は通行人を呼び留めて書面を確認し、自宅からの距離を調べ取り締まる。10日間で26万人が検挙されたとのこと。日本の「自粛・お願い」に比較すると大きな差がある。ソーシャルディスタンス感覚(パリでは1m、イギリスでは2m)や外出時のマスクの徹底度合いは文化の差が大きそうである。ただ、辻が外出する際のスタイルはマスク、メガネ、ハンチング、サージカル手袋と聞くとその徹底ぶりにいささか驚くのであるが、その姿ではパリであろうが日本であろうが違和感を持たれるのではないか。
そして「Stay Home」による人間関係のストレスでDVが一週間で30%増えたことが象徴する様に、多くの人は逃げ場のない人間関係に追い詰められた。一方、異文化に住む辻自身の考え方が語られている。一言で言えば「冷静と情熱の間」が丁度良いというもの。辻は「僕は誰からも負けたことは無い、いやもしかしたら、負けた事に気付かないので結局は負けた事にならない・・」という生き方を示しつつ、自分は攻撃を受けやすい人間として自らをサボテンに例えている。
「全身トゲをまとって人を近づけない。しかし、たまに花を咲かせると誰かが声を掛けてくれる」
こんな自身の分析であるが、本書を読む限りでは、もう少し攻撃的な要素もありそうに思えたのだ。こう言いながらも、辻のパリに於ける近所との付き合いはなかなかポジティブである。多くのエピソードを含めて、散歩途中の近所との会話やカフェ、食料品店などでのやり取りはパリの地区の風土もあるのだろうが、辻の性格だからこそ出来る付き合い方の様に思える。
辻が「心の体操」と言っている一つが「感謝を忘れない」というものだが、日本での医療従事者やその家族に対する偏見と差別のニュースに怒りつつ、パリで有名な毎晩八時になると家の窓を開けて拍手をして医療従事者に対して感謝の気持ちを表わす行動に参加してきたという。5月11日のロックダウンが解除された夜、辻が窓を開けて拍手をすると誰も居ないことに気付く。それでも拍手をし続けると一人二人と隣人が拍手を始めて以前と同じ様子になったという。
辻の息子と二人のステイホームというのも厳しい時間だったようだ。シングルの親は働きながら家事・育児の全てをこなさなければならない。その大変さは想像するに余りあるが、父親が子育てをするとなると大変なことだろう。それも、フランスという外国である。
辻は「親の権利を手渡された時」という言い方をしているので、自分の意志で親権を取ったのではないようだ。 しかし、子育ては単に意地だけでできることではない。我が息子と二人三脚という意味を見つけることが重要だったと言っている。自宅に居て、限られた時間だけ外に出て買い物をして帰ってくるというロックダウンの生活の中で、洗濯、食事作りなど全てを行うことにフラストレーションを感じつつも、特に食事作りには情熱を捧げていることが良く判る。加えて息子に包丁の使い方や火の扱い方などを教え、単に美味いものを食べる楽しみの共有だけでなく、生きるための教育になったとことが良く判る。そして、食べ物に対する感謝の気持ちが息子に育まれたことを喜んでいる。この意味ではコロナのロックダウンを有効活用したということなのだろう。
友人が「国民だから国のルールには従う。でも、心が折れてまで生き残りたくない」と言ったことに対して「もし一人だったらそう考えていたかも知れない。でも息子が居るから・・・」と、時としてストレスの対象になる息子の存在が、救いになったと語っているのも印象深い。
長い歴史の中で人間は集合体として智慧を磨き、仕組みを作り上げてきたが、それらへの構造変化も起こるだろう。加えて、文明によってもたらされた幸福感や達成感などの価値観の変化も確実に起こっている。それらは経済的側面だけでなく、政治的側面へも必ず影響を及ぼす。
辻は渡仏して18年、初めてひっそりとした姿のパリに接し、沈みゆく夕日を見ながら「老境に入った自分を感じた」と感慨している。私を含め団塊の世代であれば日々考えることなのだが、50代で「老境」は早すぎる。こうした気持ちから自分を取り戻す手段として辻は歌を歌うという。何であれ気分を切り替えるスイッチを持っていることは重要だ。
人間が持ち込むストレスとは、我慢、頭を下げる、自分の人格が否定されるといったことが原因である。だから彼はそうした社会・集団には近づかず孤独で良いという。しかし、現代では人と交わらず生きて行くことは不可能だ。必ずストレスが発生する。それだけに「会話」「言葉」の大切さに気付くことになる。同じ「ことば」でも使い方ひとつで「武器」にもなれば「支援」にもなる。その伝える力の多くは論理だけでない、表情や仕草も必要だ。
孫がこの春、大学に入学した。ずっとオンライン授業が続いているという。「勉強はどうにか進むけど、友達は出来ない」という言葉が切ない。若い人達がこの事態をどう乗り越えて希望に繋げていくのか正念場だ。彼らには「どう生きるか」を考えてもらいたい。一方、本書は、私を始めとした団塊の世代が「なぜ生きているのか」を問い掛けているようだ。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





