21世紀の資本【トマ・ピケティ】
21世紀の資本
| 書籍名 | 21世紀の資本 |
|---|---|
| 著者名 | トマ・ピケティ |
| 出版社 | みすず書房(710p) |
| 発刊日 | 2014.12.08 |
| 希望小売価格 | 5,940円 |
| 書評日 | 2015.03.16 |
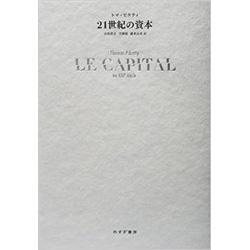
トマ・ピケティの『21世紀の資本』は世界で150万部超、日本でも13万部のベストセラーになった。700ページを超える専門書がこれだけ売れたのは、40年に及ぶ編集者生活でもあまり見た記憶がない。世界中で格差問題に対する関心がいかに高いか、ということだろう。
日本でも何冊かの解説本が出版され、週刊誌で「1時間でわかるピケティ」なんて特集も組まれた。ピケティ自身も来日してシンポジウムやインタビューでいろんな発言をしている。だから本書の、
「r ≻g(資本収益率は経済成長率≒賃金上昇率を上回る)」
といった式や、
「現在の格差は長期的には持続不可能なところまで高まっている」
という結論について知りたいのなら、わざわざ700ページを読むまでもない。
では、結論が分かったうえでこの本を読む面白さはなんだろう。いくつかあるけれども、僕がいちばん面白かったのは115点に及ぶ図表だった。ピケティのこの本は、100年から200年に及ぶ米欧日の膨大な税務データ(相続税や所得税などのデータ)を協力者とともに集め、それを国際比較できるようにしたことにいちばんの価値がある。「r ≻g」というのも理論的に導かれた式でなく、データから得られた「歴史的事実」なのだ。
ところで版元のみすず書房は、太っ腹なことに本書の命ともいうべき115点の図表をホームページで公開している。そこからいくつか紹介してみようか。
各国の格差の度合とその歴史が一目でわかるという意味では、次の2点。
・トップ1%が総所得に占めるシェア(アングロ・サクソン諸国
第二次大戦後の世界はどの国でも比較的格差の少ない時代がつづいたけれど、現在問題になっている格差が拡大しはじめたのが1970年代のサッチャー・レーガン時代からであることはよく知られている。この図を見ると、アメリカやイギリスではトップ1%の所得が70年代以降激増し、今では国民の総所得の15~20%を占めている。ピケティによれば、これは主にトップ経営者の報酬が激増した(しかもその根拠ははっきりしない)ためだ。この「スーパー経営者」の台頭を彼は「アングロ・サクソン的現象」と呼んでいる。
一方、大陸ヨーロッパや日本を見ると、トップ1%のシェアは増大する傾向にあるけれども米英ほどではない。先進国の格差は米英で激しく、ドイツ、フランス、日本は中くらい、スウェーデンは低いという結果になる。ただしピケティは、「誤解してもらっては困るが、日本とヨーロッパの国民所得比で2、3ポイントの増大が、所得格差の著しい増大を意味することはまちがいない」と念を押している。
この図からは、歴史的には各国とも1910年前後にピークだった格差が1940年代まで急激に小さくなり、それが1970年代までつづいていたこともわかる。その時代的傾向を、もっと長期にわたって示す図がある。
・ヨーロッパでの資本/所得比率 1870─2010
これは英仏独の3国で民間財産(土地、建物、諸設備、金融資産など)の総価値が、その国の国民所得の何年分にあたるかを示したもの。3国で長い時間をかけて蓄積された富が、その国の国民所得の何倍あるかがわかる(日本は仏独と似た傾向を示す)。その数字は1910年にピークに達したあと急激に低下して1950年に底を打ち、以後上昇している。「この『U字曲線』は、圧倒的に重要な変化を反映したもの」とピケティは言う。
1910年以降にその比率が急減したのは言うまでもなく2度の世界大戦と、それに挟まれた大恐慌の結果によるものだ。戦禍がもたらした資産の破壊、インフレ、破産、国有化、植民地独立による資産接収などによって各国の富裕層の財産は急激に減り、貧富の格差は小さくなった。その格差縮小は、各国政府が累進所得税や累進相続税、累進資本課税を導入し、各種の資本規制や最低賃金を上げるなどの公共政策を取ったことによっても維持された。
蓄積された富の比率が1970年以降に国民所得に比べ急増したのは、累進課税の最高税率を劇的に低くしたことや、国有企業の民営化などによるが、もっと大きな理由は先進国が低成長の時代に入ったことにある。また人口増加が鈍化したことも影響している。そんな社会では、富をつくりあげる上で相続される財産や、投資された資本の利益が重要になる。財産は大きければ大きいほど、利益を得るチャンスも多くなる。ピケティはそのような社会を「世襲型資本主義」と呼んでいる。
資本の収益率(r)は先進国では18世紀から21世紀までずっと年率3~6%の間に収まっている。一方、経済成長率(g)については、先進国で長期にわたって年率1.5%以上になったような「歴史的事例はひとつもない」。この資本収益率と経済成長率の差が、富が富を生み格差を増大させる基になっている。
ついでに言えば、戦後の日本や現在の中国の高成長は、先進国をキャッチアップする過程での一時的現象だった。「多くの人々は、成長というのは最低でも年3~4%であるべきだと思っている。歴史的にも論理的にも、これは幻想にすぎない」。もっとも、年1%の成長でも30年つづけば累積して35%以上になるから変化は激しく、「社会格差の構造や富の分配力学にとって重要な意味を持つ」。
ほかにも開発途上国の格差のすさまじさを示すデータや、各国ごとの歴史的特殊性がわかるデータなど、面白い図表がたくさんある。でもこの本を読むいちばん大きな意味は、数百年の歴史のなかで見ると僕たちはこういう社会のこういう段階に生きているんだとデータで納得させられることだろう。
このままでは社会が持続不可能なまで格差が増大すると警告するピケティの提案が、資産への国際的な累進課税であることもよく知られている。その場合、どんな税率を考えているのか。例えば、と言いながら彼は「100万ユーロ(1.3億円)以下の資産は無税、100~500万ユーロに1%、500万ユーロ以上に2%」と記す。
「かなり慎ましい」税率だが、「主要な目的は税源をまかなうことでなく、資本主義を規制すること」にある。「申告義務づけ法」のようなものだとも言うように、世界中で企業や最富裕層がどれだけの資産を持っているかの情報を明らかにすること、タックスヘイブンなどへの税逃れを許さない、といった狙いもある。
国際的な資本税を実現することは、もちろん簡単ではない。でも格差を縮小させるためにできることは、ほかにもある。所得税や相続税の最高税率を引き上げたり、最低賃金を引き上げたりすることが格差縮小につながったことはこの本が実証している。でももっと大事なのは教育と技能習得への投資、つまり人への投資だとピケティは言う。急がば回れ、ということだろう。
ところでこの700ページの本、買ったとき考えたより短い時間で読み通すことができた。ひと昔前に比べれば大きな活字が使われているせいでページ数が膨らんでいることもあるし、文章も大学教養課程の授業を受けているように丁寧に説明されている。たくさんの図表は、いろんなことを考えさせてくれる。そんなこんなで読書の楽しみを味わった一冊だった。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





