裁判官も人である【岩瀬達也】
裁判官も人である
| 書籍名 | 裁判官も人である |
|---|---|
| 著者名 | 岩瀬達也 |
| 出版社 | 講談社(330p) |
| 発刊日 | 2020.01.31 |
| 希望小売価格 | 1,870円 |
| 書評日 | 2020.07.17 |
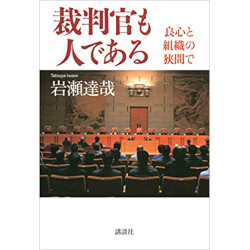
多様な事件の訴訟、裁判に関するニュースは毎日の様に報道されている。そうしたニュースを読みながらも、三権分立の中で、特に司法の独立性はそれなりに担保されると無意識のうちに思っている自分がいる。「裁判官、弁明せず」と言われる様に、裁判官は自らの下した判断に解説することはない。それだけに、司法の実態については自分から積極的に知ろうとしない限り時代とともに進んで行く法律解釈の変化を理解していくことは難しい。
本書では、裁判官が判決に至るプロセスを追いながら、死刑制度、原発の稼働、最高裁を頂点とする裁判所組織、人事評価や裁判官の独立性といった、現代の司法が抱えている課題を多くの視点から取り上げている。特に、「司法」は裁判所を運営する最高裁判所の司法行政部門があり、それは行政の一部であると著者は指摘する。別の言い方をすれば、「人事権と予算査定権を立法府と行政府に握られている最高裁判所は三権分立の理念を実践できていない」という主張である。それを示すために本書では日々の裁判官の仕事の中で発生する判決で、国策を否定したり、各分野の違憲判決や最高裁判例を覆さざるを得ない判断によって発生する裁判介入や人事異動、評価への影響などを描いている。
国策に対する裁判として、原発の再稼働時の判決が取り上げられている。一連の裁判は、2006年金沢地裁は北陸電力の志賀原発2号機の安全対策が不十分として原発の停止を判断したことに始まる。2011年東日本大震災による東京電力福島原発の事故の後、2014年福井地裁での樋口裁判長は大飯原発の安全技術と設備は脆弱であるとして3号機と4号機の停止判決を出した。以降、高浜原発3-4号機の再稼働禁止、川内再稼働容認、伊方原発の再稼働容認、伊方原発の再稼働禁止、伊方原発再稼働容認といった形で原発再稼働の禁止と容認の判決が行ったり来たりの歴史を繰り返している。
ただ、2013年に最高裁判所は「高度な専門性が求められる原発の安全性を専門知識の無い裁判官が判断するのは難しい。従って、裁判官は行政側の審査基準が正当で、その審査過程で大きな手続き的欠落がないかを審査し、安全性の独自の審査には自省的であること」という意見を研修資料に取り入れている。介入ではなくガイドラインであると言い張るのだろうが、それは無理である。こうした状況下においては、原発再稼働を止めた裁判官と再稼働を認めた裁判官のその後のキャリアを見ると、法律議論以前に国策に逆らった裁判官に対する処分と言わざるを得ない。
また、裁判官への介入が公になったのが札幌地裁で行われた「長沼ナイキ事件」である。地対空ミサイルのナイキを配備するために保安林を伐採しようとした国に対して住民が起こした訴訟である。第二次安保闘争など騒然とした社会状況の中の1969年に札幌地裁の福島裁判長は「憲法違反の恐れのある自衛隊のために保安林指定解除処分の執行を停止すべき」と判決を出したのだが、その判決内容が国に告知される前に平賀札幌地方裁判所長が福島裁判長宛てに「国側の主張を認めるよう求めた」書簡を届け、結果その書簡が外部に流出したという事件である。
青年法律家協会の裁判官部会の世話人をしていた宮本は福島と同期で、平賀書簡の外部流出の犯人と最高裁から疑われ、青年法律家協会に参加していた裁判官達に対する差別(ブルーパージと呼ばれた)とともに、宮本は10年目の裁判官再任審査でただひとり再任されなかった。この問題は、裁判干渉が露骨に行われていた事実と人事権の使われ方の異常性である。ちなみに再任されなかった宮本は弁護士登録に必要な経歴保証書を最高裁判所に求めたが最高裁は発行を拒否したため、弁護士会の特例処置で弁護士登録が行われたと言う。
こうした、裁判官の職業人としての独立性を担保する仕組みの例として、裁判所法では「意に沿わない人事異動は応じなくて良い」という考え方が紹介されている。しかし、全国3000人の裁判官で構成されていることを考えれば、必然的に異動を前提にして育成・昇進をやって行かなければ組織運営は回って行かないのは目に見えている。毎年8月に裁判官は自身の健康状態、家族構成とともに次の異動の希望任地を記載するが、ここで「希望任地以外は不可」を選択すると処遇・昇進面で制約をうけることになるという。民間であれば社員は「希望」や「異動が出来ない理由」を上司に申告することはあっても、異動の発令が有ればそれに従うことになり、かりに「組織の指示に従わないとすれば、その結果「失う」ものもあるということは明らかだ。組織で仕事をする限り、裁判官の権利と考えてしまうと、問題を矮小化してしまうのではないか。職業人としての姿勢と組織の仕組みの両面を考えないと真の独立性の議論にはなりそうもない。
また、死刑制度そのものの問題提起している。現在、先進7ヶ国(G7)の中で死刑制度を続けているのはアメリカと日本だけである。戦後の憲法改正作業の時、GHQの法政司法課長だったドイツ系アメリカ人は死刑制度廃止論に立つ弁護士であったが、日本政府が死刑制度の温存を求めたため、あえて異議を唱えなかったという。この結果、現憲法下でも死刑制度は存続したが、一石を投じた事件として2011年に大阪で発生した放火事件(5名死亡)である。裁判長は死刑を宣告したが、この裁判では死刑は残虐な刑罰に当たるのかどうかが問われた。証人の一人であった元検察官の筑波大学教授が「絞首刑はむごたらしいとは言えないとは、実態を知らなさすぎる、と言わざるを得ない」と意見を述べている。検察官は死刑執行に立ち会う義務があるが、裁判官にはない。このため、死刑執行に立ち会ったこともない裁判官が「絞首刑は惨たらしくない」という判断がなぜできるのかと、裁判官を揶揄するような意見が紹介されている。こうした事例を読むにつけても、まだまだ、死刑制度に関しては議論が続く論点の様だ。
そして、気になった点がある。1968年に起きた尊属殺人事件で1969年宇都宮地裁は尊属殺人条項は違憲という判断をし、過剰防衛であるものの情状の余地ありとして刑を免じた。本来尊属殺人は死刑もしくは無期懲役であり、東京高裁は一審判決を破棄して情状懲役酌量のうえ3年6ヶ月の実刑判決を言い渡した。この判決にたいし世論は極めて批判的で1973年に最高裁は尊属殺人の違憲判断をするに至る。しかし、尊属殺人の条文が刑法から削除されたのは1995年の改正刑法である。何と時間の掛かることかと思う。司法判断から立法までの道のりの長さは気が遠くなる様だ。
裁判員制度がスタートして10年を超え、6万人以上の国民が裁判員として裁判に参加している状況を考えれば、自分自身が裁判に出席して人を裁くことはもはや他人事ではない時代になっていると思う。裁判員裁判制度の評価をするにはまだ早いのかもしれないが、裁判員裁判では裁判員は被害者の立場がストレートに出るため、量刑的に厳しい判決になりやすいと言われている。しかし、本来、法理だけではなく、社会経験からも判断するということが裁判員裁判の目的だとすると、その目的を果た結果ではないのかと思う。自分が人を裁き、量刑判断しなければならない時が来ることを想定しながら本書を読みながら、今更ながら裁判官という職業の大変さを実感する。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





