志ん朝の落語(1)【古今亭志ん朝】
志ん朝の落語(1)
志ん朝伝説のはじまり
| 書籍名 | 志ん朝の落語 |
|---|---|
| 著者名 | 古今亭志ん朝 |
| 出版社 | ちくま文庫(464p) |
| 発刊日 | 2003.9.10 |
| 希望小売価格 | 950円 |
| 書評日等 | - |
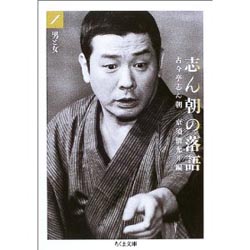
全6巻で刊行がはじまった「志ん朝の落語(1)」の第1巻。一昨年秋に亡くなった志ん朝の高座を活字化したもので、この「男と女」には、「明烏」「品川心中」「お直し」なんかの有名な廓噺(くるわばなし)から「真景累ケ淵豊志賀の死」のような人情噺まで、色恋をテーマにした12編が収められている。
僕が買った本の奥付には「2003年10月30日第3刷」とあった。発売後2カ月足らずで2回も増刷しているのだから、着実に売れているのだろう。
志ん朝の落語(1)は、すでにCDとしてさまざまなタイトルで発売されている。この全6巻に収められた噺も、そのほとんどがCDで聞けるはずだ。CDには当然のことながら志ん朝のしゃべりや客の笑い声がそのまま収録されているから、どちらが生の志ん朝や場の空気を彷彿させるかといえば、CDのほうに軍配があがる。
でも、この本を読む楽しみは、CDを聴いて志ん朝の生の声に接するのとはまた別のところにある。活字と活字のあいだから志ん朝が、あの歯切れのよい口調や息づかい、照れたときの少年のようなはにかみまで見せて立ち上がってきて、誰かがうまく言いあてていたけれど、まるで志ん朝の幽霊を目の前にしているような気分になるのだ。
僕はとりたてて落語ファンではないし、熱烈な志ん朝ファンでもない。志ん朝の高座を2度ほど聴いたことがあり、後はテレビかラジオ、亡くなったあとCDを数枚求めたという程度にすぎない。それでも志ん朝の「幽霊」を眼前にした。
これは、どういうことなのだろう。
この本に志ん朝の霊を宿らせたいちばんの功労者は、なんといっても編者の京須偕充だ。こうした口演を活字化するのはなんでもない作業のように見えて、実際には大変な技術と深い理解を必要とする。漢字と平仮名、平仮名と片仮名をどう使いわけるか。振り仮名をどう振るか。言葉と言葉のあいだの間を、どう表すか。しゃべる勢いや語尾のニュアンスをどう伝えるか。そのために、句読点をどう打つか。
僕自身もそうした作業に多少の経験をもっているが、その目からみて、京須の仕事には非の打ちどころがない。そんな見事な仕事を読んで、気がついたことをメモしてみたい。
まず、噺を耳で追うのと、活字化されたものを目で追うのとでは、噺に対する理解がぐんと違ってくることだ。噺の隅々までおぼえている熱心なファンを別にすれば、活字を読んではじめて、ああここはこうなっていたのかと分かることも多いはず。例えば「明烏」のこんな一節。
「いい年ごろの男がだよ、毎日[まいんち]毎日家[うち]イ閉じこもって本ばかり読んでんだよ。その本だっておもしろくない本だよ、ねえ。「シーノタマァク(子曰く)、シーノタマァク」なんて火[し]の玉ばっかり食ってやがン。火の玉食うから赤くなるかと思ったら蒼くなってんだよ。しょうがないよ、あれじゃア、ねえ」([ ]内は振り仮名)
寺子屋で教えられ、おそらく江戸っ子の誰もが耳にした「論語」の「子曰く」と、火の玉が江戸弁で「シノタマ」になることをかけた洒落なのだけれど、CDで聴いているときにはなんのことか理解できなかった。
この「明烏」にかぎらず、志ん朝は江戸に生まれた落語を僕らにも納得できるよう、かなり手を入れて現代化しているけれど(巻頭の、そこここに直しの入った若い時代のノートが興味深い)、それでも耳で追うだけでは理解できないところも多い。そこを、活字ではじっくりと考えることができる。
CDでは分からない志ん朝の動作や表情を補ってくれるのも、活字のありがたいところだ。これも有名な「お直し」から。
「(多少言いにくそうに)うん、それがね、今階下[した]でね、若い衆[しゅ]にちょっと話をしたン…。そしたらね、あの…、「二階[うえ]行ってそう言やァいい」と…。「階下でおれがそう言ったから」って、そう言ったよ、若い衆が。う…だからね、(と金額を手指で示し)これでひとつなんとかしてもらいたい」「えッ?(指で同じ金額をなぞり)これ?これっぱかり?(頭から否定し)だめよォそりゃア!」
ここでも、話の中身や動作をどこまで注をつけて補うかはとてもむずかしい問題だ。引用したのは全体のなかで目立って()の多い部分だけれど、その注をなくしてしまえば話の進行が分かりにくくなり、かといって増やしすぎては野暮になる。総じて京須の判断は適切で、程のよい注になっていると思う。
活字を読んではじめて気がついたこともある。高座やCDではなんとなしに聴いていたが、志ん朝の語りは語尾に工夫がこらされて、かなり丸められていることだ。
「大変な売れっ妓[こ]でございます。ところが今言ったように、どうも歳にゃ勝てないン、ねえ?」
「やっこさん泳げないもんですから、あっぷあっぷしながら。クワァーッてんで手を伸ばすってえと、うまい具合に桟橋の杭を掴んだン。ありがてえってんでガアーッって足を伸ばすってえと、品川は遠浅だから膝[しざ]までしかないン」
志ん朝が「勝てないン」「掴んだン」と発音しているところを、「勝てない」「掴んだ」では文章語に近くなってしまうし、「勝てないんです」「膝までしかないんですね」ではリズムが悪くなる。そこを「ン」で語尾を丸めて噺のリズムをととのえる。聴いている僕らは「ン」がなにを意味しているかを無意識のうちに補って聴いている。
それからこれは「週刊文春」で高島俊男が指摘していたことだけれど、「できる」という意味の「られる」が「らいる」になるのも、活字になってはじめて気がついた。
「へッ?どしたんだい?お、お前、よくここへ一人で来らいたね」
「一番しまいのその、ブタキュウってのァなんだい?」「豚が灸[きゅう]据えらいたときのような顔してるってんだァ!」
いくらでも引用したくなってしまうが、このへんで止めておこう。江戸弁あるいは東京弁で、「らいる」が実際にどの程度使われていたのかは知らない。ひょっとしたら、今でも下谷あたりの老職人が「らいる」と発音しているかもしれない。でも語尾の「ン」にせよ「らいる」にせよ、実際の江戸弁や東京弁でどれだけ使われていたのかを詮索するより、現実からひとまず離れた志ん朝の芸の言葉だと解するほうがいいのだろう。
最初の問いに戻ろう。CDの生の声ではなく、活字から立ち上がる志ん朝の魅力とはなんなのか。
この本の読者が活字を追いながら脳裏に思い描く志ん朝の像は、なんといったらいいか、ちょっと抽象化されているように思う。例えばCDには、録音されたある日の志ん朝の生の声や客の笑い声がそのまま記録されている。だから僕らはそこで、具体的な日付のある、その日の声の張りや調子の良しあしを持った志ん朝を聴いている。
もちろんこの本も、ある日の志ん朝の口演を活字化したものだ。けれども僕らは活字を追いながら、「その日」の志ん朝ではなく、僕らが体験した高座やテレビやラジオやCDの志ん朝の記憶のなかから、その活字にいちばん合った像を探しだし、そうしたイメージの断片を組み合わせて、自らが理想的だと考える志ん朝像をつくりあげている。
これは、ひょっとして神話あるいは伝説というものが誕生する瞬間ではないか。そうしたフィクショナルな像の深度と、その像を共有できる人々の広がりとを掛け合わせたものが、神話化の度合いをはかる目安になるのではないか。だからこの本は、古今亭志ん朝伝説のはじまりなのだと思う。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





