さよなら渓谷【吉田修一】
さよなら渓谷
| 書籍名 | さよなら渓谷 |
|---|---|
| 著者名 | 吉田修一 |
| 出版社 | 新潮社(208p) |
| 発刊日 | 2008.6.20 |
| 希望小売価格 | 1470円(税込み) |
| 書評日等 | - |
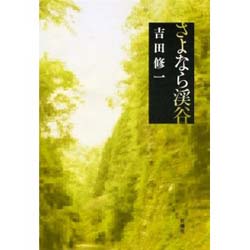
私ごとから始めるのをお許しいただきたい。
小生、1年ほどニューヨークに滞在していた。8月中旬に帰国して1カ月。まだ日本の日常に復帰しきれていない。電車に乗っても町を歩いていても、ニューヨークと違ってやけにきれいで清潔で静かで、なんだかアメリカからまた別の国に来たみたいで、自分が半世紀以上も暮らして慣れ親しんだ国に戻ったという実感がない。
それと関係あるのかどうか、1年ぶりにこのレビューを書こうと新刊を読みはじめたけれど、2冊試みて2冊とも最後まで読み通せずに放り投げてしまった。どちらも興味あって買った本なんだけど、身体のどこかが醒めていて忍耐がきかない。
ちなみにその2冊とはロバート・B・ライシュ「暴走する資本主義」(翻訳)と池上永一「テンペスト」。3冊目に挑戦して、ようやく読み通したのが「さよなら渓谷」だった。人によっては、挫折した2冊のほうがずっと面白いよと言うかもしれない。
小生が「さよなら渓谷」のどこに反応したのかといえば、この国を覆っている空気について考えさせてくれたからだ。
都心へ行こうと郊外からJRに乗る。朝の通勤時間を過ぎた電車は座席の6、7割が埋まっている程度。ほとんどの乗客は寝ているか、あるいは無言で携帯をのぞきこんでいる。互いに無関心で自分の世界に閉じこもったままの車内の空気に、この国に帰ってきたんだなあと思う(ついでに言えば、本を読んでいる人がほとんどいないのにも改めて驚く。ニューヨークの地下鉄では単行本を読んでいる人がたくさんいる)。
あるいは夜、都心から郊外に帰るとき、空いている席を見つけて座る。隣に腰掛けて脚を広げていた若い男にわずかに触れたからか、男が冷たい目でこちらをちらりとにらむ。車内は静かだけれど、その裏に冷たい敵意と殺気が流れていて、それがいつ爆発するか分からないような緊張を感ずる。
ニューヨークの地下鉄は良くも悪くも単純明快だった。
知人同士は乗ってから降りるまでスペイン語や中国語でしゃべりまくっているし、電車が地上に出て携帯が通じる場所にかかると一斉に通話が始まる。音楽やダンスのパフォーマンスで金を集めるグループ、あるいは何の芸もなく小銭をせびる物乞いもいる。かと思うと、意味不明の言葉をつぶやきながら怒鳴りつづける男もいて、車内はいつもにぎやかだ。
そんなニューヨークの地下鉄とは対照的に日本の電車は静かできれいだけれど、そこに流れているのは他者への無関心と、それと裏腹の他人への密かな敵意であるような気がする。車内に流れている空気は、それを呼吸する者に同調を強い、一見、秩序は保たれているけれど、何かのはずみで他者が自分の小さな空間を侵害したと感ずると一気に敵意が噴出しそうな、べっとりと気味の悪い空気を感ずる。
「さよなら渓谷」にはこの国を覆うそんな空気が充満していて、その空気が乱されることから、他人にはほとんど見えないけれど一組の男女にある悲劇的な崩壊が起こる。
舞台は東京郊外。秋川渓谷が想定されているらしい、川沿いの市営団地だ。渓谷で幼い子供の死体が発見されその母親に嫌疑がかかって、彼女は今日明日にも逮捕されようとしていている。……と書けば、誰でも現実にあった事件を思い浮かべるだろう。
もっともこの小説は、子殺しの母親が主人公なのではない。主人公は、殺された子供とその母親が住む家の隣に住んでいる30代の男と女。彼らの家の周囲には母親を取材しようと報道陣がつめかけている。カップルが隣家の母親とわずかな接触を持ち、ひとりの週刊誌記者が周辺の住民に話を聞いてまわることから、カップルの間に小さな亀裂が生まれ、彼らの過去の「秘密」が徐々に浮かび上がってくる。
小説の舞台に想定されている秋川は都市近郊の美しい渓谷だけど、その地名には同時に禍々しい記憶が重なっている。
1980年代、秋川渓谷で全裸殺人事件があった。岩の間に折り畳まれるように捨てられた女性の死体は報道陣が詰めかけてもまだそのままで、当時、隆盛を極めた写真週刊誌の格好の餌食になった。これは想像だけど、「渓谷」という言葉に吉田修一はそんな過去の禍々しい記憶も織り込んでいるように思える。
「さよなら渓谷」はミステリー仕立てになっているのでネタバレは避けるけれども、その「秘密」に触れないとレビューも書きづらい。内容ではなくスタイルについて語ろうか。
この小説が連載されたのが「週刊新潮」であることに注意しよう。「週刊新潮」は数ある週刊誌のなかでも男女のスキャンダルを売り物にしていることは誰でも知っている。なかでも創刊以来40年以上つづく「黒い報告書」は、男と女の事件を素材にした読み物として、かつて梶山季之なども書いたことのある定番中の定番連載だ。
この小説はフィクションだけれども、明らかにこの連載を念頭に置いている。主人公の設定も、ストーリー展開も、「黒い報告書」の通俗的な枠組みを踏まえて、あえてそこから大きくはずれることをしない。
副主人公に週刊誌のレポーターを据え、彼の調査でカップルの「秘密」が暴き出されてくることも、いわば週刊誌レベルで物語を展開させ、文学的な深み(?)に必要以上に踏み込まないための意識的な選択であるように思える。もっとも、そのレポーターも妻との間に問題を抱えており、第三者的な語り手ではなく主人公カップルの揺らぎに共振していく構造になっているのが面白い。
砂利敷きの広場を囲んで平屋が並ぶ市営団地。住んでいるのは主人公のような契約社員だったり、殺された子供と母親のような母子家庭だったり、管理組合の会長のような老人世帯だったり、いわば「正社員」とは無縁の社会。
そこに犯罪とジャーナリズムの覗き見的好奇心が絡むことで、団地の平穏な空気が乱れはじめる。「秘密」を抱えたままそれなりに安定し、「幸せになりそう」だった男と女の生活が崩れはじめる。
その息苦しい空気を吉田修一のクールな文体が掬いあげる。
「汗びっしょりのシャツや靴下を玄関で脱ぎ、「ただいま」と声をかけて居間へ入ると、扇風機を抱くようにして、椅子に腰かけているかなこの背中がある。
Tシャツは着ておらず、よほど暑いのか、ブラジャーのホックも外している。
「ただいま」と俊介は改めて声をかけた。
「おかえり」と振り向いたかなこのうなじで、貼りついていた何本かの髪の毛が扇風機の風で靡く。
「外、すごいことになってるよ」
俊介は椅子の背にかけられていたタオルで、汗の噴き出す顔を拭いた。かなこが使ったものなのか、微かに自分とは違う誰かの汗の臭いがする。
かなこの足元に新聞の折り込み広告が散らばっていた。一番上に求人広告があり、時給七百八十円のスーパーのレジ係の募集欄に、鉛筆で○がつけられ、その○が赤ペンでグチャグチャに消されている」
冒頭、男と女が「過去」を抱えたまま人目を避けて暮らすそれなりに安定した日常に、隣家に事件が起こることで微妙な揺れを生ずるシーン。髪の毛や汗や新聞のチラシの微細な描写が2人の生活ぶりをリアルに伝え、同時に読者のかすかな不安を呼び起こして見事だ。
吉田修一は「東京湾景」みたいな都会的な恋愛小説も書けば「長崎乱楽坂」みたいに中上健次ばりのサーガも書く多彩な技を持った小説家だけど、この作品は現実の事件を想起させる前作「悪人」と同系列の、犯罪を素材にした物語だ。
もっとも「悪人」のようにぐいぐいと登場人物の内側に入り込んでいくのではなく、週刊誌連載小説として「黒い報告書」吉田ヴァージョンとでもいった軽い仕上がりになっている。「悪人」みたいに濃厚な世界を期待するとはぐらかされるけど、さらりとした仕上がりもまた吉田修一の技のうちということか。
物語も終わり近く、主人公の男と、彼を追う週刊誌記者との対話が心に残る。
「「だから、俺と彼女、幸せになりそうだったんです」
「だ、だったら、なればいいじゃないですか!」
思わず上げた渡辺の声が、暗い渓谷に響き渡る。その声に、尾崎が小さく笑う。
「……無理ですよ。一緒に不幸になるって約束したんです。そう約束したから、一緒にいられたんです」
「でも」と言いかけて、渡辺は言葉を呑んだ。
インタビューの最後で、かなこの呟いた言葉がふと蘇る。
「私がいなくなれば、私は、あなたを許したことになってしまうから」
彼女は尾崎にそう言ったのだ。
姿を消せば、許したことになる。一緒にいれば、幸せになってしまう。「さよなら」と書き置きしたかなこの言葉が、渡辺の胸に重く伸しかかる」
廣木隆一監督、浅野忠信・寺島しのぶ主演で映画化してほしいなあ。あるいは韓国のキム・ギドク監督に。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





