続 昭和街場のはやり歌【前田和男】
続 昭和街場のはやり歌
| 書籍名 | 続 昭和街場のはやり歌 |
|---|---|
| 著者名 | 前田和男 |
| 出版社 | 彩流社(240p) |
| 発刊日 | 2024.05.16 |
| 希望小売価格 | 2,420円 |
| 書評日 | 2024.09.17 |
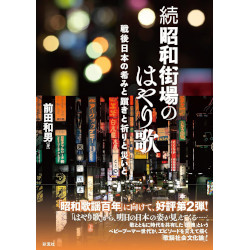
本書は、戦後日本社会で喧噪の街の中やラジオ・テレビなどから流れていた楽曲を取り上げて、その歌詞や曲に込められた意味や歴史を考察している。作る側の視点も然りながら、聴く側の思いも著者自身の感覚を素直に出して語っている。著者は私と同じ団塊の世代、いわゆるベビーブーマーの1947年(昭和22年)生まれ。ただ、本書を読み進んで行くと、同じ社会状況に身を置いていたとしても、その体験感覚の違いは多々あって、世代論として一括りで語る事の難しさも明らかである。著者が「我々の世代は」といっても体験の爪痕と記憶の残され方は当然一様ではなく、その感覚差を否定ではなく「そんな風にも受け止める奴も居るか」といった許容の中で語れるのが同世代ということか。
タイトルは「はやり歌」となっているが、取り上げている楽曲は単に「売れた」とか、「歌謡曲・流行歌」というだけでもない。なにしろ、冒頭に取り上げられているのは「軍艦マーチ」からも想像出来るように、幅広い楽曲から曲の持つ「裏面・細部」からその社会性を語り、昭和の原風景を描いている。本書は大きく4つのテーマで構成されている。一つは1945年(昭和22年)8月15日で区切ることなく戦前と戦後の繋がりを示す楽曲をテーマとして「軍艦マーチ」、「交響曲第九」、淡谷のり子の「別れのブルース」を取り上げている。二つ目の視点は「復興の光と影」と題してマドロスもの、銀座にまつわる楽曲、企業キャンペーンソングの台頭を取り上げている。三つ目の視点は戦後社会でのプロテクトソングを取り上げている。「練鑑ブルース」とともに「上を向いて歩こう」も取り上げられている。「上を向いて歩こう」がプロテストソングとはいささか違和感もあるが、作詞家の永六輔が語って来た言葉を拾い集めながら作詞意図を探っている。そして最後の章では「宴の終焉」と題し「知床旅情」や「石狩挽歌」といた楽曲を取り上げている。終焉と言いながら、それは著者自身の感情であって、若い世代からすれば、次に平成・令和が続くわけで、時代の連続性を語る歌謡史がまた作られていくのだろうと思う。何が引き継がれ、何が終わったのかは有るにしても、複数の世代が共存して歴史を刻んで行くことを考えると、団塊の世代が満喫した「昭和」の終焉が次の世代に重くのしかかるということなのだろう。
戦前戦後の繋がりの象徴として「軍艦マーチ」についての歴史を紐解いている。軍艦マーチは1893年(明治26)に「軍艦」として小学唱歌に取り入れられ、1900年に横須賀海軍軍楽隊によって行進曲として改作編曲され、1933年(昭和12)に東海林太郎の歌が国民的愛国歌としてヒットするとともに、大戦中は大本営海軍部のラジオ放送のテーマ曲として使われた。戦後は当然のことながら「禁歌」とされ、日比谷公園にあった「軍艦マーチ」の歌碑も1947年に撤去されている。しかし、1951年(昭和26)に有楽町のパチンコ店から突然大音量の軍艦マーチが流れ出した。これは元海軍軍属の店主田中が「厳罰」を覚悟の上で銀座の米兵闊歩とバンバンの狂乱に辟易したことから「禁制の軍歌」による決起だったという。田中はGHQに連行されたものの、お咎め無しで決着している。その理由を「GHQとしては、占領最終期で冷戦が激化している中、日本がアメリカの擁護の下で『良き番犬』として手元に置くことによる軍事同盟の強化が得策と考えた結果」と著者は見ている。
加えて、「軍艦マーチ」に関する象徴的な事例が、1987年に米国で開催された第9回サミットにおいて、中曽根首相を歓迎する式典で米国陸軍軍楽隊によって「軍艦マーチ」が演奏されたという。当時新聞各紙でも批判的に取り上げられていたが、私は良く覚えていない。
曲の持つ意味とその使われ方の象徴性も時代とともに変化するという例なのだろう。
戦後復興のはやり歌の象徴としてはマドロスものや、銀座に係わる楽曲だったと思う。軍艦マーチの復活、「君の名は」等は銀座が舞台となり、そして「銀座カンカン娘」がお洒落な若い娘たちの盛り場としての銀座の華やかさを発散させた。地下鉄銀座線の銀座駅の発車メロディ開始以来、現在に至るまで「カンカン娘」がホームに鳴り響いている。
復興・経済活動の象徴が1957年(昭和32)にリリースされたフランク永井の「有楽町で逢いましょう」だ。有楽町の読売新聞社ビルに大阪のそごうデパートが開店するに際して、大々的なキャンペーンを行った一環である。同名のTV歌番組をスタートさせ、同名小説を週刊誌で連載開始、翌年には京マチ子主演の映画上映と、あらゆるメディアを活用したキャンペーンだった。当時小学生の私としては、そごうとの関連を知る由もなく、フランク永井の低音歌唱に面白さを感じながら歌番組を見ていただけであった。こうしたキャンペーンソングとともに銀座の持つ底力を再確認させられる。
こうして銀座から戦後の新しさが生まれ語られてきた。巣鴨で育った私は小・中の頃は繁華街と言えば池袋だったが、高校になると親には日比谷図書館に勉強に行くと言いながら、有楽町で下車してそのままジャズ喫茶「ママ」に行ってジャズを聴いていたし、学生時代は映画は有楽座、日比谷映画、日劇地下のアートシアターに通い詰めていた。そして、鉄道模型を趣味にしていたので銀座の天賞堂の2-3階の鉄道模型売り場は夢のような場所であった。私にとって銀座・有楽町はオシャレの場でも会食・交際の場でもなく、「趣味」の場として重要な町だったことを今更ながらに思い出す。
1961年に「上を向いて歩こう」が中村八大作曲、永六輔作詞、坂本九の歌唱でリリースされた。この頃永六輔は「60年安保の騒乱で樺美智子さんが亡くなったとき、僕もデモに参加していたこともあり、そうした挫折感があったことから『遠くへ行きたい』『上を向いて歩こう』『見上げてごらん夜の星を』等を作詞した」と60年安保の挫折組曲だったと語っている。しかし、彼の意図とは別に「上を向いて歩こう」は失恋の歌として聴き、歌っていた人は多かったのではないかと思う。また、「上を向いて歩こう」の録音に立ち会っていた永は坂本九の歌唱法について「これではヒットしない」と激怒したものの、結果は大ヒット。2年後にはビルボードチャートで第一位を取ることになるが「SUKIYAKI」は日本語歌唱のまま歌われていた。この点も作詞家永六輔としての居心地の悪さを感じていたはずである。
しかし、永六輔自身「上を向いて歩こう」の作詞意図を2012年のTBSの番組で「あの曲は小学校高学年の男の子が悲しい事あって涙がこぼれそうになった時、空を見上げてこらえようという想いを描いた」と全く違う作詞意図を語っている。また、中村メイコの永六輔追悼秘話という文章が紹介されている。
「私は永君と神津君と三人で仲良くしていた。何年か経って私が神津君と婚約発表すると永君に告げると、彼はポロポロとべそをかいた。男の子の涙なんて気味が悪いから公衆電話で父(作家中村正常)に相談したら、『(父は)上を向いて帰りなさい。涙がこぼれない様に』 というんだよと電話の向こうで笑っていた。それを私は永君にそのまましゃべって、あの歌になったの・・・」
もはや、「上を向いて歩こう」の真の作詞意図は判らないが、まあ、聴く側、歌う側の思いで楽しめばいいのだから、素晴らしい歌で有ることは変わらないという事だろう。
最終章「宴の終焉」と題して昭和の終焉を語っているが、取り上げられている楽曲は「落陽」「知床旅情」「石狩挽歌」など全て北海道に関わる曲である。団塊の世代としてその意味も分かる気がするのだ。1960年代後半学生運動の最中で多くの学生同様、私もリュックを担いで利尻島、礼文島、網走など一人旅をした。駅の待合室で横になったりしながらの旅だった。1970年に社会人となり、仕事に没頭する日々が続く状況で、1971年の加藤登紀子「知床旅情」や旧国鉄のデイスカバー・ジャパンの宣伝は、過ぎた日々を振り返るちょっとした気分転換でしかなかったというのも過去に振り向くちょっとした刺激でしかなかったというのも辛い思い出だ。
歌の力を考えさせられるとともに、私自身が昭和であることを思い知らされた読書だった。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





