周恩来秘録【高文謙】
周恩来秘録
| 書籍名 | 周恩来秘録 |
|---|---|
| 著者名 | 高文謙 |
| 出版社 | 文芸春秋(上下共400p) |
| 発刊日 | 2007.2.27 |
| 希望小売価格 | 上下共1950円+税 |
| 書評日等 | 上村幸治訳 |
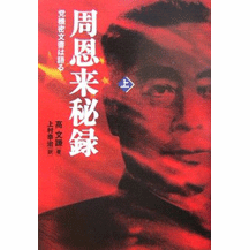
「晩年周恩来」と題された原書は2003年にアメリカで出版され、直後に中国当局から発禁処分を受けたという。
著者は中国共産党中央文献研究室委員で周恩来生涯研究小組組長も努めた後、天安門事件で民主化運動に好意的であったとして事件後に処分を受け、現在米国に暮らしている。文化大革命から天安門事件と続く中国の混乱の中で祖国脱出を余儀なくされた典型的な知識人ともいえる経歴である。
1966年の文化大革命から1976年の死去までの十年間を主たる対象として公的な記録に従い記述しているのだが、「周恩来」を語ることとは「毛沢東」を語ることそのものであると再認識させられる。しかも、二人の関係は合理性とか政治的とかいう概念・理念からは明らかに外れたところにあるドロドロとした権力闘争の中で作り上げられて行ったこともよく判る。毛沢東の周りには権力闘争しかなかったと言って良いのかもしれない。
文化大革命の勃発から周恩来の死去という期間は私にとってひどく長い時間であったように記憶している。しかし、現実はたった10年というその短さを再確認するとともに、何故それほど多くの事象がこの10年間に起き、人が斃れ、心が荒廃していったのかを考えると、文化大革命という表層の理解ではなく、表面下に存在する権力闘争の理解が必要であり、それはほとんど中国にとっては悲劇だったということだろう。そして、その事実はまだまだ十分に公開されているわけではない。著者は本書を書いた目的を次のようにいっている。
「第一は周恩来を改めて評価し、周の身辺に塗りたてられた絵の具を拭き取り、その歴史に本来の姿を取り戻させること。第二は中国当局が意図的に覆い隠してきた文革の黒幕と指導部内の政治のでたらめさ、その暗黒と凶暴な部分を暴露し、中共政治文化の根底に根ざす皇帝型権力専制主義を掘り出すことにあった。・・・・・」
全体を通して語られる「周恩来」の姿は、「毛沢東」の影と力に常に怯えながら、あらゆる自己犠牲をもって皇帝に仕える実直な官吏といった感がある。また、同時に毛沢東は周恩来が敵側につくことを極度に恐れていたということもよく判る。この葛藤を明らかにするために本書は書かれているといっていいだろう。毛と周はともに中国の南方の出であったが、かなり違った環境で育ち考え方や行動に差があったといわれている。著者としての視点の一つがこの相違である。
「毛は独裁的、厳格粗暴な父親に抑えつけられ、また湘楚文化の伝統に影響され幼時から伝統に反抗し権威を蔑視し、個性を振り回す反逆的な性格を養ってきた。周は文人の家柄の養母に育てられ、幼い頃から穏やかな愛情に包まれて育ち、江浙文化の薫陶を受け、人となりや処世は温良で慎ましい儒家的色彩を帯びていた。」
こうした違いを内在した中で、抗日戦争時における両者の中国共産党内でのイニシィアテブのあり方は非常に興味深い。この時期、かなりの期間において周は立場的には毛の上に存在していたし、抗日戦争のターニング・ポイントとなる幾つかの中国共産党内の重要な会議で果たした周の力について言及している。それは、今まで語られてきた毛が常にリードしてきたと言われている公式の見解と異なり周の主導性の発揮や、毛も周を味方につけるために腐心していた状況を活写している。その後、大躍進政策・人民公社の設立などの施策が混迷を深める中で1959年、国家主席を劉少奇に渡すものの、数年の後に文化大革命を引き起こす。
そして、劉少奇の粛清。文革陣営の分裂、林彪のクーデター未遂と逃走による飛行機墜落死、という大混乱が続くわけだが、毛は常にナンバー2を潰してきた状況を克明に記載している。こうした中で毛の周に対する思いは揺れていた。特に、毛自身の病が重くなり、自分が周恩来より長く生きられないのではないかと心配するようになったことによる。周がもし自分の死後に率先して文革の評価を覆したら、周の党内外における声望と手腕によって皆がいっせいに周に賛同する。そんな毛の姿勢が示されたのが林彪の死後、周の病に際して示されたと紹介している。
「1972年5月中旬、毎月の検査で膀胱移行上皮細胞癌と診断された。まだ、早期で治癒率は80-90%と考えられたため、早期の手術を医師団は進言した。しかし、毛沢東の主治医に対する返答は、秘密にして総理と夫人には知らせないこと、検査不要、手術不要、看護と栄養を強化すること。」
政治局委員以上の立場の人間に対する治療方針は毛沢東が最終決定するという仕組みは、このようなおぞましい事実を作っていたと言われている。
周の死後、毛は周恩来の追悼会に参加しなかった。永らくその理由は毛の病状によるものと言われていたが、本書で明らかにされているのはそんな奇麗事ではない。毛の為の車椅子のアプローチも準備され、医師団も一定の時間の参加は問題ないとしていたが、結果毛は追悼会に出席しなかった。そのとき毛はこう発言したといわれている。
「なぜ、私が総理の追悼会に参加しなければならないのか。私には参加しない権利があるだろう。偉大なるマルクス主義者などと誰が総理に贈った呼称だ・・・・・・」
読んでいて、気が重くなるような事実の列挙である。しかし毛沢東の死後、所謂四人組の裁判や華国鋒の進出、そして_小平がまたまた復権して中国をリードしたように、中国の政治のダイナミックさは明らかに毛沢東・周恩来を乗り越えて進みつつある。徐々にではあるが国内外に対して情報の公開も進み始めていると思われる。それにしても、「なぜ周恩来は文化大革命を止めなかったのか」という一言が最大の疑問として存在する。文化大革命が中国史においてあまりに多くの犠牲と破壊を起こしてしまった、と同時にそれを止められたとすると周恩来以外には誰もいなかったという事実こそがその質問の源なのだろう。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





