世界史を変えた独裁者たちの食卓(上)【クリスティアン・ルドー】
世界史を変えた独裁者たちの食卓(上)
| 書籍名 | 世界史を変えた独裁者たちの食卓(上) |
|---|---|
| 著者名 | クリスティアン・ルドー |
| 出版社 | 原書房(209p) |
| 発刊日 | 2022.07.25 |
| 希望小売価格 | 2,200円 |
| 書評日 | 2022.10.18 |
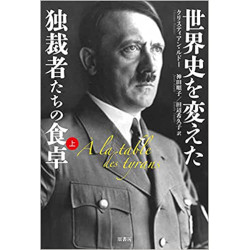
著者のクリスティアン・ルドーはフランス人の作家でパリのエリゼ宮で働くシェフたちを描いた作品や、各国のリーダーと食事をキーワードとしたテレビドキュメンタリー番組制作をしてきたというから、そうした活動の集大成が本書ということなのだろう。
「何を普段食べているものを聞けば、どんな人間なのかが解る」という言葉から本書は始まる。食べ物(料理)は個人の願望、社会的地位、育ち方などの象徴であるし、民族という観点で考えれば国の歴史もそこから辿ることも出来る。ただ、「元首や独裁者が公邸で食事をするときはけして一人ではないので、彼らの胃袋はもはや自分一人のものではない。独裁者の食事・宴会の場は血まみれの悲喜劇の舞台」と著者が言っている様に、我々一般人が仲間と楽しく食事を分かち合うという状況とは全く異なる食事環境だということに気が付かされる。本書は中国の毛沢東、中央アフリカ共和国のボカサ、ドイツのヒトラーを取り上げているのだが、独裁者たちの食事の小話を取りまとめているものではなく、食卓という切り口から独裁者たちの生きた時代と国家の状況を広く俯瞰して見せているとともに著者の独特(フランス人的)な視点も面白い所である。
第一章は毛沢東。長江で水浴びをしている毛沢東のデップリとした体形から始まる。1950年代の大躍進政策の失敗で全国民が飢饉状態でやせ細っていた中で、あの世界の注目が集まった肥満体映像を思い出すことが出来るのも我々団塊の世代の特権だろう。
毛沢東は湖南省の堅実な生活を送る父のもとで育ち、教師をしながら28才で湖南省の共産党代表になっている。地位が上がって行っても食事については地元料理(豚の角煮や羊のシャブシャブ)だけで充分満足していたものの、お気に入りの唐辛子は「真の共産主義者の鉄の意志を鍛えるもの」といった食を通しての政治的視点も忘れずに語っていたという。
大躍進政策で人民公社・大食堂といった制度を導入して農作物や鉄鋼製品の増産を図るが、技術的な未熟さから失敗を重ねた結果、20世紀最悪といわれる飢饉をもたらし1500万人以上の餓死者を出した。人民が飢餓に苦しんでいる厳しい状況が伝えられると毛沢東は「肉を断って粗食に甘んじる」と宣言して、「英雄的菜食主義」と宣伝させた。実際は肉の変わりに「武昌魚」といわれる長江産の新鮮な魚を食べ、ウミガメのスープを楽しんでいたということから、人民とはかけ離れた食生活だったことは歴然としている。
その後、文化大革命を通して国家中枢に君臨したが、世界各国の元首が北京を訪れても公的な宴会の場に毛沢東が出席することは無く、周恩来がホストを務めていた。「革命は客にご馳走をふるまう事ではない」という毛の言葉はけして比喩だけでなく、こうした現実の外交行事でも筋を通していたということなのだろう。
二人目の独裁者はジャン・ベデル・ボカサ。彼はフランスから1960年に独立した中央アフリカ共和国で軍事クーデターを起こして1966年大統領に就任している。ヨーロッパ各国はアジアやアフリカに多くの植民地・属国を持っていたが、第二次大戦後には各国が独立している。こうした独立国家にとって旧宗主国との関係は感情論を含めて多くの歴史的問題をはらんでいた。ボカサの父親はフランスの人種差別に異議を唱えたことから見せしめで処刑され、悲嘆にくれた母親はその7日後に自殺している。そんな体験を持っていても、彼は宗主国のフランス軍に入隊し25年間の軍歴を全うしたうえでフランスを第二の祖国として考え、独立後も二重国籍を維持していたという男だ。
大統領ボカサは郷土料理であるキャッサバの葉と肉のグリルで済ませるという位だったから、食に対する欲は強くなかった。そんな大統領の性格もあり、この国の公式レセプションでは形式はともかく、供されるアフリカ料理やフランス料理の味に対する各国要人たちからの評価は圧倒的に低かったという。
こうした中でボカサは「終身大統領」という民主主義とは相いれない立場に就き、さらに皇帝となって戴冠式を行うに至った。まさに茶番でしかないのだが、この戴冠式典ではクリストロフ社の銀のカトラリーやリモージュの皿などが使用され、フランス産の6万本のワインやシャンパンが運び込まれ国家の年間予算の1/4に当たる金額が消費されたという。
そんなボカサも、数年後にクーデターで失脚。フランスに亡命したが母国に残された公邸の冷蔵庫に人肉が保管されていたというシヨッキングな報道がなされた。この話に元料理人は、アフリカ各国からの賓客に食べてもらうための物であったという説明をしている。
フランス人からみたボカサの印象はばかげた戴冠式とこの人肉食の噂に集約されていて、ボカサを道化師のように馬鹿にしているのだが、ボカサが消費した金はほとんど旧宗主国のフランスに流れ込んでいるというのも忘れてはいけないと思うし、何故そこまでしてまで旧宗主国から認めてもらいたかったのかは理解出来ない。
三番目の主人公はヒトラーである。彼が敗戦を目前にして過ごしていたベルリンの地下要塞には大量に貯蔵された高級食材、お菓子、シャンパン、煙草などがあり、戦況悪化に対する不安を紛らわすことに役立っていたと聞くと、身体を維持するための食材と言うよりも心を維持する嗜好品ということなのだろう。「わが闘争」における自らの描写の要点は、ウイーンの美術学校に入学出来ず、雑役夫や売れない画家として暮らした5年間の空腹に耐えた事。そして、第一次大戦の兵役で規則正しい生活パターンを身に付けたという「苦労の体験」と「真面目な学び」の両面を示すことでドイツ再生のリーダーとしての正統性を示している。「労働者に仕事とパンを」というのはナチ党の公約だが、ヒトラーが仕事もなく飢えた原因は「ユダヤ人」ではなく自らの才能の無さによるものであるし、無思慮な生活の結果であるという著者の冷静な指摘は的を射ている。
「ヒトラーは煙草を吸わず、酒を飲まず、肉も魚も食べず、女にも手を出さない」と言われていたように彼は快楽主義とは無縁だった。こうした行動をとった原因として、ヒトラーは自分の外見が理想的なアーリア人という審美基準(肥満でないスマートさ)に近づけようとしていたと著者は見ている。
そんなヒトラーの食卓は彼の二つの顔を映し出す鏡だった。第一は「食事時間の不規則性、食事を共にする人同士の交流という社会的機能を奪い、ヒトラーの自らを称える演壇になっていた」というもの。もう一つの鏡には「気遣いと礼節に満ちており、特に若い女性に対しての礼節と父親のような温情に溢れた」ヒトラーがいる。
しかし、お気に入りの栄養士の女性に対する「人種純正証明書」の例外発行命令の話などを読むにつけ、この独裁者の自己中心的な温情に辟易とさせられるとともに、ホロコーストを生み出したのは「怪物」ではなく「人間」だったことを忘れるべきではないという著者の主張も納得出来る。
食卓の風景の主役は人と料理だが、自分でその風景を客観的に語る事は難しい。当たり前の様に食べている料理も、母親から作り方を教わっただけで、どんな時代を紡いで出来ているのかも知識として持っている訳でもない。ただ、人は食べなければいけないので日々の食卓は家族や仲間との重要な空間である。
一方、通常の公的な会食の場であれば、政治的やビジネス的視線が交錯しながらも文化や伝統といった基準が一定に保たれている空間が形成されて、談笑しながらの会食を通してお互いの狙いを伝えていくことになる。しかし、その席の中心人物が独裁者だとすればその人間の政治的思惑と自己中心的個性だけが際立って食卓の目的さえも意味を失っていくということは容易に想像できる。それは本書でも示されている様に、最早食事の為の場ではない。
ただ、本書のような視点からの分析の対象として面白そうな、近代日本の指導者・元首たちが見当たらないのも寂しいものではあるが。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





