2days4girls【村上 龍著】
2days4girls
| 書籍名 | 2days4girls |
|---|---|
| 著者名 | 村上 龍 |
| 出版社 | 集英社 |
| 発刊日 | 2003.8.10 |
| 希望小売価格 | 1900円 |
| 書評日等 | - |
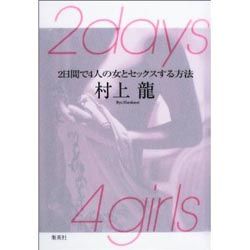
僕のまわりに村上春樹ファンの女性はいくらでもいるけれど、村上龍のファンは少ない。もっとはっきり言えば、いない。僕が、龍のほうが断然いいよと言うと、たいてい、そーお? どこが? と、うさんくさいものを見るような表情をされてしまう。
たしかに村上龍の小説は、女性に好かれない要素に満ちている。取りあげる素材も文体も暴力的だし、時にポルノグラフィーと見まがうほどにエロティックだし、マッチョな側面が無神経に顔をのぞかせたりもする。
この「2days4girls」も、設定からして女性を怒らせそうだ。主人公の「わたし」は「プラントハンター」と呼ばれている。「プラントハンター」とは、19世紀のヨーロッパで王侯貴族の求めに応じてアジアやアフリカで珍しい植物を探し、本国に持ち帰った植物学者や聖職者、ときには犯罪者である男たちのことだ。
「わたし」はバブルで資産をつくった投資家なのだが、「プラントハンター」が王侯貴族から求められたように、金持ちの男たちからの依頼で神経を病んだ彼らの愛人を預かり、彼女たちの精神を「オーバーホールする」ことを趣味的な副業にしている。
女たちはといえば、秘密クラブでSMをやっていたり、愛人として文字通り檻のなかで飼われていたりする……という出だしからして、フェミニストの目が釣りあがるさまが目に浮かぶようだ。
龍が女性に好かれない理由のひとつである暴力的で過激な描写とは、たとえばこんなふうだ。
「窓外に蛾と虫がびっしりと貼り付いたベトナムのリゾートのヴィラで、おれたちは湿気を含んだシーツに横になっていて、マキは気が遠くなるような長い時間をかけてフェラチオをした。その夜だけじゃなかった。会うときはいつもそうだった。おれは部屋をできるだけ明るくした。マキの首筋に生えている産毛までが見えるように、部屋を明るくした」
「マキは……からだを軽く拭いて、洗面台に立って、まだバスタブに浸かっているおれのほうを向いてていねいに歯を磨いた。髪の先や肘、尻の肉から水滴が垂れた。出会ってから一年が経っていたが、マキの尻の肉は微妙なカーブを描いていた。いつもおれはそれを腐る寸前の果物のようだと思ってじっと眺めた。尻の割れ目のまわりは最初会ったときより黒ずんでいた。陰毛は増えたし、陰唇も黒くなった。そのことを確認するように、おれはマキが素裸で歯を磨くところを眺めた」
途中を省略したが、引用を含めた12行ほどが改行なしで、息長くひとつながりになっている。その息の長さや露骨に男の視線から眺められた描写がいかにも龍らしいが、もうひとつ、いやそれこそがいちばんの特徴だと思うのは細密描写の素晴らしさだ。
「窓に貼り付いた蛾と虫」「首筋の産毛」「垂れる水滴」「腐る寸前の果物のような尻のカーブ」と、虫眼鏡で部分を拡大したような鮮やかなイメージ群が、リズムよく畳み込まれている。
これはいわば空間的に視覚を拡大した文章だけれど、龍は時間を拡大してまるで超スローモーションの映画を見ているような細密描写も得意としていることは、彼のファンなら先刻承知のことだ。僕は村上龍のそんな文体が好きだ。
それと表裏になるけれど、その一方で龍はあきれるくらいストーリー・テリングが下手なのだと思う。物語を複雑に動かさなければならない作品になると特にそうだ。見事な細密描写が延々とつづいて一段落し、通常の時間や空間にもどって物語を動かしはじめると、とたんに劇画のあらすじのような文章になってしまったりする。「愛と幻想のファシズム」「五分後の世界」なんかがいい例だろう。
その意味で、「コインロッカー・ベイビース」のあとがきで龍が、「瞬間を連ねること。それしかなかった。全力疾走を繰り返して42.195キロを走破するマラソン・ランナーのように書こうと思った」と書きつけたのは、デビュー3作目にしてすでに自身のタチをよく分かっていたわけだ。
それにつづけて彼は、そんなふうに書くには膨大なエネルギーが必要だが、「エネルギーの充実に最も適しているのは、私の場合、平穏な休息ではなく、ある種の錯乱であるようだ」と記している。1980年のことだ。
その後、龍はみずから錯乱を求めるように、バブルの狂乱に身を添わせながら作品を産みだしてゆくことになる。
バブルの波に乗りながら、波が砕けてゆくその波先のすぐ裏にいて、あやうくバランスを取っている姿勢。フーゾクの女たちを主人公にした「トパーズ」や、隆盛をきわめたフレンチをはじめとする料理をタイトルにあしらった恋愛小説「村上龍料理小説集」などの短編集が、この時期を代表する作品だろう(長編は先ほど言ったようなわけで失敗作が多い)。
バブル崩壊後の90年代には、自身の分身のような男ヤザキを主人公にした「エクスタシー」「メランコリア」「タナトス」の連作が書かれる。ヤザキの彷徨は、ほとんど龍自身の彷徨にちがいない。この国のバブルは崩壊したが、ヤザキの漂流の先に夢見られているのはヨーロッパの洗練と退廃だ、と僕は思う。
金と時間をたっぷりかけなければ見えてこない世界がある。それは金と時間をかければ必ず見えるものではないが、金と時間なしには成り立たない。この国の文学は、そういうものに対して無関心だった。青春や貧乏にばかり気を取られていた。
そんな村上龍の姿勢は、たとえば隠者の文学として、ひとつところから動かず永遠の青春小説を紡ぎつづける村上春樹と比べるとき、ひときわ挑戦的に映る。バブルとその崩壊に進んで身をさらし、美食でぱんぱんになったからだをアルマーニに包んだ村上龍は、ウィーンの観覧車の上から街を見下ろしているオーソン・ウェルズなのかもしれない。
などと先走ってしまったが、「2days4girls」に戻れば、これは90年代の「ヤザキもの」に連なる作品だ。最初に引用した文章の一人称「おれ」は主人公「わたし」の友人で、「快適な人生を味わえば人格は変わるはずだ」とうそぶいてSMクラブの女を買い、彼女に高価な服を着せたり、高いレストランで食事をしたり、ファーストクラスで旅行に連れていったりして「女を変える快楽」を楽しんでいる。
「わたし」はその結果こわれてしまった女を引き取り、「信頼」や「自己評価を高める」ことや「自分を好きになる」ことを教えようとするのだが、当然のことながらうまくいかない。
ポストモダンな投資家である「わたし」が柄にもなく教育者や医者といった「近代」的役割を果たそうとする設定にそもそも無理があることは、「わたし」の独白より、バブルの申し子のような「おれ」の独白に圧倒的なリアリティーと迫力があることからも分かる。「わたし」は「おれ」に負けている。「おれ」は「わたし」以上に村上龍なのだ。
植民地主義の産物である「プラントハンター」の延長線上に成立した民族学や文化人類学は、20世紀に入って、辺境への好奇心を生みだし、辺境からの収奪を先導したヨーロッパの知それ自身へと疑いの目を向けていった。
同じように「わたし」も、壊れた女を救おうなどと大それたことを試みた結果として(「わたし」は女を「救う」のではなく「関与するのだ」と言っているが)、女に逃げられ、彼女をさがして広大な庭園をさまよい歩く。
微妙に変化しながら螺旋状に繰り返されるそのさまよいの細密描写が、この小説のもうひとつの魅力なのだが、結局、「わたし」は探している女には出会えず、自身の無力感と疲労と幼児期の記憶とに向かい合うことになる。
この小説には、だから救いも癒しもやってこない。やっぱり村上龍は女性には好かれないのだ。
蛇足。サブタイトルに「2日間で4人の女性とセックスする方法」とある。おそらく編集者の提案だろうが、最悪。つくった本を売ることは編集者の大切な仕事だから、そのためにタイトルやサブタイトルを工夫するのは当然のこと。でも、このセンスのなさにはあきれてしまう。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





