堕天使殺人事件【ボリス・アクーニン】
堕天使殺人事件
| 書籍名 | 堕天使殺人事件 |
|---|---|
| 著者名 | ボリス・アクーニン |
| 出版社 | 岩波書店(326p) |
| 発刊日 | 2015.06.25 |
| 希望小売価格 | 2,052円 |
| 書評日 | 2015.08.17 |
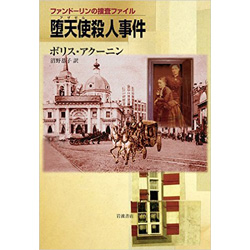
ロシアのSFはストルガツキー兄弟はじめ豊かな伝統があり、『ストーカー』とか『神々の黄昏』とか映画にもなっているけれど、ロシアのミステリーというのは読んだことがない。書店でぱらぱらページをめくって、19世紀ロシアを舞台にした歴史ミステリーらしいとわかって食指が動いた。
ボリス・アクーニンという名前からして、なにやら怪しげだ。訳者解説を読むと、アクーニンというペンネームは日本語の「悪人」から取ったという。もともと日本文学に通じ三島由紀夫をロシア語訳したジャパノロジストで、本名はグリゴーリイ・チハルチシヴィリ。彼がアクーニンの名前で、モスクワ警察特捜部のファンドーリンを主人公に出版した本書がベストセラーになり、その後発表された「ファンドーリン・シリーズ」はロシアで大ブームを巻き起こした。テレビドラマ化や映画化もされたそうだ。本書は1998年に発表されたその第1作。
1876年、モスクワ。帝政ロシア末期、ナロードニキ運動が活発になって社会が揺らぎはじめた時代である。ある日、市内の公園で、大富豪の相続人でモスクワ大学の学生ココーリンがロシアン・ルーレットでピストル自殺を図る。ポケットからは「ふとどきな無神論的内容のメモ」が発見された。新米捜査官のファンドーリンが話を聞いてまわると、ココーリンは貴族の屋敷に住む美女アマリヤが開くパーティに出席していたことがわかる。彼女の屋敷には怪しげな伯爵が出入りし、ファンドーリンはなにやら秘密結社が関係していると睨む。
ところがこのファンドーリン、美女にからきし弱い。アマリヤにいいようにあしらわれる。「『大胆な人は好き』彼女はうす笑いを浮かべた。『とくにこういうハンサムな男性の場合はね。でも、そっとあとをつけるなんて、みっともないわ。私のことがそんなに気になるのなら、夜あらためていらっしゃい』」
ウェストを絞る男性用コルセットを装着し、燕尾服に身をかためてアマリヤの邸宅を訪れたファンドーリンはゲームに勝って、アマリヤに質問でき彼女が正直に答えなければならない権利を得る。「『ココーリンの死について何かご存知ですか』……『ココーリンを殺したのは、とても残酷なある女性です』一瞬にして黒くて濃いまつげをふせ、その下から細い剣の一撃のようなまなざしで刺してきた。『その女性の名は<恋>よ』」
いいようにあしらわれているが、ここからファンドーリンは、やはりアマリヤに首ったけだった別の学生が殺された際に呟く「アザゼル(堕天使)」という言葉を追って、ロシア上流階級を舞台にした秘密結社の犯罪に深入りしていくことになる。「アザゼル」と呼ばれる国際秘密組織は皇太子暗殺を目的にしているらしい。モスクワからロンドンへ、サンクト・ペテルブルクへ、ファンドーリンの冒険と恋の物語が始まる。
この小説を貫いているのは古き良きロシアへのノスタルジーである。優雅な社交や服装、まだ貴族階級の秩序と美意識が残っていた時代、現在のロシアの読者は、やがて失われ今では追憶の対象でしかない旧世界の感触に心地よさを感ずるのだろう。でもそんな貴族的生活の背後にはテロと革命がひしひしと迫っていた。この小説はその両面を素材にしている。また自殺するモスクワ大学生というエピソードは、当時、都市部で流行していた若者の自殺(彼らはニヒリストと呼ばれた)という事実に裏打ちされている。
19世紀後半のロシアはトルストイやドストエフスキーの小説で馴染みのある時代だけれど(本文中にもドストエフスキーの名前が出てくる)、僕がこの小説を読んで思い出したのは、ロープシンのペンネームで『蒼ざめた馬』を書いたサヴィンコフの回想録『テロリスト群像』(現代思潮社)だった。
サヴィンコフがリーダーとしてテロを指揮した社会革命党(エス・エル)戦闘団は20世紀初頭に結成されたが、その前身ともいえるナロードニキの「土地と自由」人民の意志派は、まさにこの小説の舞台となる時代にテロを敢行していた。1878年、警視総監にピストルで重傷を負わせ、81年には皇帝アレクサンドル2世を暗殺。そういう時代背景があるからこそ、ロシアの読者はこの小説にリアリティを感ずるのだろう。
『テロリスト群像』のなかで、サヴィンコフと女性テロリストの間でこんな会話が交わされる場面がある。「『あなたはなぜテロに参加するのですか?』彼女は、すぐには答えなかった。……彼女は黙って机に近づき、聖書を開いた。『汝ら、汝らの魂を救わんと欲せば、必ずや死に至らん。もし汝らの魂をわれのために捨つるならば、汝らの魂は救われん』」
ドストエフスキーもそうだけれど、テロや犯罪を行う人間たちが魂の救済について哲学的問答を交わすのはロシア文学の伝統といえるだろうか。そんな「テロリストの悲しき心」(石川啄木)は、同時代の日本でも多くの人間の心を掴んだ。本書でも、秘密組織の首領である女性とファンドーリンとが革命とその手段としての殺人をめぐって問答する場面が登場する。ただし、ドストエフスキーのように長く徹底した問いと答えではなく、現代的でスピーディに処理されているが。総じてこの小説には、ドストエフスキー的設定をポップにし、場面転換の早いエンタテインメントに仕立て直した趣がある。
訳者(沼野恭子)によると、現在十二巻まで出ているファンドーリン・シリーズは、各巻ごとに犯罪小説のさまざまなジャンルとスタイルを意識的に取り入れた「知的エンタテインメント」だという。本書『堕天使殺人事件』は非合法活動小説、第2作『トルコ捨駒スパイ事件』はスパイ小説、第3作『リヴァイアサン号殺人事件』は密室殺人小説、第4作『アキレス将軍暗殺事件』は暗殺者小説といった具合。しかも本書がそうであるように、時代考証のしっかりした歴史小説でもある。また僕がドストエフスキーやサヴィンコフ(ロープシン)を思い出したように、19世紀ロシア文学へのオマージュでもある。
第6作『五等官』は映画化され、巨匠ニキータ・ミハルコフが製作し、フィリップ・ヤンコフスキーが監督している。人気俳優のオレグ・メンシコフがファンドーリンを演じ、ニキータ・ミハルコフ自身も役者として出演し主役を食っているそうだ。見てみたいものだ。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





