東京の空の下、今日も町歩き【川本三郎】
東京の空の下、今日も町歩き
| 書籍名 | 東京の空の下、今日も町歩き |
|---|---|
| 著者名 | 川本三郎 |
| 出版社 | 講談社(240p) |
| 発刊日 | 2003.11.10 |
| 希望小売価格 | 1800円 |
| 書評日等 | - |
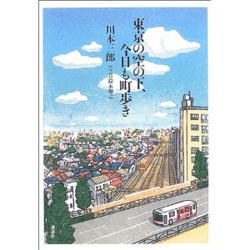
会社員生活というのは、人生の3分の1を会社に売り渡している。1日24時間のうち8時間を生活のために切り売りし、残りの16時間で食べ、眠り、家族としゃべったりテレビを見たりする。往復の通勤時間だって馬鹿にならない。となると、遊びや趣味に時間を費やせるのは週末ということになる。
遊びや趣味は本来、無為の時間に属するものだから、日常の時間の流れからはずれている。でも、限られた時間のなかで遊びや趣味に時間を使うには、本来そんなものとは無縁のはずの優先順位なんてことを、ついつい考えてしまう。あれもこれもと好奇心が湧いても、「もう少し暇になったら。定年になったら」と自分を納得させて我慢する(定年になった人に聞くと、定年後というのは実に忙しいらしいのだが)。
そんなふうに我慢していることのひとつに、町歩きがある。仕方がないから、町歩きの本を読んで小さな旅をした気分になる。東京の町歩きについていえば、永井荷風から田中小実昌や種村季弘まで、よりどりみどりだけれど、同時代と同世代の風を感じさせるものといえば写真の荒木経惟、文章の川本三郎に止めを刺す。
「東京の空の下、今日も町あるき」で川本三郎は、東京の山の手や下町のもうひとつ外側、かつての郊外を歩いている。西は阿佐ヶ谷、荻窪から八王子、青梅、東は亀戸、新小岩、業平橋、曳舟、北は板橋、赤羽、南は池上、蒲田、羽田などなど。主に関東大震災後に市中から人々が移って形成された新開地。
例えば板橋を、川本はこんなふうに歩く。まずお昼時に、東武東上線の大山駅で下車。「東京のローカル線」のような駅前商店街を歩きながら洋食屋を探して(蕎麦屋に入ることも多い)ハンバーグライスのお昼。そこから個人商店が連なる商店街から商店街へと、伝い歩きを始める。「東京の町は、行けども行けども商店街が続く」「東京は小さな商店街の集積でできている」といった感想が差しはさまれる。
商店街の裏側の住宅地も歩く。生け垣のある家が並んでいる。彼は、東京の町並みを支えているのは個人住宅だという小林信彦の、こんな一節を呼び出す。「街作りについてなんのポリシーも持たない今の東京で、辛うじて<美>あるいは<趣味>を感じさせるのは、新旧を問わず、個人の住宅である」。
板橋は町工場の多い土地でもある。板橋に工場がつくられたのは、明治時代に荒川の水運を利用した火薬製造所ができてから。そんな歴史をさり気なく披露しながら、この工場地帯にロケした日活の青春歌謡映画「あゝ青春の胸の血は」が思い出される。
地下鉄で高島平へ移動して、「東京大仏」を見たり、小さな植物園に入ったりもする。「珍種よりも、日本のどこにでも見られる普通の木や花を植えているのは好感が持てる。これが植物園の基本だと思う」とつぶやく。
5時間ほども歩けば黄昏どき、好物のビールが恋しくなる時間。ときわ台の駅前に戻って、居酒屋を探す。「いい居酒屋の条件は「品書きが多いこと」と決めている」。ビールと新じゃが揚げで一杯やり、「いい居酒屋が多いのは、工場の多い町だから」という事実に思いいたる。
このエッセーは雑誌「東京人」に連載されたもので、その夜は町の旅館やビジネスホテルに1泊するという贅沢なもの。翌日は荒川土手まで足を延ばし、東京町歩きの古典ともいうべき永井荷風の「断腸亭日乗」や「放水路」が引用されて、ささやかな旅は終わる。
こんなふうに町から町を歩く川本から「町歩き術」を学んでみれば――。
- いきなり目的地へ行くのはもったいないから、少し遠回りする。駅なら一駅手前か一駅先で下りる。
- 目標とする場所のだいたいの方角を確認したら、地図を見ないで歩く。迷うことから発見があるし、そのうちに目標に着く。
- 古本屋を見つけたら、必ずのぞいてみる。
- 銭湯に入れるよう、タオルを持っていく。
- ひとりでも居心地のよさそうな居酒屋を見つける。「品書きの多い店」がよい。ただし長っ尻は禁物。
- 他人様の町に入り込むのだから、できるだけ目立たず、静かにする。
川本には、町歩きしながら「断腸亭日乗」を読み解いた傑作「荷風と東京」があるし、この本の正編ともいうべき「私の東京町歩き」もある。前者は町歩きというよりは文学論だし、後者は主に下町を歩いているが、紀行でありながらもそれぞれの町を論ずる姿勢が見える。町が激しく変貌したバブルの真っ最中に書かれているから、下町への思い入れがやや過剰にも思える。
それらに比べるとこの本は肩の力も抜け、町から町へ、路地から路地へと何の気負いもなく歩いている川本の楽しそうな貌が浮かんでくる。大正・昭和の都市小説を隈無く読み、黄金期の日本映画を山ほど見た蓄積が、ごく当たり前のように顔をのぞかせる。そのさり気なさが好ましい。
うーん、つまらぬ我慢など捨てて、次の休みには気になる町へ出かけていこうか。(雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





